吉川生美
| きっかわ・いきみ | 生20131228没 | 享年92 |
| 爆心地から約1・6キロの現広島市中区西白島町で被爆。夫の「原爆1号」と呼ばれた故吉川清とともに、戦後のヒロシマを生き抜く。 | ||
吉川生美
| きっかわ・いきみ | 生20131228没 | 享年92 |
| 爆心地から約1・6キロの現広島市中区西白島町で被爆。夫の「原爆1号」と呼ばれた故吉川清とともに、戦後のヒロシマを生き抜く。 | ||
閃光を背負って―原爆第一号の足跡(毎日新聞(広島版)連載1989年8月16日~9月6日
| 回 | 掲載月日 | 見出し1 | 見出し2 |
| 1 | 0816 | 署名運動 | 救済求め手を組もう |
| 2 | 0817 | 請願書 | 最初は”外注”友人に依頼 |
| 3 | 0818 | 被爆者の叫び1 | 「このケロイドを見よ」 |
| 4 | 0819 | 被爆者の叫び2 | 東京でも体験語る |
| 5 | 0822 | 被爆者の叫び3 | 被害者の会を脱退 |
| 6 | 0823 | 八・六友の会 | すべてと仲良く |
| 7 | 0824 | 抗議 | 広島の人間として |
| 8 | 0826 | あがき | 自分が手がけたのに |
| 9 | 0830 | 吉川清の思い | この”肩書”ずしりと |
| 10 | 0831 | 歩み・上 | 権利の主体へと |
| 11 | 0902 | 歩み・中 | 土産物店など経営 |
| 12 | 0902 | 歩み・下 | ぐち口にせず往生 |
広島大学勤務期の日録(抄)
| Y | M | D | 事項(敬称略) |
| 77 | 04 | 30 | 被爆問題国際シンポジウム広島準備委員会社会科学委員会(第1回) |
| 78 | 02 | 10 | ミーティング。栗原訪韓(31日~7日)報告。 |
| 03 | 03 | ミーティング。話題-栗原発言=復元事業に対する厚生省の補助は53年度までで打ち切り。復元資料は市から借用している。復元資料は市では証拠能力をもつとは見ていない。復元資料の閲覧はケースバイケース。 | |
| 03 | 25 | 『原爆モニュメント碑文集』(原爆モニュメント研究グループ編・刊)。 | |
| 03 | 31 | 「米国戦略爆撃調査団について-調査報告と収集資料を中心に」(『広島県史研究』3) | |
| 07 | 15 | 広島原爆被災撮影者の会(於広島YMCA)<発足>
『広島壊滅のとき―被爆カメラマン写真集』(1981年刊) |
|
| 08 | 06 | 「NYタイムズ原爆関係記事目録(1)」(『広島ジャーナリスト』78)
「同(2)」(『同』79、19781225)、「同(3)」(『同』80、19790220) |
|
| 79 | 03 | 31 | 「原爆と市民-米国戦略爆撃調査の再検討」(『広島市公文書館紀要』2) |
| 06 | 30 | 「マンハッタン・プロジェクトのプレス・リリーズ」(『広島ジャーナリスト』80) | |
| 07 | 25 | 『広島長崎の原爆災害』(広島市・長崎市原爆災害誌編集委員会編)岩波書店。 | |
| 80 | 03 | 19 | 湯崎送別会。4月1日より総合科学部に転出。 |
| 04 | 20 | 「広島市の平和意識」(『ひろしまの地域とくらし』9(自治体問題研究所広島研究会)) | |
| 04 | 26 | 藤居平一日本被団協初代事務局長との出会い。
「原爆被害問題研究の恩師」(『人間銘木 藤居平一追想集』(藤居美枝子、1997年4月刊)) |
|
| 05 | 01 | 文部省内地研究員として一橋大学へ出張(~1981年2月28日). | |
| 12 | 「広島の原爆被災資料収集状況」(『現代史通信』17) | ||
| 81 | 03 | 31 | 『広島新史資料編Ⅰ-都築資料』(広島市編・刊) |
| 06 | 25 | 『平和教育実践事典』(広島平和教育研究所編)労働旬報社 | |
| 08 | 25 | 湯崎稔,志水清,栗原登,務中昌己,早川式彦,山本脩,渡辺正治,上岡洋史,宇吹暁,大瀧慈「原爆による家族破壊-「原爆被災復元調査」の成果を通して」(「広大原医研年報22」) | |
| 10 | 01 | *、初出勤。(藤居のテープや資料の整理をして貰うことになる) | |
| 82 | 「原爆医療法の成立」(『広島大学原爆放射能医学研究所年報』23) | ||
| 82 | 「日本における原水爆禁止運動の出発-1954年の署名運動を中心に」(『広島平和科学5』)(広島大学平和科学研究センター) | ||
| 03 | 31 | 『広島新史資料編Ⅱ-復興編』 | |
| 04 | 「日本における原水爆禁止運動の前提-「被爆体験」の検討」(『日本史研究』236) | ||
| 10 | 25 | 『広島県大百科事典』(中国新聞社編・刊) | |
| 83 | 03 | 31 | 「原水爆禁止世界大会に関する覚書」(『広島県史研究』8) |
| 04 | 広島大学職組書記長。1984年度委員長。~1985年5月4日、解任。
<高血圧と心筋梗塞> |
||
| 05 | 31 | 「「被爆体験」の展開-原水爆禁止世界大会の宣言・決議を素材として」(『芸備地方史研究』140) | |
| 07 | 15 | 『資料‘82反核-原爆文献を検証する』(「ひろしまをよむ」会編、渓水社) | |
| 84 | 03 | 03 | 志水清より資料寄贈(本人持参)(第1便) |
| 03 | 08 | 志水資料の大まかな整理。 | |
| 06 | 11 | 湯崎稔死亡。13日、廿日市光禅寺で葬儀。<自らの死の不安> | |
| 06 | 16 | 『原爆被災資料総目録 第4集』(原爆被災資料広島研究会編集部会(石井浩史・宇吹暁・島津邦弘・田原幻吉・丹藤順生・ピカ資料研究所)・ピカ資料研究所)編集。原爆被災資料広島研究会刊) | |
| 07 | 08 | 広島大学会館運営協議会協議員(=1985年7月7日) | |
| 07 | 23 | 今堀より依頼=平和文化センタ-の資料調査研究委員会に湯崎のかわりに委員になって欲しい。被爆体験テープの取りまとめ。 | |
| 07 | 11 | 原医研将来検討委員会(第1回)~第52回(最終回)(1992年6月10日) | |
| 08 | 08 | 栗原より話。総合科学部*より湯崎の資料のうち復元関係資料を整理して欲しいとの依頼があった由。8月21日、総合科学部社会文化図書室。湯崎資料を見る。地図10数筒、電算機打ち出し約30ケース。9月17日総合科学部で芝田進午と会う。湯崎の地図だけ原医研で引き取ることで了解。
10月17日総合科学部より湯崎の地図を引き上げる。 |
|
| 09 | 01 | 財団法人広島平和文化センター原爆被災資料調査研究委員会 | |
| 11 | 30 | 『広島新史歴史編』(広島市編・刊)[監修]今堀誠二、[執筆者]小堺吉光、宇吹暁、天野卓郎、藤原浩修、頼祺一、今堀誠二。 | |
| 12 | 11 | 「予算からみた原爆被爆者対策の変遷」(『ヒバクシャ-ともに生きる』3) | |
| 85 | 03 | 21 | 「原爆報道の軌跡-新聞記事の量的側面の検討」(『広島市公文書館紀要』8) |
| 07 | 10 | 「原医研が歩んできた道」(『学内通信 (広島大学)』242)
著者:栗原登・務中昌己・宇吹暁 |
|
| 08 | 15 | 「原爆資料をめぐって」(『広島市医師会だより』232) | |
| 10 | 18 | 「軍縮と市民運動-日本の原水爆禁止運動をめぐって」(『国際政治(日本国際政治学会)』80) | |
| 10 | 25 | 『平和事典』(広島平和文化センター編)勁草書房 | |
| 12 | 25 | 「被爆40年の広島の現状と課題(上)」(『ひろしまの地域とくらし』73)
「同(中)」(『同』74、1986年1月)、「同(下)」((『同』75、2月) |
|
| 86 | 02 | 01 | 「原爆についての広島市民意識」(『歴史地理教育』393) |
| 03 | 04 | 志水清より資料寄贈(第2便)。 | |
| 03 | 31 | 『原爆被爆者等面接記録-米国戦略爆撃調査団資料(テープ部門)』(財団法人広島平和文化センター) | |
| 05 | 10 | 広島県戦災史編集委員会<『広島県戦災史』(1988年6月刊)> | |
| 06 | 01 | 「新聞の「記録性」を考える」(『新聞研究(日本新聞協会)』419) | |
| 06 | 21 | 湯崎家より資料借用。6月27日、湯崎資料整理。*、内田、石田。
25日、*(広島・長崎平和基金)来所.湯崎資料整理。 |
|
| 06 | 30 | 「原爆被災資料をめぐって」(『ヒバクシャと現代 地域と科学者(日本科学者会議広島支部』第8号) | |
| 07 | 01 | 広島大学文書保存委員会専門委員会専門委員。<1988年からか?>。~1990年3月31日(任命権者:沖原豊)~1992年3月31日(任命権者:田中隆荘) | |
| 87 | 07 | 平和会館資料借用。 | |
| 88 | 04 | 11 | 財団法人広島平和文化センター専門委員(委嘱者:荒木武)
『平和記念式典の歩み』(1992年刊) |
| 04 | 財団法人広島平和文化センター原爆映画製作委員会 | ||
| 05 | 19 | 古川博(中国・東京支局)より電話。平凡社年鑑の執筆の引継を依頼される。89年4月14日「反核運動1988」(『平凡社百科年鑑』)。以後、「反核運動1998」まで執筆。 | |
| 06 | 17 | 内田恵美子、休暇に入る。30日、日赤に内田を見舞う。 | |
| 09 | 02 | 中国地域データベース推進協議会データベース標準化部会 | |
| 11 | 04 | 栗原登中国文化賞受賞祝賀会。 | |
| 12 | 23 | 「あらたな意味をもつ被爆体験の継承」(『人間の心ヒロシマの心』(秋葉忠利編)三友社出版) | |
| 89 | 03 | 18 | 栗原最終講義。4月1日栗原と話す.家族票について. |
| 04 | 04 | 秦野裕子入院。 | |
| 04 | 吉川清資料借用(1989年4月~) | ||
| 11 | 01 | 蔵本淳所長より、助教授の辞令。 | |
| 11 | 10 | 財団法人広島平和文化センター平和関係施設調査研究委員会。 | |
| 12 | 10 | 児玉克哉、湯崎資料を見に来所。湯崎の論文関係の箱(1箱)を持ち帰る。 | |
| 90 | 04 | 01 | 原爆放射能医学研究所附属原爆被災学術資料センターの危害防止主任者(任命権者:田中隆荘)。
広島総合科学部講師(併任) |
| 08 | 31 | 「原爆症の調査・研究・治療の再開-原爆医療法前史への覚書」(『広島大学原爆放射能医学研究所年報』31) | |
| 11 | 20 | 「第29回オマール氏法要」(『広大フォーラム(広島大学広報委員会)』) | |
| 11 | 25 | 「過去15年間の原爆報道(新聞)の検討」(『長崎医学会雑誌』65特) | |
| 91 | 03 | 05 | 内田恵美子、午後8時24分日赤病院で死亡。 |
| 07 | 24 | 志水清死亡。26日、死亡連絡入る。「復元の最も良質の精神が無くなった」「ヒロシマの枠組みは存在するものの,その良質の精神(例えば志水清や藤居平一に体現されていた)は,次第に失われている.現在の被爆体験の継承というスタイルでは,本当に継承できるとは思えない.必要なのは「継承」というより「構築」ではないか.」 | |
| 07 | 23 | 広島市被爆建物等継承方策検討委員会。~1992年7月15日。 | |
| 91 | 「原爆関連文献資料のフルテクスト・データベースの構築の試み」(『広島平和科学 14』メンバー:松尾雅嗣・宇吹暁・川崎信文・好村富士彦・田村佳子・舟橋喜恵) | ||
| 92 | 01 | 00 | 志水清資料=目録の出版。湯崎稔資料=選別と返却 |
| 02 | 「公的機関・団体の原爆資料(非医学的資料)」 | ||
| 03 | 25 | 『平和記念式典の歩み』((財団法人広島平和文化センター) | |
| 04 | 17 | 秦野裕子、死亡。39才。 | |
| 05 | 14 | 芝田の話=湯崎の論文集を中国新聞社の創立100周年の記念出版として出版してもらうよう交渉している。芝田は来年3月で停年退官。 | |
| 06 | 01 | 広島大学大学院医学系研究科担当(任命権者:田中隆荘) | |
| 06 | 12 | 資料センタ-教官会議。教授会報告(早川)、今週の業務、来週の予定、宇吹報告。提出資料=「資料調査通信」最終号・センタ-概況年報別冊・AFIP返還資料報告書・センタ-蔵書目録3冊・センタ-要覧(和英)・秦野論文・宇吹「資料センタ-の現状と将来について」。 | |
| 06 | 20 | トゴーで散髪。「銭型禿」まだ治らず。 | |
| 09 | 01 | 厚生省委託原爆死没者慰霊等調査研究啓発事業
原爆資料および情報ネットワーク委員会・被爆者対策資料小委員会委員 (委嘱者:重松逸造=放射線影響研究所理事長)。~?。1996年10月1日付の委嘱状まで。 |
|
| 09 | 18 | 広島県旧陸軍被服支廠保存・活用方策懇話会(第1回) | |
| 10 | 27 | 広島修道大学非常勤講師(~11月30日) | |
| 11 | 10 | 『戦争と平和の理論』(芝田進午編、勁草書房刊) | |
| 11 | 19 | 所内回覧済みの本・紀要類と志水清の本類の処分。 | |
| 93 | 03 | 01 | *(広島市平和記念館)・*(平和文化センタ-)、来所。「広島平和記念館展示物・説明文」の執筆依頼。 |
| 03 | 1 | 広島市博物館(仮称)展示検討委員会専門部会委員 | |
| 03 | 29 | 広島大学研究・教育 資料・機器類の基礎的調査研究プロジェクト『広島大学研究・教育 資料・機器類調査報告書』(1993年3月29日) | |
| 03 | 31 | 「原爆被害者の証言と平和教育-文集を読んだ感想にかえて」(『若い世代に被爆体験を語り継ぐために-平和学習の感想文集』(被爆体験証言者交流の集い世話人会、1993年)所収) | |
| 03 | 広島大学原爆放射能医学研究所『原爆被爆者資料のデータベース化 平成4年度広島大学教育研究学内特別経費による研究報告』 | ||
| 04 | 01 | 広島大学平和科学研究センター運営委員会運営委員。 | |
| 04 | 07 | *の話=湯崎資料を2箱預かっている。 | |
| 94 | 01 | 20 | *(中国新聞社長秘書役)から1977年原水禁統一前後の資料を預かる。 |
| 02 | 09 | 新聞切り抜き関係の仕事が終わった後の業務として、*に志水資料目録の入力、*に未登録の刊本の整理を頼む。 | |
| 03 | 28 | 「商用データベースと『原爆・被爆』情報」(『広島医学』47-3 ) | |
| 06 | 24 | 広島大学助教授原爆放射能医学研究所附属国際放射線情報センターに配置換(任命権者:原田康夫) | |
| 07 | 27 | 第1回統合移転記念事業実行委員会広報部会。於旧総合科学部第2会議室。
編集長:難波紘二。 |
|
| 09 | 01 | **(広島市原対部調査課)、来所。早川とセンターで援護史に関する資料について説明。志水資料の衛生局長時代の資料を貸す。14日**来所。志水資料を返却。国会会議録のコピーを持ち帰る。*が28日の大阪朝日の調査に同行するとのこと。 | |
| 09 | 30 | 早川の話=資料センターの教授選考で星が決まった由。 | |
| 12 | 21 | 広島市「米国スミソニアン協会航空宇宙博物館の特別展について意見を伺う会」 | |
| 95 | 03 | 31 | 広島大学研究・教育総合資料館研究報告第1号(広島大学) |
| 04 | 01 | 広島大学医学部講師(併任) | |
| 04 | 29 | 「日本原水爆被害者団体協議会の結成」(『日本社会の史的構造-近世・近代』(朝尾直弘教授退官記念会、思文閣出版)) | |
| 07 | 05 | 「被爆50周年を迎えて-現状と課題」『ひろしまの地域とくらし』177 | |
| 07 | 21 | 「核兵器廃絶の世紀へ」(『年表・ヒロシマ-核時代50年の記録』(中国新聞社)) | |
| 07 | 28 | パグウォッシュ会議全体会議。「核兵器の効果」。B・バーンステイン、飯島宗一。 | |
| 07 | 28 | 原医研国際シンポジウム。「セミパラチンスク近郊住民の放射線被曝とその問題点」。於医学部第4講義室。秋山実利(司会)・ローゼンソン・リスコフ・山下俊一・星正治・今中哲二・佐々木正夫・早川式彦。 | |
| 08 | 01 | 「被爆50周年とヒロシマの動き」(『日本の科学者』30-8) | |
| 08 | 21 | 統合移転史の後半部分の原稿を仕上げ、借用資料とともに学内便で*(企画調査)へ送る。統合移転史関係の資料をまとめて収納。書き上げて見ると、無理やり、やらされた仕事ではあってもそれなりに得るものはある。 | |
| 10 | 01 | 『広島大学公開講座・被爆50年-放射線が人体に与えた影響』 | |
| 11 | 01 | 『翔べ!フェニックス-広島大学統合移転完了記念誌』 | |
| 11 | 28 | 「被爆体験と平和運動」(『戦後民主主義-戦後日本・占領と戦後改革第4巻』(岩波書店)) | |
| 96 | 03 | 30 | 広島大学博物館研究報告(旧広島大学研究・教育総合資料館研究報告)第2号(広島大学) |
| 03 | 31 | 『街と暮らしの50年-被爆50周年 図説戦後広島市史』 | |
| 04 | 01 | 広島大学大学院国際協力研究科講師(併任) | |
| 07 | 23 | 原医研第2回国際シンポジウム。特別講演。重松・佐々木。 | |
| 07 | 25 | 「[座談会]木の葉の歴史を語る」(『木の葉のように焼かれて』第30集) | |
| 09 | 28 | 健康診断の結果は、「心電図に異状あり」。 | |
| 10 | 15 | [シンポジウム:あらためて原爆遺跡保存を考える質疑・討論](『芸備地方史研究』) | |
| 10 | 20 | 「被爆50年の中の原爆展の位置」(『「原爆展」掘り起こしニュース』6) | |
| 12 | 『原爆手記掲載書・誌一覧』(IPSHU(広島大学平和科学研究センター)研究報告シリーズ研究報告No.24 ) | ||
| 97 | 02 | 『原爆被爆者対策史の基礎的研究-原爆被爆者対策史資料集(1945年~1953年)平成6-8年度科学研究費補助金(基礎研究c2)研究成果報告書 課題番号06610313』 | |
| 03 | 28 | 広島大学博物館研究報告(旧広島大学研究・教育総合資料館研究報告)第3号(広島大学) | |
| 04 | 10 | 「原爆被爆資料をめぐって」(『長崎平和研究』1) | |
| 04 | 17 | 「原爆被害問題研究の恩師」(『人間銘木 藤居平一追想集』) | |
| 05 | 20 | 「保存運動の到達点-どう生かすかが課題」(『原爆ドーム・ユネスコ世界遺産-21世紀への証人』、中国新聞社) | |
| 06 | 01 | 第38回原爆後障害研究会(広島国際会議場)。-9時41分まで、座長を無事務める。すぐに帰宅。 | |
| 06 | 02 | 年休を取って、共済病院へ。9時、胃カメラを飲む。食道から胃にかけてひどい潰瘍。薬を大量に貰う。 | |
| 07 | 25 | 原医研国際シンポジウム。於広仁会館。 | |
| 08 | 01 | 「INTERVIEW「地域では独自に体験を遺している」」(『放送文化1997.8』(日本放送出版協会)) | |
| 09 | 『被爆関連文献のフルテクスト・データベースの作成・検索・分析の研究
平成7-8年度科学研究費補助金(基礎研究B1)研究成果報告書 課題番号07309010』(松尾雅嗣・宇吹暁・田村佳子・濱谷正晴・舟橋喜恵) |
||
| 98 | 02 | 04 | 広島大学50年史編集専門委員会。事務局2F会議室。頼委員長より幹事になるよう依頼される。 |
| 04 | ホームページ『ヒロシマ通信』開設(1998年4月~)。
1999年8月1日~6日のアクセス数90件。7日現在5173件。 |
||
| 07 | 05 | 「原爆資料の今後をめぐって」(『ひろしまの地域とくらし』212) | |
| 10 | 01 | 広島女子大学講師(任命権者:藤田雄山) | |
| 10 | 12 | 原医研国際シンポジウム(第1日)。於国際会議場。~14日。 | |
| 99 | 03 | 31 | 『図録・広島平和記念資料館-ヒロシマを世界に』(広島平和記念資料館。監修:葉佐井博巳、宇吹暁、井出三千男) |
ビル・シェリフ
| ビル・シェリフ | 1927生200905没 | 享年82 | オーストラリア陸軍入隊(1945年4月)後、1948年2月~1953年3月、英連邦占領軍の一員として日本で勤務。 |
資料
| 『広島大学文書館蔵 ビル・シェリフ関係文書目録』(広島大学文書館、2014年2月) | |
広島大学文書館蔵『大牟田稔関係文書目録』(広島大学文書館)
| 発行年月 | |
| 資料編1 | 2013年2月 |
| 資料編2 | 2014年2月 |
| 個別編 | 2015年2月 |
| 書籍・雑誌編 | 2016年2月 |
金井利博
| かない・としひろ | 19140101生 19740616没 | 享年60 |
| [52広島平和問題談話会](中国新聞社学芸部記者)。中国新聞社取締役論説担当。原爆被災白書運動を提唱。[69原爆被災資料広島研究会]。『広島県現代文学事典』 | ||
止
案内状(宇吹宛)にみるヒロシマの動向 <注:「発行年月日」は、消印による>
| 発年月日 | 事項 | 発 | 形態 |
| 19710819 | <原災研例会お知らせ>ゲスト:小堺吉光(広島市戦災誌編集長、平和資料館主査)。議題:第3集編集進行報告ほか。日時:8月27日、場所:平和記念館。 | 原爆被災資料広島研究会 | 葉書 |
| 19710910 | <原災研例会お知らせ>ゲスト:佐々木英男(広島市平和文化センター局長)「平和文化センターの新構想について」。議題:今後の原災研の方針について。日時:9月17日。場所:平和記念館。 | 原爆被災資料広島研究会 | 葉書 |
| 19711021 | <原災研例会お知らせ>ゲスト:河村虎太郎(河村胃腸科内科病院長)「韓国へ原爆被爆者を往診して」。議題:原災研の会員増募について。日時:10月29日。場所:広島大学会館。 | 原爆被災資料広島研究会 | 葉書 |
| 19711120 | <原災研例会お知らせ>ゲスト:渡辺孟「原医研データ・バンクについて」。議題:東京・広島・長崎に原爆被災資料センター設置など、政府に対する学術会議の韓国決議について。日時:11月26日。場所:広島大学原爆放射能医学研究所。 | 原爆被災資料広島研究会 | 葉書 |
| 19711213 | <原災研例会お知らせ>ゲスト:佐々木雄一郎「原爆写真あれこれ」。議題:広大原医研・被爆者調査の充実について、市民の協力態勢を展開する可能性にかんして。日時:12月17日。場所:中国新聞ビル。 | 原爆被災資料広島研究会 | 葉書 |
| 19720121 | <原災研例会お知らせ>ゲスト:熊田重邦(広島県史編纂室長)宇吹暁(同室員)「広島県史原爆資料編の編纂をめぐって」。議題:「原爆被災資料センター」の実現の可能性について。日時:1月28日。場所:中国新聞ビル。 | 原爆被災資料広島研究会 | 葉書 |
| 19720518 | <原災研例会お知らせ>ゲスト:空辰男(宇品中学校)、脇田充子(袋町澄学校)「原爆を教室でどう教えるか」。議題:第3集発行について。日時:5月26日。場所:中国新聞社ビル。 | 原爆被災資料広島研究会 | 葉書 |
| 197212 | <原爆被災資料総目録第3集出版記念合評会ごあんない>日時:12月16日。場所:中国新聞社ビル。 | 原爆被災資料広島研究会 | 葉書 |
| 1973 | <原災研例会ごあんない>議題:①総目録第4集(社会科学の部)の企画について②第2集の配布状況について③会報発行について | 葉書 | |
| 19760812 | 「芸備地方史研究辞典」(仮題)原稿執筆催促 | 芸備地方史研究会(広島県立図書館郷土資料室内) | 葉書 |
| 19761031 | 石田明『被爆教師』出版記念会(11月13日、会場:広島国際ホテル) | 呼びかけ人(今堀誠二・大西典茂・坂田修一・佐藤正夫・庄野直美・宅和純・山田浩) | 葉書 |
| 1977 | 広島憩いの家(事務局長:田辺耕一郎)(主催)日本ペンクラブ・広島市(後援)「文芸家・画家・名士色紙書画展」(7月21~27日)会場:天満屋7階画廊 | 広島天満屋美術部 | 葉書 |
| 19771026 | 広島県社会運動史研究会創立総会・講演会(11月8日、会場:労働会館3階会議室)<講演:鈴木裕子「戦後女性の労働運動史」、山木茂「中国視察報告」> | 山木茂(広島県社会運動史研究協議会) | 葉書 |
| 1978 | 広島県社会運動史研究会第5回例会「水原史雄(中国新聞文化部)報告「安芸門徒の歴史と風土」」(10月27日、広島市立中央図書館会議室) | 広島県社会運動史研究会(山木方) | 葉書 |
| 19790309 | 旧天神町有縁者親睦会(4月1日、場所:浄円寺) | 世話人 | 葉書 |
| 197906 | 『白いチョゴリの被爆者』出版記念会(7月14日、会場:広島国際ホテル) | 広島県朝鮮人被爆体験記協力委員会 | 葉書 |
| 19790717 | 『ヒロシマを語る十冊の本』(ヒロシマを知らせる委員会編)発行案内 | 労働教育センター | 葉書 |
| 19790718 | 広島県社会運動史研究会第5回例会。報告:丸屋博(広島共立病院長)書評『白いチョゴリの被爆者(労働旬報社)』(7月25日、場所:広島平和文化センター会議室) | 広島県社会運動史研究会(山木方) | 葉書 |
| 19790918 | アリス・ハーズ夫人平和賞受賞記念会(9月26日、会場:教育会館) | 広島県原爆被害者問題研究会 | 葉書 |
| 19800124 | 広島県社会運動史研究会第12回例会。報告:宇吹暁(広大原医研)「広島と平和」(1月30日、場所:広島平和文化センター会議室) | 広島県社会運動史研究会(山木方) | 葉書 |
| 19800221 | 広島県社会運動史研究会第13回例会。報告:藤原浩修(県史編さん室)「広島県労働文化協会について」(2月27日、場所:広島平和文化センター会議室) | 広島県社会運動史研究会(山木方) | 葉書 |
| 19800715 | 広島県社会運動史研究会第17回例会。報告:藤原浩修(県史編さん室)「戦後広島県内の青年運動」(7月23日、場所:広島平和文化センター) | 広島県社会運動史研究会(山木方) | 葉書 |
| 810703 | 平和と学問を守る大学人の会・原爆問題広島総合研究会(主催)シンポジウム「非核三原則をめぐって」<話題提起:大西典茂、桜井醇児、永井秀明>(7月11日、会場:広島市平和記念館) | 原爆問題広島総合研究会 | 葉書 |
| 20030806 | 第10回中島地区ゆかりの人交流会(8月6日、場所:レストハウス3階) | ||
| 20120624 | 「広島ジャーナリスト」2周年「談論風発の夕べ」(7月13日、JCJ広島支部事務所) | 日本ジャーナリスト会議広島支部 | 葉書 |
| 201308 | 「 『被爆者山岡ミチコさん 被爆証言ありがとう』―4年間の記録」写真展への観覧お礼 | 関邦久(JRP広島支部) | 葉書 |
新藤兼人
| しんどう・かねと | 19120422生20120529没 | 享年100 |
| 映画監督。『広島県現代文学事典』 | ||
***
平山郁夫
| ひらやま・いくお | 19300605生20091202没 | 享年79 |
資料(新聞報道)
| 掲載紙 | 掲載日 | 見出し | 備考 | |
| 日経 | 19950731 | 今週の人 広島平和記念日(6日)平山郁夫さん(65) 東京芸術大学学長 「被爆国・日本、核廃絶の先頭に | ||
| 中国 | 19991122 | 平山氏をアカデミー会員に 仏学士院【パリ20日共同】 | ||
| 中国 | 20001102 | 国民文化祭ひろしま2000 平山郁夫氏(国民文化祭実行委員会会長(日本画家)) 39市町村の特性 存分に味わって | ||
| 出演者メッセージ | ||||
| 大林宣彦 | ||||
| 森下洋子 | ||||
| 島原帆山 | ||||
| アグネス・チャン | ||||
| 栄久庵憲司 | ||||
| 西田ひかる | ||||
| 原田真二 | ||||
| 内館牧子 | ||||
| 柳谷福治 | ||||
原田東岷
| はらだ・とうみん | 1912生 19990625没 | 享年87 |
| 外科医。「原爆乙女」の渡米治療に尽力。ワールド・フレンドシップ・センター初代理事長。広島市名誉市民。 | ||
| リンク=資料年表:原田東岷 | ||
| 出典:『ながれ』<pp.605-606>(村上哲夫、村上哲夫後援会) | ||
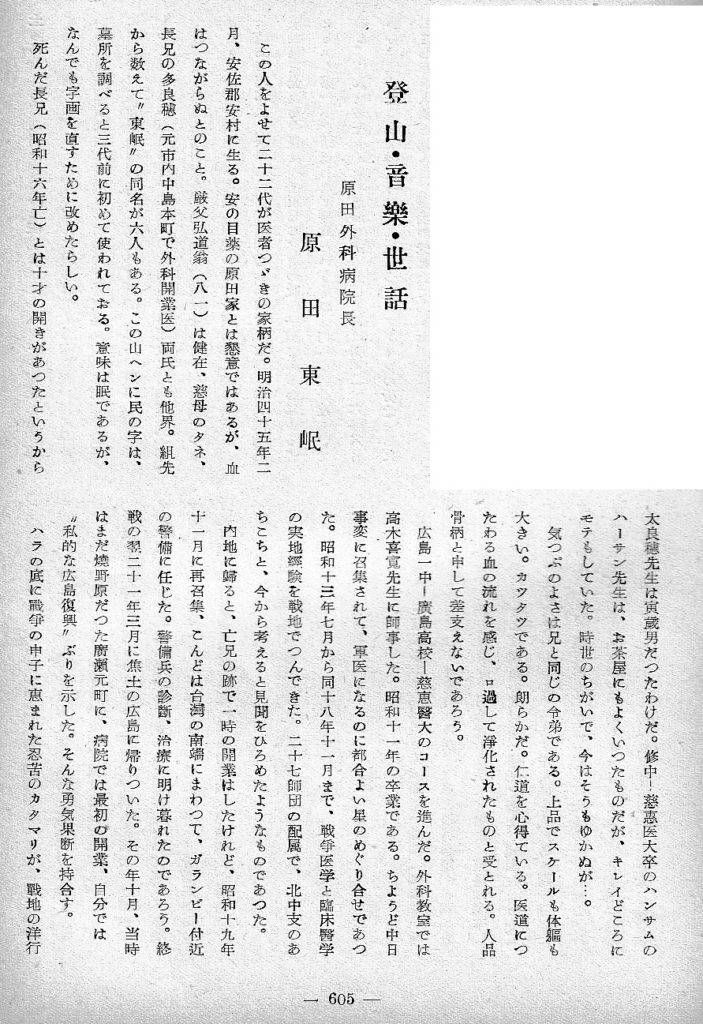 |
||
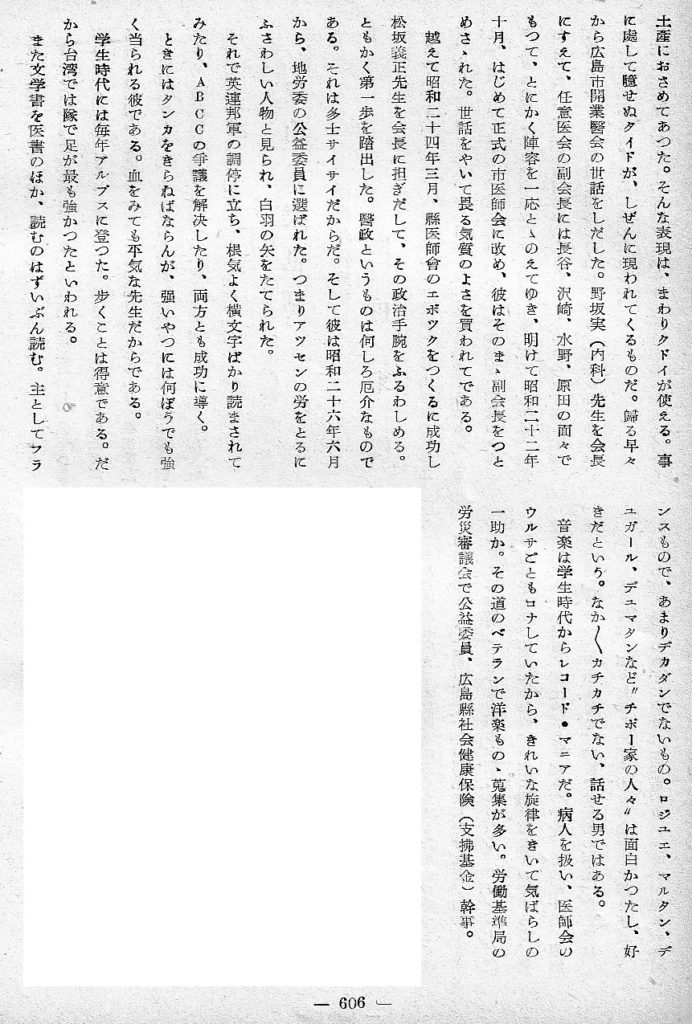 |
||
著書
| 書名 | 発行所 | 発行年月日 |
| ヒロシマの外科医の回想-ヒロシマからベトナムへ | 未来社 | 1977041503 |
| ヒロシマ歴程-外科医の回想 | 未来社 | 1982020101 |
| 平和の夢を追いつづけて | 影書房 | 1984081501 |
| ヒロシマのばら | 未来社 | 1989081505 |
| ひろしまからの発信-明止め治・大正・昭和・平成 | 1993111501 | |
| 平和の瞬間-二人のひろしまびと | 勁草書房 | 1994052001 |
| 命見つめて60年 | 溪水社 | 1997022001 |
止め