終戦15周年国民行事 平和祈念慰霊国民大祭
8月15日 午前10時 広島市公会堂
「祈りの像」除幕式 午后5時広島市平和公園内 慰霊碑前
主催・平和祈念慰霊国民大祭実行委員会
後援・広島県・広島市・中国新聞社・広島中央放送局・ラジオ中国
終戦15周年国民行事 平和祈念慰霊国民大祭
8月15日 午前10時 広島市公会堂
「祈りの像」除幕式 午后5時広島市平和公園内 慰霊碑前
主催・平和祈念慰霊国民大祭実行委員会
後援・広島県・広島市・中国新聞社・広島中央放送局・ラジオ中国
フォーラム・被爆者援護法―その1―
テーマ:被爆者援護法案の内容と問題点
主旨:
日時:1989年12月6日(土)午後1時30分~5時
場所:広島県民文化センター
参加費:500円
内容:
主催:原爆二法研究会(代表者 広島大学教授 田村和之、弁護士 島方時夫)
参議院社会労働委員の現地調査
1.視察委員:参議院議員 谷口弥三郎、同 山下義信
2.視察日程概況
| 1月 | 時刻 | 概況 |
| 6日 | 14:20 | 広島県庁を訪問し、地自宅において副知事、民生部長、衛生部長、関係各課長から原爆傷害者対策の概況説明を聴取した後意見を交換し、又県側の陳情を聴いた。 |
| 15:15 | 県知事応接室 | |
| 15:30 | 市役所 | |
| 16 | 市役所会議室 | |
| 7日 | 10 | 市役所 |
| 11 | ABCC(原爆影響研究所)ロバート・エッチ・ホームズ所長 | |
| 13 | 日赤広島病院 | |
| 14 | ||
3.調査項目
<以下未入力>
広島大学平和科学研究―センター・原爆放射能医学研究所・広島大学文書館(共催)「第16回広島国際シンポジウム 広島の黒い雨と関連する課題」。開催日:20110112
情報元:広島大学平和科学研究センター”NEWSLETTER”2011年
被爆者問題シンポジウム―被爆者調査をめぐって
開催日:1988年11月28日
場所:日本都市センター会議室
主催:日本原水爆被害者団体協議会
『報告書 被爆者問題シンポジウム―被爆者調査をめぐって』(日本原水爆被害者団体協議会発行)
シンポジウム:原爆被害と援護問題
日時:1983年8月7日
場所:広島市社会福祉センター
主催:「原爆被害と援護問題」シンポジウム世話人会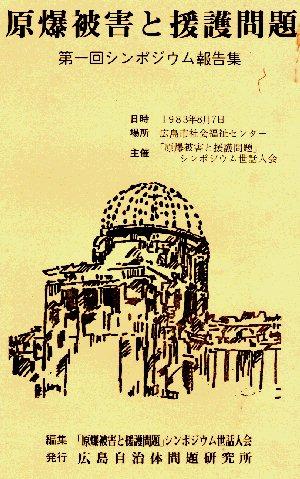
| 田村和之 | 開会のあいさつ |
| 小川政亮 | 被爆者援護の法理 |
| 湯崎稔 | 原爆被害者援護問題への課題 ー「基本懇」答申の問題をめぐって一 |
| 河合幸尾 | 被爆者援護と社会保障 |
| 若林節美 | 被爆者行政の現状と限界 |
公開シンポジウム「核開発の国際史―各時代の幕開けにおける科学者の社会的責任―」(日時:2003年8月10日、 会場:広島平和記念資料館メモリアルホール)
国際シンポジウム「20世紀における戦争・冷戦と科学・技術―国際共同研究の展望―」(日時:2005年10月2日、会場:広島市まちづくり市民交流プラザ内マルチメディア・スタジオ)
記録
『”戦争と科学”の諸相 原爆と科学者をめぐる2つのシンポジウムの記録』(広島大学総合科学部…編、市川浩・山崎正勝責任編集、丸善株式会社)
青年平和文化講座(創価学会) 1973年~
http://www.pv-hiroshima-soka.jp/activity/lecture/backnumber/
| 年月 | 講師 | 肩書(当時) | テーマ |
| 197308 | 原田東岷 | 外科医 | ヒロシマの外科医として |
| 197404 | 伊藤満 | 創価大学教授 | 人権と平和 |
| 197608 | 熊田重克 | 中国新聞論説副主幹 | 現代における核の状況 |
| 197608 | 丸山益輝 | 広島大学教授 | 広島の青年の役割 |
| 198003 | 今堀誠二 | 広島女子大学学長 | 私にとってのヒロシマ |
| 198004 | 畑博行 | 広島大学教授 | 日本と平和主義 |
| 198007 | 高橋昭博 | 原爆資料館館長 | 私の被爆体験と広島の心 |
| 198203 | 熊田重克 | 中国新聞論説主幹 | 広島と沖縄を結ぶ想像力 |
| 198302 | 豊永恵三郎 | 広島電機大学付属高校教諭 | 朝鮮・韓国人被爆者と私達 |
| 198308 | 深川宗俊 | 歌人 | 朝鮮・韓国の被爆者 |
| 198310 | 伏見康治 | 元日本学術会議会長 | 地平から平和の巨塔を |
| 198404 | 日隈健壬 | 広島修道大学教授 | 21世紀の広島が見える |
| 198408 | 北西允 | 広島大学教授 | 反核・平和運動の状況と展望 |
| 198503 | 磯野恭子 | 山口放送テレビ制作部次長 | 生命(いのち)の鼓動を伝えて |
| 198504 | 山田浩 | 広島大学教授 | これからの平和問題と私達 |
| 198603 | 片岡徳雄 | 広島大学教授 | いま、教育の原点を考える |
| 198706 | 川本義隆 | 原爆資料館館長 | 世界のヒロシマ 使命と責任 |
| 198709 | 大野允子 | 児童文学作家 | あなたへのメッセージ |
| 198711 | 秋葉忠利 | 広島修道大学客員教授 | ヒロシマの心と広島に住む若者の役割 |
| 198802 | 小倉桂子 | HIP代表 | 一人の力が平和の万波に |
| 198805 | 二宮皓 | 広島大学助教授 | 世界のなかのヒロシマ |
| 198809 | 目瀬守男 | 岡山大学教授 | 地域活性化と青年の役割 |
原爆被害者相談員の会 1981年6月13日発足
若林節美「原爆被害者相談員の発足と1年間のあゆみ」
(「ヒバクシャ-ともに生きる1号」所収)より
一九八○年十二月十一日、原爆による苦しみをなめ尽くしてきた被爆者は、原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見書(以下、意見書)を期待と不安の中で、じっと待っていた。
それは、被爆者のみならず、被爆者援護や核廃絶を願う人々にとって、被爆者援護法が制定されるか否かは、日本の将来、ひいては人類の未来が問われるという重大な関心事であった。
しかし、報告された意見書は、国の戦争責任を回避し、原爆の被害を矮小化し、そしてあいまいな国家補償論で、三十五年間にわたる被爆者の苦渋に満ちた歴史に意味を与えず、逆に、被爆者に衝撃を与え、生きる意欲を奪ってしまうものであった。
年の瀬も迫る中、日常的に被爆者に接するソーシャル・ワーカー(以下、ワーカー)は、被爆者の悲しみ、怒りを見すごすことはできず、二十人の被爆者の怒りの声を、厚生大臣宛に直訴状として届けた。
震える手で直訴状をつづった老被爆者は、「夫と娘の死にようはひどいものでした。苦しんで、苦しんで……。生きる支えだった息子は、九年間生きましたが、白血病で狂うようにして死にました。たった一人残された私は、あとどれだけ生きられるかわかりません。この死を無駄にしないで下さい。」と訴えた。しかし、この被爆者は長年願い続けてきた援護法の日の目を見ないまま、意見書の衝撃と寒さのため、一ケ月後に他界してしまった。
こうした二十名の被爆者の怒りと抗議の声は政治の前にはむなしく、私たちの小さな灯は、意見書を乗り越える取組みへと燃えていった。
一九八一年六月一三日、専門ボランティアによる原爆被害者相談が広島市内でスタートした。
これは、不当な意見書を乗り越えるために約半年をかけて産み出された、私たちの唯一の方法であり、運動であった。
今日、被爆者の高令化にともない、被爆者の問題は、複雑かつ深刻化し、とりわけ、被爆者援護の遅れは、被爆者のくらしや、こころの再建を非常に困難にしてきた。
この被爆者の問題に対し、行政や、各関係団体、各機関で相談事業が行なわれてきたが、今日の被爆者の切実な要請に応えるためには、一層、相談事業を強化しなければならず、しかも、専門的知識と経験を生かした総合的、かつ継続的な相談事業が求められていた。
それは、谷間で苦しむ被爆者のために、広く相談窓口を設け、被爆者の直接相談に応じながら、被爆者がかかえる現行二法の問題点、及ぴ、その被害の実態を科学的に究明し、しかも被爆者が被爆者として主体的に生きるための条件を整えていくという内容であった。
しかし、この相談事業の中心的役割を担わなければならないワーカーにとって、これほど重要な課題を目指すには、余りにも荷が重すぎ、不安は隠し切れなかった。
使命感と不安の中で、ワーカー、弁護士、研究者、教師、団体職員、市民等によって原爆被害者相談員の会が発足し、被爆者相談が取り組まれていった。こうして、過去五年にわたる原爆被害者問題研究会活動、NG0国際シンポジウムでの生活史調査、そして「三十五年目の被爆者」の出版等、ねばり強い活動経験が、さまざまな不安を一つ一つとり除き、次のような多くの成果と教訓を残した。
参考
| 年月日 | 事項 |
| 197511 | 広島原爆被爆者問題ケースワーカー研究会 |
| 198208 | 原爆被害者証言のつどい |
| 198212 | ヒバクシャ-ともに生きる1号 |
| 1981~ | 年表:原爆被害者相談員の会 |
放射線被曝者医療国際協力推進協議会(HICARE) 平成3(1991)年4月に発足
http://www.hicare.jp/about/
| 被曝者医療の国際協力10年の軌跡 | 放医協の歩み(平成2年~平成13年) | 2001/03/01 |
| 被曝者医療の国際協力25年の軌跡 HICARE25周年記念誌 | 活動年表 | 2017/03/01 |