『世界平和への提言-ユネスコ語録』(民間ユネスコ活動推進連絡協議会編、日本ユネスコ協会連盟、19720601)
内容
| 頁 |
|
|
|
民間ユネスコ運動25周年記念出版 |
| 007 |
数納清(社団法人日本ユネスコ協会連盟会長) |
はじめに |
| 009 |
ユネスコ設立のためのロンドン会議 |
|
各国代表の演説 |
|
| 010 |
|
ロンドン会議の背景 |
| 013 |
C・Rアトリー(会議議長、イギリス首相) |
歓迎の辞 |
| 017 |
エレン・ウィルキンソン(イギリス文相) |
開会のあいさつ |
| 022 |
レオン・ブルム(共同議長、フランス主席代表) |
あいさつ |
| 028 |
A・ミヒェルセン ほか |
演説抜すい |
|
A・ミヒェルセン、ファタン・アミル・パシャ、ルネ・カッサン、ラジクマリ・アムリト・カウル・トレス・ボデー、ヴァン・デル・レーウ、A・E・キャンプベル、ニルス・ヒエルムトヴェイト、マキシモ・M・カラウ、クゼラフ・ウィセク、バーナード・ドルセウィエスキー、サン・アリ・ユーセル、アーチボルド・マックリーシュ、ルジュポ・レオンティク |
| 035 |
ウイリアム・ベントン(国務次官補) |
国務長官へ宛てた伝達書 |
| 037 |
アーチボルト・マックリーシュ |
アメリカ代表団主席より国務長官へ宛てた報告書 |
| 047 |
ジュリアン・ハックスレー |
ユネスコの目的と哲学 |
| 075 |
ジュリアン・ハックスレー |
世界各国民の自己探求 |
| 085 |
ハイメ・トレス・ボデー |
戦争との戦い |
| 097 |
ハイメ・トレス・ボデー |
ユネスコ、軍服をつけぬ人々の要塞 |
| 105 |
ジャン=ポール・サルトル |
作家の責任 |
| 131 |
八人の科学者による共同声明 |
| 139 |
平和問題に関する日本の科学者の声明 |
| 147 |
ゴールドン・W・オルポルト |
期待の役割 |
| 187 |
箕輪三郎 |
ユネスコと日本 |
| 204 |
鮎沢 巌 |
歴史の現段階とユネスコの使命 |
| 218 |
前田多門 |
日本のユネスコ加盟に際して |
| 222 |
仁科芳雄 |
平和問題と科学者の態度 |
| 227 |
安倍能成 |
平和宣言 |
| 235 |
谷川徹三 |
ユネスコと世界政府運動 |
| 240 |
森戸辰男 |
独立と平和主義 |
| 245 |
大原総一郎 |
ユネスコ運動にのぞむもの |
| 249 |
喜多村 浩 |
平和をになう経済 |
| 255 |
横田喜三郎 |
ユネスコ活動のあり方―重点を大衆の国際理解に |
| 259 |
関口 泰 |
戦力不保持に誇を持って |
| 264 |
勝本清一郎 |
ユネスコ運動の民主的公共性 |
| 271 |
抄録 |
|
| 273 |
アーノルド・トインビー |
|
| 273 |
アルベエル・カミユ |
|
|
<以下日本人のみ> |
|
| 285 |
安倍能成 |
|
|
伊原宇三郎 |
|
|
上田康一 |
|
|
尾高朝雄 |
|
|
勝沼精蔵 |
|
|
勝本清一郎 |
|
|
桑原武夫 |
|
|
矢内原伊作 |
|
|
|
ユネスコ憲章(前文・第一条) |
|
|
筆者紹介 |
|
|
原典紹介 |
|
|
編集後記 |
|
|
|
『ウ・タント 世界平和のために』(国際連合広報局編、国際市場開発、19720410)
内容
|
|
|
|
日本語版への序文(ウ・タント) |
|
|
本書の推薦のことば(国際連合広報センター所長代理) |
|
|
編集者のことば |
|
| Ⅰ |
国際連合の目的と原則 |
|
|
国際連合の必要性/国際連合の任務/事務総長の役割/総会と安全保障理事会の役割/平和と進歩への障害/暴力/協力の利益/諸国の行動の調和/忍耐、多様性、相互理解/国家主権/国家主義と国際主義/新興独立国の役割/小国の役割/一国一票の原則/普遍性/極小国家/平和について/国際法の役割/国際連合の強化/国際連合のコスト/新しい地球への脅威、新たな出現/国際連合の評価 |
|
|
|
|
| Ⅱ |
平和と安全の維持 |
|
|
紛争の平和的解決/地域的取極/軍縮と核兵器/核保有国会議の必要/宇宙空間の平和利用/原子力の平和利用/平和維持の必要/平和維持活動/中東/コンゴ/キプロス/インドーパキスタン/国際平和部隊/ヨーロッパの安全保障に関する会議/世界平和の安全と多様性/ |
|
|
|
|
| Ⅲ |
ベトナム戦争 |
|
|
解決を求めて/基本的問題/国際連合とベトナム/戦争終結への三段階/ドミノ理論/直接会談/国際的評価/政治的ディスエスカレーション/戦争のエスカレーション/インド-シナ |
|
|
|
|
| Ⅳ |
チェコスロバキア |
|
|
|
|
| Ⅴ |
ナイジェリア |
|
|
|
|
| Ⅵ |
経済社会開発 |
|
|
国際連合開発の10年/地球戦略/貿易と開発/格差の拡大/国際援助の必要性/資本主義と共産主義/技術革新/科学と技術の役割/開発と軍縮/変動世界における教育/人間環境/加盟国の選ぶ道/新しい問題、新たな挑戦 |
|
|
|
|
| Ⅶ |
独立の達成と人権 |
|
|
人権/人種差別/アパルトヘイト/植民地解放/青年と人権 |
|
|
|
|
| Ⅷ |
国際連合と世論 |
|
|
世論の役割/マス・メディア |
|
|
|
|
|
付録 |
|
| Ⅰ |
国際連合について(国際連合広報センター) |
|
| Ⅱ |
抜粋・参考文献 |
|
|
|
|
|
訳者あとがき(井上昭正) |
|
|
|
|
核兵器禁止条約発効-新聞報道(20210122)
| 紙名 |
頁 |
見出し |
| 中国新聞 |
01 |
核兵器禁止条約が発効 被爆地 廃絶へ前進願う |
|
|
|
| 朝日新聞 |
01 |
天声人語 |
|
|
|
| 毎日新聞 |
02 |
核禁条約順次発効 批准50カ国・地域で |
|
|
|
| 読売新聞 |
02 |
核禁条約22日発効 50か国・地域 米中露など不参加 日本不参加方針変えず |
|
|
|
| 産経新聞 |
05 |
核兵器禁止条約 きょう発効 保有国含めた行動 課題 |
|
|
|
| しんぶん赤旗 |
01 |
核禁条約きょう発効 世界各地で行動を計画 |
|
|
|
| 日本経済新聞 |
|
なし |
核兵器禁止条約発効-Yahooニュース 2021年1月22日、8:22:30
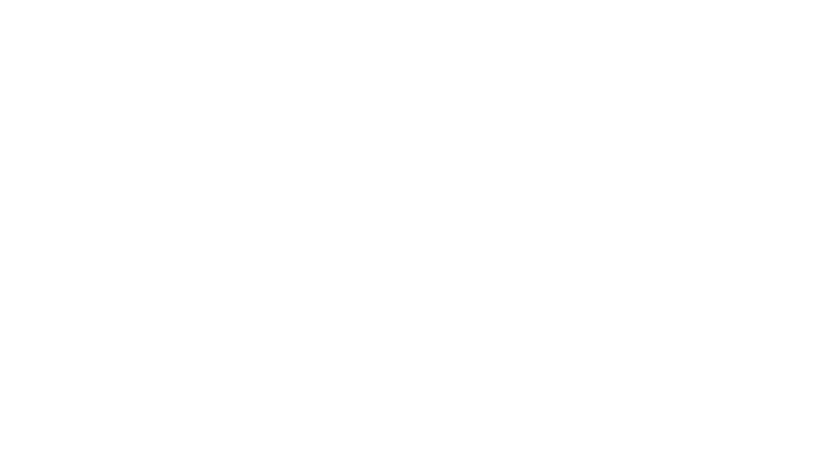 |
| 時事通信社会 |
1/22(金)7:14 |
署名1370万筆、核禁止条約に力 被爆3世ら、新たな運動も 発効未届け活動終了 |
| 朝日新聞デジタル国際総合 |
1/22(金)04:41 |
核兵器禁止条約が発効 51の批准国・地域で初の違法化 |
| 毎日新聞国際総合 |
1/22(金)0:16 |
核兵器禁止条約、批准国で順次発効 締約会議はオーストリア開催へ 日本惨禍は? |
| 中国新聞デジタル社会 |
1/21(木)23:02 |
核兵器禁止条約が発効 「核の傘」依存の日本、不参加のまま |
『核兵器の包括的研究 国連事務総長報告』(服部学監訳 、出版社、19820305 )
| 章 |
|
|
|
日本語版刊行にあたって |
|
|
国連事務総長による前書き |
|
|
報告提出にあたっての手紙 |
|
| 1 |
はじめに |
|
| 2 |
現在の核兵器の実態 |
|
|
A 核兵器 21
B 長距離運搬システム 22
C 情報・指揮・管制・通信 27
D 超大国の主要な戦略兵器 28
E 地域核戦力 35
F 他の国の戦略兵器 36
G 戦術核戦力 37
H 核兵器取得の技術と費用 |
|
| 3 |
核兵器の技術的発展の傾向 |
|
|
A 過去ならびに現在の発展の主要な形態 43
B 弾頭の設計と特性 46
C 核兵器実験 49
D 兵器体系についての一般的解説 52
E 戦略的運搬システム 54
F 戦略的対抗手段および対抗システム 59
G 探知・識別システム 62
H 地域的核戦力 |
|
| 4 |
核兵器使用の効果 |
|
|
A 一発の核爆発による効果 68
B 限定核攻撃の効果 79
C 戦術核兵器の広範な使用による影響 84
D 全面核戦争、核の応酬の影響 89
E 全地球的側面 96
F 核実験の影響 103
G 民間防衛 |
|
| 5 |
抑止論および核兵器にかんするその他の理論 |
|
|
A 戦略理論と核兵器 112
B 核兵器と抑止 113
C 戦略理論と技術の発展 118
D 核兵器保有国の核戦略理論 119
E 戦略理論と安全保障 129 |
|
| 6 |
核兵器体系のひきつづく量的増加と質的改良が安全保障に対してもつ意味 132 |
|
| 7 |
核軍縮にかんする諸条約、諸協定、諸交渉の意味 157 |
|
| 8 |
むすび 「人間社会にたいする絶え間ない脅威」 172 |
|
| 付録Ⅰ |
核兵器による効果の技術的記述 |
|
|
A 爆風とその効果 183
B 熱線とその効果 187
C 火災 188
D 電磁パルスとその効果 190
E 初期核放射線 193
F 残留放射線(フォールアウト)196
G 放射線傷害 198
H 複合傷害および一般的相乗作用 |
|
| 付録Ⅱ |
1980年度軍縮交渉委員会に提出された核保有国による「安全保障の保証」 |
|
|
あとがきにかえて |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国連歴代事務総長
| 名前 |
出身国 |
在職期間 |
|
|
|
| アントニオ・グテーレス |
ポルトガル |
2017年1月1日~ |
| 潘基文 |
韓国 |
2007年1月~2016年12月 |
| コフィー・A・アナン |
ガーナ |
1997年1月~2006年12月 |
| ?ブトロス・ブトロス=ガーリ |
エジプト |
1992年1月~1996年12月 |
| ハビエル・ペレス・デクエヤル |
ペルー |
1982年1月~1991年12月 |
| クルト・ワルトハイム |
オーストリア |
1972年1月~1981年12月 |
| ウ・タント |
ビルマ(現ミャンマー) |
|
|
1961年11月に事務総長代行に任命され、1962年11月に正式に事務総長に任命。1971年12月まで在職 |
| ダグ・ハマーショルド |
スウェーデン |
|
|
1953年4月から1961年9月にアフリカでの航空機墜落事故で殉職するまで在職 |
| トリグブ・リー |
ノルウェー |
1946年2月~1952年11月 |
出典:https://www.unic.or.jp/info/un/un_organization/secretariat/secretary-general/list_sg/
核兵器禁止条約50カ国・地域批准報道(日本)
日本の新聞(10月26日1面掲載)
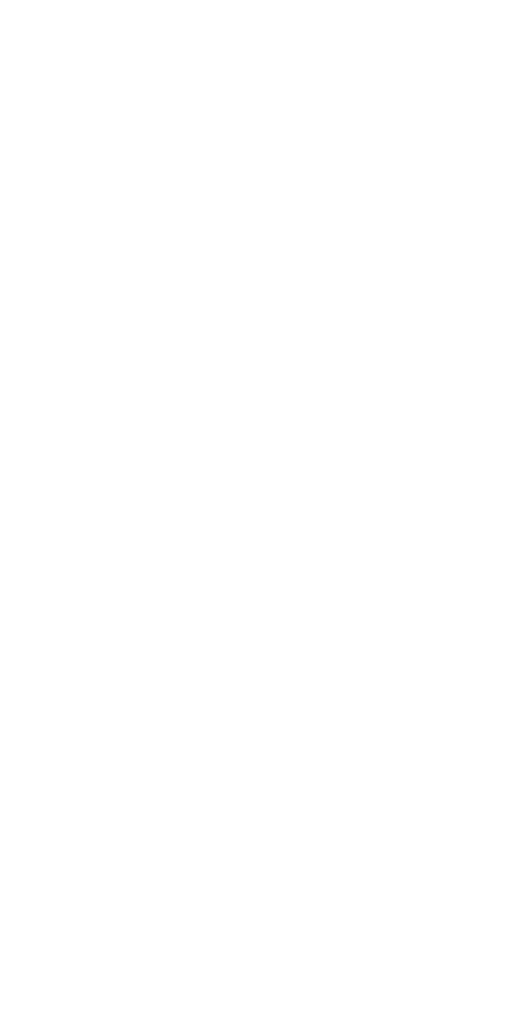 |
| 日本の新聞報道(1面掲載20201026) |
| 中国新聞 |
|
| 朝日新聞 |
|
| 毎日新聞 |
|
| 読売新聞 |
|
| 日本経済新聞 |
|
|
国連軍縮特別総会(1978)
(日本平和学会『平和研究 第4号』19790620)
| 加藤俊作 |
国連軍縮特別総会の経緯と展望 |
|
<資料>国連軍縮特別総会における最終文書(外務省情報文化局提供仮訳) |
| 蔵田雅彦 |
<資料>NGOの日における六つの平和研究所の演説全文 |
|
国際情報センター(米国) |
|
世界経済国際関係研究所(市冷えと連邦科学アカデミー) |
|
ウィーン国際平和研究所 |
|
国際平和研究学会(IPRA) |
|
スタンレー財団 |
|
ストックホルム国際平和研究所 |
| 佐藤栄一 |
<報告>国際平和探求へのたゆみなき実践―ストックホルム国際平和研究所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
『高校生平和大使にノーベル賞を 平和賞にノミネートされた理由』(「高校生平和大使にノーベル賞を」刊行委員会編、長崎新聞社、20180804)
目次
|
|
|
|
| 第1章 |
ノーベル賞候補ノミネートへの道 |
|
|
|
|
|
|
| 第2章 |
高校生平和大使への軌跡 |
|
|
|
|
|
|
| 第3章 |
未来へつなげていくために |
|
|
|
|
|
|
| 特別収録 |
高校生平和大使アンケートから |
|
|
|
|
|
|
| 資料 |
歴代の高校生平和大使一覧、署名数推移 |
|
|
|
|
|
|
|
あとがき |
|
|
『世界の平和・軍縮教育 1982年国際シンポジウム報告書』(WCOTP・日教組報告書編集委員会編、勁草書房、19830710)
目次
|
|
|
|
|
刊行のことば |
槙枝元文 |
|
|
世界の平和・軍縮教育 1982年国際シンポジウム |
|
| 序章 |
|
|
|
|
広島アピール 19821029 |
軍縮教育国際シンポジウム |
|
| 第1部 |
|
|
|
| 第1章 |
シンポジウムの意義と課題-全体会議挨拶・報告 |
|
|
沈黙を守らずに声をあげて語ろう |
ジェームス・キリーン |
|
|
被爆国の国際的責務を自覚して |
槇枝元文 |
|
|
国際教育分野におけるユネスコの活動 |
ヤハイル・カバチェンコ |
|
|
第2回国連軍縮特別総会後の国連と軍縮教育 |
ヤン・モーテンソン |
|
|
勝利は必ずや私たちのものに |
ヴィクター・シュー |
|
| 第2章 |
全大陸から |
|
|
|
戦争をさばく良心を |
アルフレッド・バッド |
|
|
平和を望むのなら平和を準備せよ |
ギー・ジョルジュ |
|
|
資源を飢えと無知の克服のために |
シー・アビブーラエ |
|
|
平和・軍縮のために勇気を |
サミュエル・ベロ |
|
|
子どもたちに何を語るべきか |
ウィラード・マックガイヤー |
|
|
核時代に人類の生存をかけて |
橋口和子 |
|
|
近・現代史教育を強化しよう |
ワー・スト |
|
|
真実の軍縮と世界平和のために(メッセージ) |
中国教育工会全国委員会 |
|
|
軍縮教育-ソ連の経験から- |
ユーリ・ニキホロフ |
|
| 第3章 |
国際組織から |
|
|
|
今こそ人権と平和の教育を |
ジャン・ドバール |
|
|
今日の世界における軍縮教育 |
アンドレ・ドルベー |
|
|
IFFTU第13回世界大会決議の意義 |
フレッド・ヴァン・ルーウェン |
|
|
平和・軍縮のための教育者の国際的協議を |
ダニエル・ルトロー |
|
| 第4章 |
二つの学会から |
|
|
|
平和・軍縮教育-3つの視点 |
大田堯 |
|
|
国家主義をのりこえて |
福島新吾 |
|
| 第5章 |
ヒロシマの心を世界に |
荒木武 |
|
|
世界の恒久平和実現を |
竹下虎之助 |
|
|
ヒロシマからの提言 |
栗野鳳 |
|
|
長崎の平和教育を省みて |
坂口便 |
|
|
人類が生きのびるために |
岸槌和夫 |
|
|
ヒロシマからの証言(メッセージ) |
石田明 |
|
|
世界の先生たちへ(メッセージ) |
広島女学院高校3年生 |
|
| 第6章 |
二つの提言-招待者発言- |
|
|
|
勇気と忍耐を-平和・軍縮をめざして- |
宇都宮徳馬 |
|
|
人類の平和と真の発展を求めて |
永井道雄 |
|
| 第2部 |
|
|
|
| 第1章 |
平和・軍縮教育をめぐって〈第1分科会〉 |
|
|
|
〔基調報告〕 |
|
|
|
この分科会の課題-ユネスコ80年「軍縮教育十原則」の追求を- |
アンドレ・ドルベー |
|
|
〔討論〕 |
|
|
|
平和・軍縮教育と教材選択の自由を |
ギー・ジョルジュ |
|
|
“国防論信仰”の克服を-憲法教育の意義- |
太田一男 |
|
|
軍縮をすべての子どもに |
テリー・ハーンドン |
|
|
貧困・人種差別をなくすとりくみを |
デビッド・トンキン |
|
|
原爆を原点に-日本の平和教育の展開と課題- |
梶村晃 |
|
|
父母とともに原爆の学習と継承を |
山川剛 |
|
|
教育学上の問題として-残酷さの教育、戦争史学習の意義- |
ロバート・バーカー |
|
|
子どもたちに平和な世界を-第3世界の直面する課題- |
ワジュデイ |
|
|
世論の喚起でカリキュラムに |
S・エスワラン |
|
|
子どもの心に偏見ではなく連帯を-超大国の支配の中で- |
シュー・チャラン |
|
|
〔分科会報告(草案)をうけて〕 |
|
|
|
軍縮教育の機は熟した-核凍結の市民の運動と学習を土台に- |
ウィラード・マッガイヤー |
|
|
重ねて残酷さを教えることについて |
ロバート・バーカー |
|
|
残酷さを教えねばならない-だが分析的考察へ向けて- |
デービッド・トンキン |
|
|
核戦争の危機の認識を-軍縮教育十原則を自覚的に- |
庄野直美 |
|
|
平和と民族の自決の教育を-日本人と連帯し、教訓に学ぶ- |
朴光沢 |
|
|
軍事基地の撤去の課題を-非核地帯設定とともに- |
大田昌季 |
|
| 第2章 |
平和・軍縮教育の教材開発をめぐって〈第2分科会〉 |
|
|
|
〔基調報告〕 |
|
|
|
日本の平和教育の具体的とりくみ 福島昭男 |
|
|
|
〔討論〕 |
|
|
|
教職員・学生の交流を深めよう |
ウォーターハウス・ワイワイ |
|
|
世界の三分の一の文盲がいる |
アバニ・ボラル |
|
|
どうして非暴力のエレメントを教えるか |
ジャック・スミス |
|
|
二度と戦争を繰返すな |
コンラッド・バクヤク |
|
|
たとえ命を賭しても平和を |
ホアン・アンブロシオ・サビオ |
|
|
軍備拡大の最大の被害者は途上国 |
トッサ・クペソー・カングニ |
|
|
軍隊のない国から訴える |
マルコ・アントニオ・バランテス・ヴェガ |
|
|
弾圧をはねのけ教師を再教育 |
マットス・トッタ・ザヒヤ |
|
|
考え方のプロセスに参加する教え方 |
ホアン・ルイ・フェンテス |
|
|
急がれる教材開発 |
サーロン・せつ子 |
|
|
先生が変わらなければ生徒を変えることはできない |
栗原貞子 |
|
|
教材の開発は教師・親の手で |
フレッド・ヴァン・ルーウェン |
|
|
広島の三つの顔を教材に |
空辰男 |
|
|
近・現代史の教育を強化すること |
プン・ティン・チー |
|
|
軍人にも一般教養を |
ギー・ジョルジュ |
|
|
安全保障は軍備撤廃によってのみ |
森滝市郎 |
|
|
あらゆる教材の活用と開発をすすめよう |
キャシー・ブロック |
|
| 第3章 |
平和・軍縮教育を自覚的に〈分科会報告と総括発言〉 |
|
|
|
〔第一分科会報告〕 |
|
|
|
平和・平和軍縮教育の原則をめぐって-教員団体の責務- |
ジョージ・リース |
|
|
〔第二分科会報告〕 |
|
|
|
平和・軍縮教育の教材・方法の創造的開発を |
マットス・トッタ・ザヒヤ |
|
|
〔総括発言〕 |
|
|
|
平和と人類の道を選ぶ意志を-教職員の責務- |
ノーマン・ゴーブル |
|
|
資料 |
|
|
|
日程および参加者名簿 |
|
|
|
あとがき |
|
|
|
|
|
|
ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。

