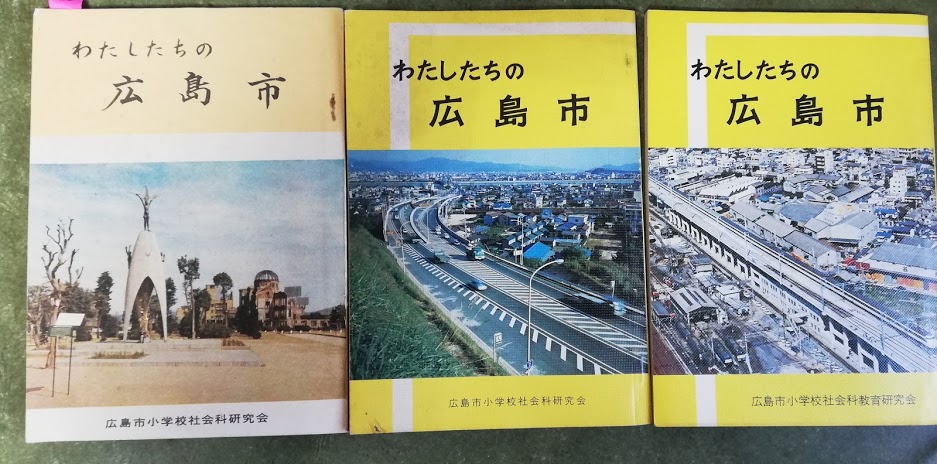『被爆(戦後)50周年 被爆(戦争)体験談児童生徒の平和作文集』(府中町・府中町教育委員会編 刊、19960101)
目次
| はじめに | 林原亘(府中町長) | |
| 被爆(戦争)体験談 | ||
| 八月六日(池本四郎) 私の見た光景(江種祐司) 被爆体験(岡村守三) 私史断片(梶川進) 敗戦直前の頃(片桐隆三) 私の青春は終始、戦争の地獄だった(栗栖徳政) 私の原爆体験記(滝山政輝) 原爆の追憶(多羅尾義男) 一生懸命働いた(中山アヤ子) 戦争と母(二井貴衣) 私の戦争体験(橋本正紀) 平和への願い(橋本ツネ子) 私の青春時代(溝本燁子) あの思いを胸に今…(山手博) 私の原爆記(山室安江) 府中小学校講堂での被爆者看護の日々(吉田美江子) |
||
| 平和作文(中学生の部) | ||
| 平和作文(小学生の部) | ||
| 資料 | ||
| 01 | 「日本非核宣言自治体協議会」結成の経過 | |
| 02 | 日本非核宣言自治体協議会会則 | |
| 03 | 年度別協議会会員自治体数及び非核宣言自治体数 | |
| 04 | 1995年都道府県市区町村別内訳 | |
| 05 | 内、1995年広島県市町村別内訳 | |
| 06 | 広島県内非核宣言自治体一覧表 | |
| 07 | 核兵器廃絶・平和宣言を呼びかける共同声明 | |
| 08 | 非核町宣言(府中町・府中町議会) | |
| 09 | 抗議文(府中町) | |
| 10 | 抗議決議(府中町議会) | |
| 11 | 府中町被爆者健康手帳保持者数 | |