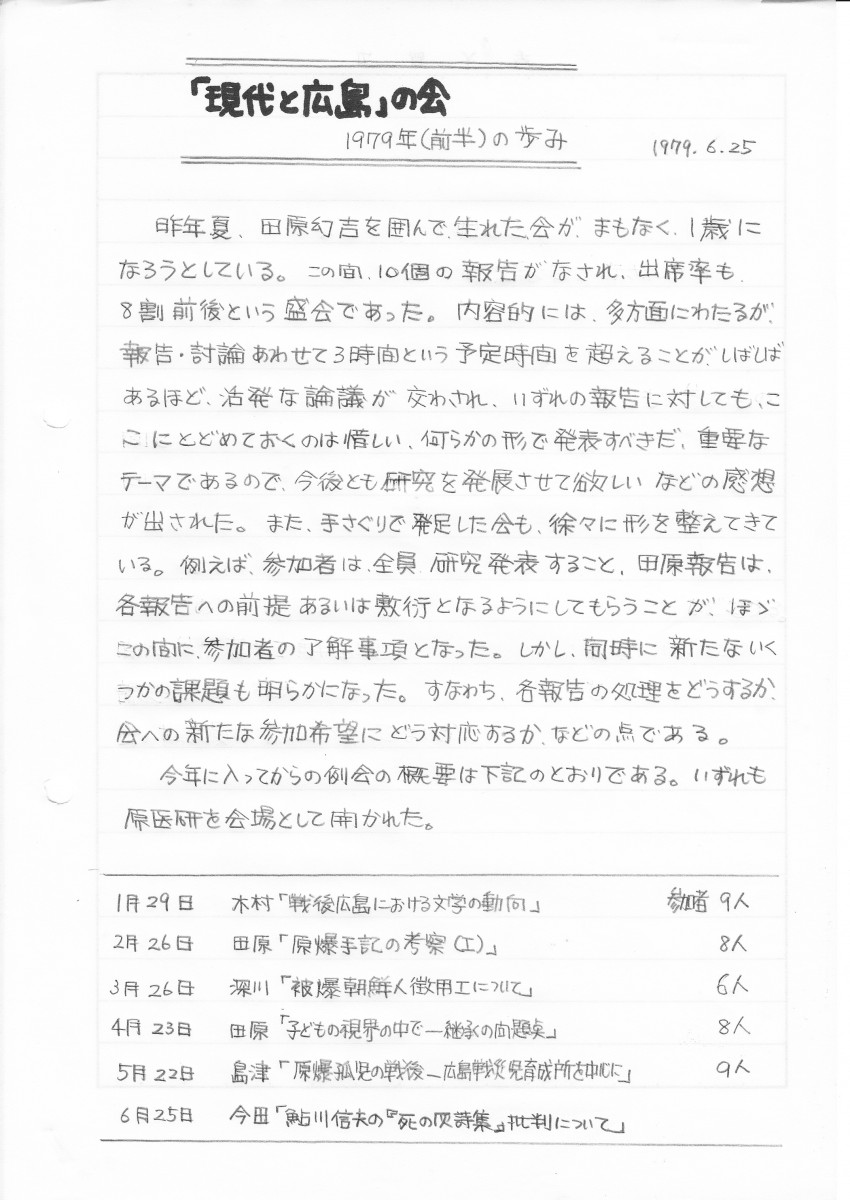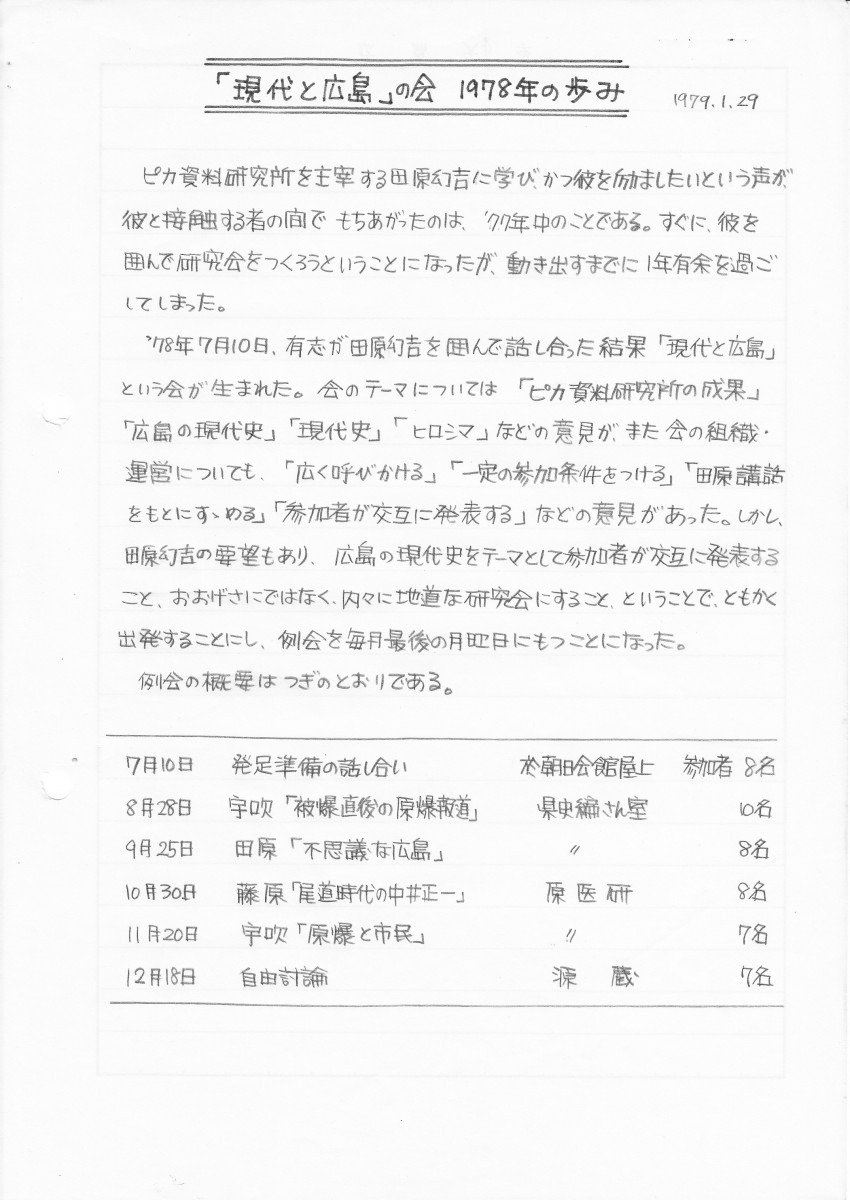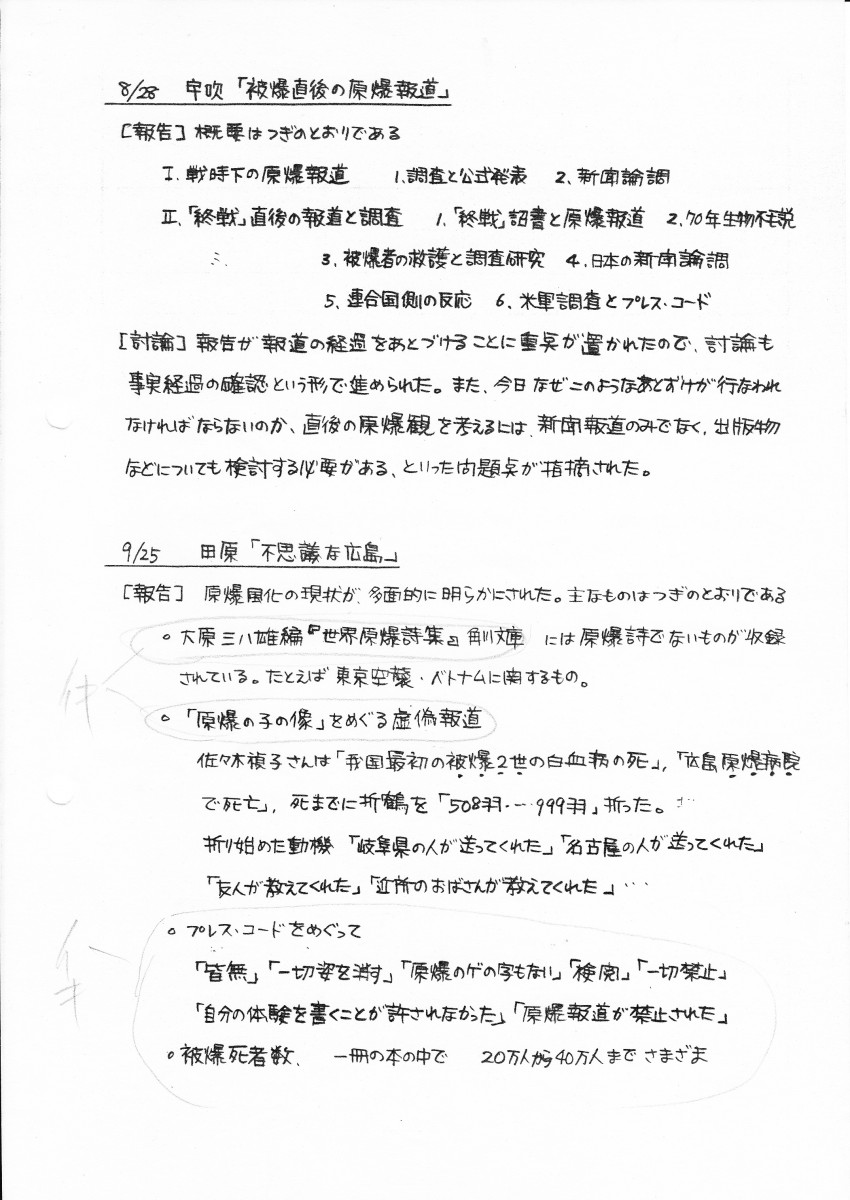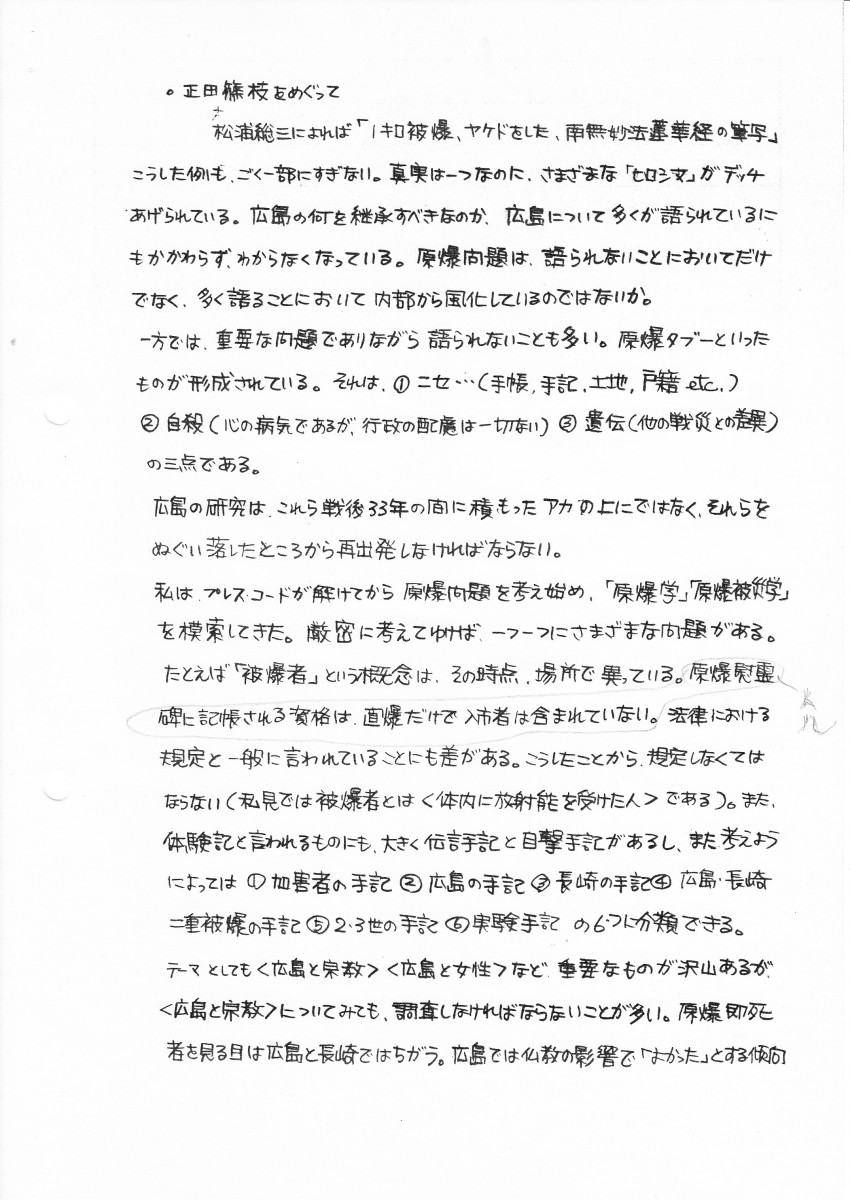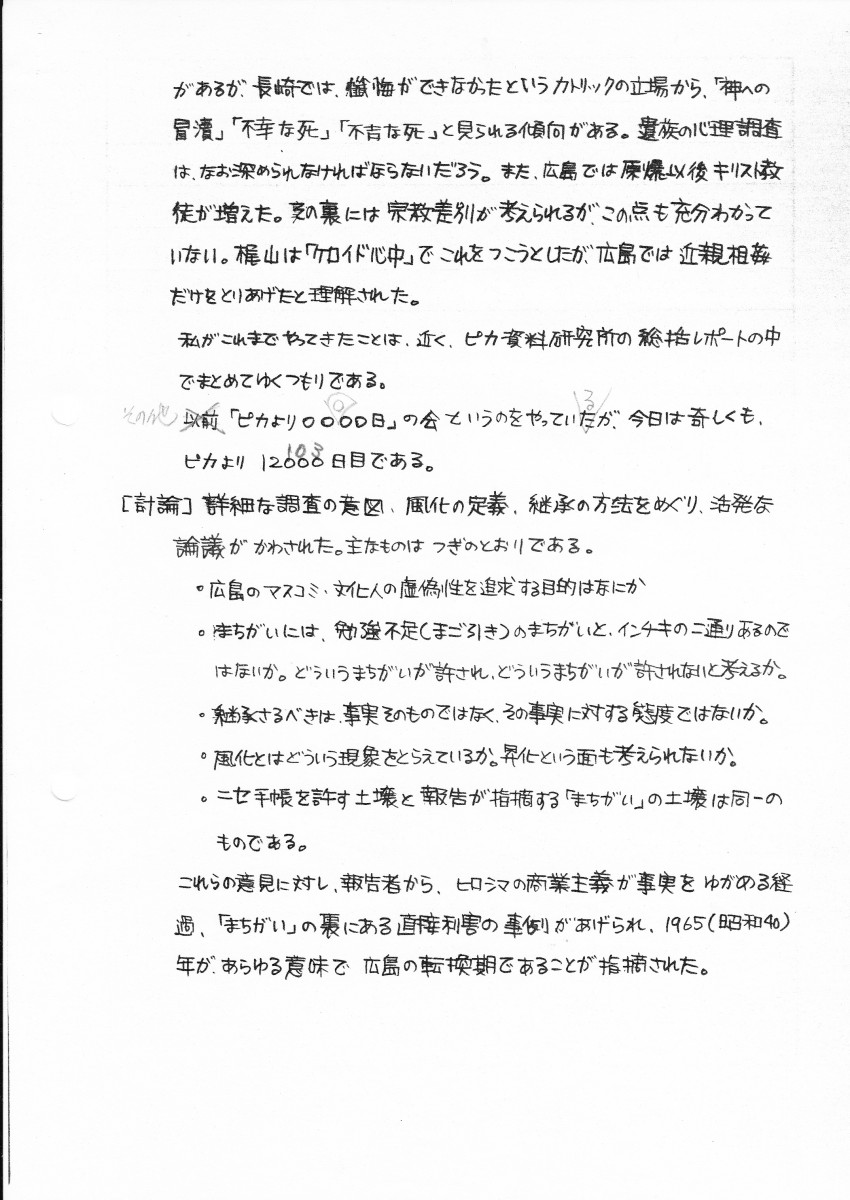『河図洛書-渓水社十周年記念』(木村逸司編、溪水社 <渓水社>19850430)目次(抄)
|
|
|
|
| Ⅰ-1 |
出合いの一冊 |
|
|
長岡弘芳 |
J・ハーシー『ヒロシマ』のこと |
| Ⅰ-2 |
幼い日に |
|
|
|
|
| Ⅰ-3 |
青春の道すがら |
|
|
天野卓郎 |
私の読書 |
|
|
佐藤進 |
万年文学青年の読書歴 |
|
|
平岡敬 |
カフカと『世紀群』 |
| Ⅰ-4 |
わたしの読書法 |
|
|
|
|
| Ⅰ-5 |
収書・探索 |
|
|
|
|
| Ⅰ-6 |
蔵書 |
|
|
宇吹暁 |
蔵書あれこれ |
|
|
|
|
| Ⅰ-7 |
思いつれづれ |
|
|
岩崎清一郎 |
ありあまる時間の中の怠惰 |
|
|
宇野正三 |
安養の浄土はこいしからずそうろう |
|
|
中敏みのり |
遠来の友との出会い |
| Ⅱ-8 |
本づくりあれこれ |
|
|
石踊一則 |
紙魚のひとりごと |
| Ⅱ-9 |
編集のことなど |
|
|
大牟田稔 |
見果てぬ夢 |
|
|
五藤俊弘 |
広島県詩集のこと |
| Ⅱ-10 |
本としてだす |
|
|
| Ⅱ-11 |
文化・地方・渓水社 |
|
|
板垣綬 |
「中央」と「地方」って何んだろう |
|
|
今堀誠二 |
世界にひろがり得てこそ |
|
|
米山穫 |
渓水社 |
|
|
|
|
| Ⅲ- |
|
渓水社の十年 |
|
火幻短歌会機関誌『火幻』(作業中)
| <所蔵>P=ピカ研、N=西岡、U=宇吹、G=原爆資料館 |
| 年月日 |
通巻 |
備考 |
所蔵 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
| 19590723 |
4 |
特集「八月六日」 |
P |
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
| 19610415 |
11 |
特選作品 松田弘江、橋本豊子、東美恵子 |
G |
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
| 19611221 |
14 |
特集・石井義人追悼 |
G |
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
| 19630920 |
21 |
5周年特集号 |
G |
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
| 19641221 |
26 |
批評特集 |
G |
| 19650325 |
27 |
春季号 |
NG |
|
|
豊田清史「評論 渡辺己の評価―戦争と短歌(完結)」 |
|
|
|
豊田清史「作品 ベトナムの戦火」 |
|
|
|
作品A******呉 西岡喜美子<27ページ> |
|
| 19650720 |
28 |
特集「戦後広島の文芸と短歌」 |
P |
| 19651001 |
29 |
火幻賞作品 横山初江ほか 1
火幻賞選考経過 松田弘江ほか 8 |
G |
|
30 |
|
|
| 19660318 |
31 |
<保田白汀追悼号> |
PNG |
|
|
豊田清史「批評精神をこめる―短歌と実作そのニ」 |
|
|
|
保田白汀氏追悼 作品・年譜・追悼記 |
|
| 19660801 |
32 |
特集「原水爆短歌この二十年」 |
PG |
| 19661006 |
33 |
虚無との対決 松永信一 5
「炎の歌集」を読んで 田淵実夫 8 |
G |
|
34 |
|
|
|
35 |
|
|
| 19670720 |
36 |
特集「広島とベトナム」 |
P |
| 19671018 |
37 |
創刊10周年記念号 |
PNG |
|
|
表紙絵 小林和作画伯 |
|
|
|
〈火幻の裸像〉〈essay〉〈広島県の文芸〉〈僚友誌の火幻評言〉 |
|
|
|
第五回火幻賞発表並びに作品 |
|
|
|
<同人の短歌・研究レポート> |
|
|
|
火幻各支部の現状 |
|
|
|
合同歌集”火幻の花” |
|
|
|
火幻と共に歩んで |
|
|
|
編集後記 |
|
|
38 |
|
|
| 19680320 |
39 |
1968 春号 |
N |
|
|
「広島抄」より 三田嘉一 |
|
| 19680723 |
40 |
特集「社会詠作品の検討」 |
P |
| 19681010 |
41 |
秋号 |
PG |
|
42 |
|
|
| 19690320 |
43 |
春号 表紙 広島市女原爆慰霊碑〈広島平和記念公園内〉
火幻20代8人選 山田美露鬼ほか 2
生と詩 仏崎紫水ほか 2
広島の七不思議〔一〕 豊田清史 8
〈特別作品〉 横山初江ほか 11
同人作品 松田弘江ほか 18
essay 藤井逸馬ほか 33
火幻集 沼田稔之ほか 39
歌会記 津村正名 50
編集記 仏崎紫水 65 |
G |
| 19690718 |
44 |
夏号 表紙 広島比治山陸軍墓地
特集 戦争と母の歌 城田斗志恵ほか 2
社会詠の本質 大成憲二 2
八日十五日 山本芳美 4
原体験の中より 横山初江 11
原水禁と私の願い 重松静馬 13
広島の七不思議〔二〕 豊田清史 15
同人集 田村伶子ほか 20
「炎の証」への評言 石川キミコほか 34
特別作品 福間彰子ほか 41
火幻集 中丸早苗ほか 43
作品批評 加川学而ほか 53
歌会記 野田一好ほか 59 |
G |
| 19691010 |
45 |
秋号 表紙 広島・不動院蔵重美〈銅製高麗梵鐘〉
第七回火幻賞作品 2
同 選考経過 3
広島県短歌史(一) 豊田清史 18
特別作品 橋本豊子、ほか 21
新鋭集 福間彰子、ほか 26
essay 大成憲二、ほか 31
火幻集 中丸早苗、ほか 48
歌会記 西村さかえ、野田一好 58
編集記 花岡芳春 67 |
G |
| 19691215 |
46 |
新春号 |
PG |
|
|
新春号 表紙・広島原爆ドーム天蓋
特別作品 山本芳美 ほか 2
斗桝先生の一首 小堺吉光 2
広島県短歌史(二) 豊田清史 14
馬場あき子「怨」の美しさ 横山初江 ほか 17
新鋭集 山田美露鬼 ほか 19
同人集 潮規矩郎 ほか 22
essay 野田一好ほか 37
火幻集 六反穂てる清てるほか 44
作品批評 松田弘江 ほか 55
歌会記 仲本政代 ほか 61 |
|
| 19700315 |
47 |
春号 |
N |
| 19700720 |
48 |
夏号 |
NUG |
|
|
新鋭集 山本芳美 ほか 2
火-60年代後半歌集 永井弘子 2
「火幻」1970年春号の作品から 荏原肆子 9
特別作品 有良佳寿 ほか 14
狭庭の記 豊田清史 14
新聞・放送はこれでよいか 豊田清史 19
同人集 松田弘江 ほか 22
essay 鍵田圭子 ほか 38
火幻集 田中睦子 ほか 43
歌集批判 花岡芳春・横山初江 56
歌会記 木山富子・大中よしみ 61
編集記 福間彰子・仏崎紫水 74 |
|
| 19701010 |
49 |
秋号 |
NG |
|
|
第八回火幻賞作品 木本寿亀 2
火幻賞選考経過 編集部 10
特別作品 横山初江 ほか 18
合同歌集「あしあと」合評 編集委員 18
新鋭集 宮本静香 ほか 26
松永信一先生追悼記 秋月佳太・永井弘子ほか 29
同人集 佐々木おらいほか 39
essay 有良佳寿・西岡喜美子ほか 50
火幻集 赤木忍 ほか 55
歌会記 65 |
|
| 19701215 |
50 |
新春号 |
N |
|
|
特別作品
松永先生を思う
評論「生方たつゑ論」
新鋭集
同人集
essay
火幻集
合評「太陽の舟」
作品批評
歌会記
会員年賀広告
編集記 |
|
| 19710310 |
51 |
春号 |
NUG |
|
|
新鋭集 木本寿亀ほか9名 2
短歌文法講義 西原栄穂 2
原爆短歌この二十六年 豊田清史 9
特別作品 松田弘江おか21名 12
同人集 福原律次郎ほか83名 20
essay 梶山雅子 34
火幻集 田中睦子ほか80名 37
宇吹ヤス
疎まるる眸<ひとみ>に馴れし淡き姿〈かげ〉菊香やさしき座に固くおり
合同歌集「結晶」批評特集 山本芳美ほか 49
歌集批評 有良佳寿ほか 65
歌会記/消息/編集記 小川和代ほか 71 |
|
|
|
|
|
| 19710720 |
52 |
夏号「ヒロシマ・平和特集」 |
PNUG |
|
|
ヒロシマ・平和特集……………升政泰ほか28名(2)
知歌文法講義……………西原栄穂(2)
歌壇の切実なこと二つ……………豊田清史(17)
特別作品……………川村伶fほか18名(21)
新鋭集……………山田すなえほか9名(26)舅病む 宇吹ヤス同人集……………上中淳男ほか77名(31)e
ssay……………原博巳ほか(45)
火幻集……………坂口茂雄70名(52)
歌集批評……………(63)
歌会記/消息/編集記……………佐々木三千枝ほか(64)呉吉浦支部歌会記 山田すなえ何時の日あるべし老残わが姿〈かげ〉をおじつつぬぐいゆく舅の漏らす 宇吹ヤス |
|
| 19711020 |
53 |
秋号 |
NP |
|
|
火幻集 宇吹ヤス |
|
| 19711220 |
54 |
新春号 |
U |
| 19720325 |
55 |
<同人三氏追悼号> |
PNU |
| 19720715 |
56 |
夏号 |
NU |
|
|
同人集 pp.40-55。p.46 宇吹ヤス |
|
|
|
宇吹ヤス p.46
いつの日かたぐる想いで煌ける霧氷と並びて夫とタチ足り |
|
| 19721010 |
57 |
秋号<創刊十五周年記念特集号> |
PU |
| 19721215 |
58 |
新春号 |
NU |
| 19730315 |
59 |
春号<*原*夫・梅田昌一・国川浩夫氏追悼> |
NU |
| 19730720 |
60 |
夏号―佐藤求歌集<空寂>批評― |
N |
| 19731015 |
61 |
秋号 |
N |
| 19731210 |
62 |
新年号 |
U |
| 19730310 |
63 |
春号 |
NU |
| 19730710 |
64 |
夏号 |
NU |
| 19741010 |
65 |
秋号 |
U |
| 19741210 |
66 |
新春号 |
NU |
| 19750320 |
67 |
春号 |
NU |
| 19750710 |
68 |
夏号〈原爆30周年特集号〉 |
NUG |
|
|
金井利博君のこと……………近藤芳美 1
みのりある文学の場を……………岩田正 3
ヒロシマ・文学・私……………米満英男 5
「原爆の子」の像の下で……………阿部正路 7
作品・ヒロシマの眼……………四十二名 12
梶山季之君を悼む……………豊田清史 22
第九回合宿研究会の案内………………編集委員会 27
歌会記……………加藤壬子ほか 37
遣遙集……………伊集院督正・東美恵子ほか 34
原水爆作品合評……………松田弘江ほか 44
新鋭集……………尹政泰・藤井逸馬 50
同人集……………佐々木おらい・西原栄穂ほか 54
essay……………横山初江・鳥越典子 68
火幻集……………石田米子・土屋よし子ほか 71
作品批評……………山本芳美ほか 79
編集記……………西岡喜美子・花岡芳春 90 |
|
| 19751010 |
69 |
秋号 |
NU |
| 19751215 |
70 |
新年号 |
NU |
| 19760315 |
71 |
春号 |
U |
| 19760710 |
72 |
夏号 |
NU |
| 19761010 |
73 |
秋号 |
NU |
| 19761210 |
74 |
新年号 |
NU |
| 19770310 |
75 |
春号 |
NU |
| 19770710 |
76 |
夏号「ひろしま33回忌特集」 |
NUG |
| 19771010 |
77 |
秋号「第15回火幻賞発表」 |
NU |
| 19771220 |
78 |
新年号 |
NU |
| 19780310 |
79 |
春号 |
PU |
| 19780710 |
80 |
夏号「核と戦争、広島特集」 |
PU |
| 19781015 |
81 |
「火幻創刊20周年特集」 |
U |
| 19781215 |
82 |
新年号「20周年大会記・歌集「心眼」批評」 |
NU |
| 19790315 |
83 |
春号 |
NU |
| 19790715 |
84 |
夏号「<核と広島>特集」 |
NUG |
| 19791015 |
85 |
秋号―火幻賞・合宿研究会記― |
N |
| 19791220 |
86 |
新年号 |
NU |
| 19800320 |
87 |
春号 |
NUG |
| 19800720 |
88 |
夏号ー原爆35周年特集― |
NUG |
| 19800720 |
89 |
秋号―第18回火幻賞発表― |
NUG |
| 19801220 |
90 |
新年号 |
U |
| 19810315 |
91 |
春号―農村詠特集― |
NU |
| 19810715 |
92 |
夏号―ヒロシマ・反核特集― |
NUG |
| 19811015 |
93 |
秋号 |
NUG |
| 19811220 |
94 |
新年号 |
NU |
| 19820325 |
95 |
春号 |
UG |
| 19820715 |
96 |
夏号「<広島反核110人の作品>特集」 |
NUG |
| 19821101 |
97 |
秋号「<創刊25周年記念号>」 |
UG |
| 19830105 |
98 |
新年号「火幻創刊25周年記念大会記」 |
NUG |
| 19830325 |
99 |
春号「久保田千文追悼記」 |
UG |
| 19830720 |
100 |
夏号「創刊100号記念特集」<反核の歌> |
NUG |
| 19831015 |
101 |
秋号 |
NUG |
| 19831215 |
102 |
新春号 |
NUG |
| 19840320 |
103 |
春号「歌集批評号」 |
NUG |
| 19840710 |
104 |
夏号「特集<今こそ核兵器の廃絶を!>」 |
NUG |
| 19841015 |
105 |
秋号「作品鑑賞批評号」 |
NUG |
| 19841220 |
106 |
新春号 |
NU |
| 19850320 |
107 |
春号 |
NU |
| 1985 0720 |
108 |
夏号「戦後40年、反核特集」 |
NUG |
| 19851020 |
109 |
秋号「西行は宮島に止錫したか」 |
U |
| 19851220 |
110 |
新年号 |
NUG |
| 19860320 |
111 |
春号―歌集批評特集― |
UG |
| 19860720 |
112 |
夏号―反核草の根特集― |
NUG |
| 19861020 |
113 |
秋号―火幻賞発表― |
NUG |
| 19861220 |
114 |
新年号 |
NUG |
| 19870320 |
115 |
春号 |
NU |
| 19870720 |
116 |
夏号―特集<反核作品と絶唱高橋武夫の歌>― |
NU |
| 19871020 |
117 |
秋号―火幻創刊三十周年記念号― |
U |
| 19871220 |
118 |
新年号―創刊30周年記念大会特集― |
NU |
| 19880320 |
119 |
春号 |
NUG |
| 19880720 |
120 |
夏号―反核、ヒロシマはこれでよいか― |
NU |
| 19881020 |
121 |
秋号―火幻賞・合宿研究会― |
NUG |
| 19881220 |
122 |
新春号 |
U |
| 19890320 |
123 |
春号―特集<昭和逝く>― |
U |
| 19890718 |
124 |
夏号―ヒロシマ・反核特集― |
U |
| 19891020 |
125 |
秋号―火幻賞と歌集評― |
NU |
| 19891220 |
126 |
新年号 |
NU |
| 19900310 |
127 |
春号―戦争と歌人― |
U |
| 19900715 |
128 |
夏号―特集<平和、渡辺直己>― |
NU |
| 19901020 |
129 |
秋号―火幻賞・新人賞発表― |
U |
| 19901220 |
130 |
新年号 |
NU |
| 19910320 |
131 |
春号―豊田清史・西岡歌集特集― |
UG |
| 19910718 |
132 |
夏号―平和・汚染はこれでよいか― |
NUG |
| 19911020 |
133 |
秋号―第29回火幻賞、大立、木村歌集評― |
U |
| 19911220 |
134 |
新年号ー火幻創刊35周年―人間性の追求一途に |
NU |
| 19920320 |
135 |
春号―中元・東田歌集批評特集― |
U |
| 19920720 |
136 |
夏号―平和・破壊はこれでよいか― |
NU |
| 19921020 |
137 |
秋号―創刊35周年記念号― |
UG |
| 19921220 |
138 |
新年号ーすぐれた歌碑とは |
U |
| 19930320 |
139 |
春号ーやっと陽の目をみる「黒い雨」と「重松日記」 |
UG |
| 19930720 |
140 |
夏号―特集<ヒロシマはこれでよいか>― |
U |
| 19931020 |
141 |
秋号―<黒い雨と重松日記>特集 第32回火幻賞発表― |
UG |
| 19931220 |
142 |
新年号ー「黒雨」を広島の枕詞としたい(豊田) |
NU |
| 19940320 |
143 |
春号―悼、歌人でもあった森瀧市郎博士― |
U |
| 19940720 |
144 |
夏号「特集<平和と渡辺直己全集>」 |
U |
|
145 |
|
|
|
146 |
|
|
|
147 |
|
|
| 19950710 |
148 |
|
G |
|
149 |
|
|
|
150 |
|
|
| 19960315 |
151 |
|
G |
|
152 |
|
|
| 19961015 |
153 |
秋号 表紙:広島県満州青少年犠牲者の碑 |
NG |
|
154 |
|
|
|
155 |
|
G |
|
156 |
|
G |
| 19971020 |
157 |
|
G |
|
158 |
|
|
| 19980315 |
159 |
春号「七万の無縁骨を平和祈念館に 第35回火幻賞発表」 |
NG |
| 19980715 |
160 |
夏号「総括―井伏作品「黒い雨」に使われた被爆者の手記」、「特集―反戦歌人の第一人者、安藤正楽」 |
NG |
| 19981010 |
161 |
秋号「中丸歌集「旅の衣は」・木原歌集「白き不要」批評」、「これでよいか、体制派歌人」 |
NG |
|
162 |
新年号「特集―末広憲爾歌集「鶴」批評」 |
N |
| 19990310 |
163 |
春号「特集=人間性の追求をヒロシマに、短歌に」 |
NG |
| 19990710 |
164 |
夏号「特集=世の歪みをわれらかく生きる!」 |
NG |
| 19991005 |
165 |
秋号 豊田 評論「原爆死没者記念館に七万人の無縁骨を祀れ」 |
NG |
| 19991210 |
166 |
新年号 田丸綾子「火幻平成11年回顧」 |
NG |
| 20000305 |
167 |
春号「国民文化祭三原市短歌大会を迎える」 |
NUG |
| 20000710 |
168 |
夏号「見つめよう合同歌集「広島」」 |
NG |
| 20001001 |
169 |
秋号「井伏作品「黒い雨」検証のまとめ」 |
NG |
| 20001201 |
170 |
新年号「「火幻」45年を迎える」 |
NG |
| 20010305 |
171 |
|
G |
| 20010615 |
172 |
夏号「37年ぶりに公表された井伏の「重松日記」」 |
NG |
|
173 |
|
|
| 20011210 |
174 |
新年号「全国月の西行祭10年・火幻45周年」 |
NG |
| 20011210 |
175 |
春号 |
N |
| 20020710 |
176 |
夏号「井伏著「黒い雨」盗作の結末特集」 |
NG |
|
177 |
秋号 |
N |
|
178 |
|
|
|
179 |
春号 |
N |
| 20030625 |
180 |
夏号「特集―反核・非戦に生きる―」 |
NG |
| 20031005 |
181 |
|
G |
| 20031210 |
182 |
新年号「豊田清史歌集「幽魂」特集」 |
NG |
| 20040310 |
183 |
春号「特集<憲法第9条が踏みにじられる>」 |
NG |
| 20040705 |
184 |
夏号「特集<真に反核、非戦を生きた歌人>」 |
N |
| 20041001 |
185 |
秋号 |
NG |
|
|
essay 田中蔦江「今も忘れない被爆のこと」 |
|
| 20041210 |
186 |
新年号「巻頭言 これでよいか、原爆慰霊碑文」(豊田清史) |
|
| 20050310 |
187 |
春号「被爆60年、ヒロシマを生きる」 |
NG |
| 20050710 |
188 |
夏号「被爆60年、原爆、劣化ウランを許さない」 |
NG |
| 20051010 |
189 |
秋号「特集 全国反核秀歌二十首」 |
NG |
| 20051210 |
190 |
新年号「特集・火幻創刊50年を迎える」、「松田弘江夫人追悼」 |
N |
| 20060310 |
191 |
春号 |
NG |
| 20060710 |
192 |
夏号「創刊50年記念号 ―人間性の追求―」 |
G |
| 20061020 |
193 |
豊田清史「表紙、湯川博士の品格の歌」 |
N |
| 20070310 |
194 |
火幻創刊50周年記念大会 |
G |
|
|
西岡喜美子「師の第一歌集「暁雲」を読みて」 |
|
| 20070701 |
195 |
<特集反核社会詠に挑む> |
NG |
| 20071001 |
196 |
木村房子刀自哀悼 編集部 |
N |
| 20080201 |
197 |
会員の人へ 「豊田は病院や治療に行って不在の時が多く・・・」 |
NG |
| 20080620 |
198 |
essay 二人の生き方 岡部伊都子と深川宗俊 |
N |
| 20081020 |
199 |
巻頭言 63年たってもまだ属国 |
N |
| 20090220 |
200 |
創刊50年・第200号特集号 |
N |
| 20090710 |
201 |
表紙絵 ヒロシマの花「夾竹桃」―入野忠芳画伯 |
N |
| 20091010 |
202 |
評論 井伏鱒二の「黒い雨」 |
N |
| 20100301 |
203 |
essay 平山郁夫君を思う豊田清史 |
N |
| 20100710 |
204 |
逍遥集作品 死ぬために生き来しか 西岡喜美子
☆小松茂美君を悼む <5月21日> |
N |
|
|
消息
☆高橋一起氏
☆豊田清史
☆第19回やすうら西行祭
☆野村剛先生逝去 <5月27日> |
|
| 20101010 |
205 |
〈評論〉全国に見る真に非戦、反核に生きた歌人 豊田清史 |
N |
| 20110305 |
206 |
巻頭言 本音を吐く…豊田清史
一首鑑賞-豊田清史の歌…豊原国夫…1
評論 大江健三郎の文学、ヒロシマへの期待と失望…豊田清史…2
今の短歌に言いたいこと…山田忠義…10
逍遥集作品
… 山田美露鬼、豊原国夫、西岡喜美子、増原淳子、
木村佐和子、東美恵子、吉口ツネヨほか ……12
essay
… 帝釈峡の見どころ-宮野滋子…25
良寛の書のこと-小川浩恵…26
第19回「やすうら月の西行祭」に思う-西岡喜美子…28
自分でも平凡な歌は捨てる自覚-豊田清史…27
歌集評 宮原小美枝「赤糸てまり」…30
支部作品 世羅宇根火三月歌会作品、神石山法師短歌会…36
消息…編集部…39
編集記…木村佐和子、後藤幸子、豊田清史…40 |
NG |
| 20110705 |
207 |
依頼原稿 新市長の望む 北西允 02 |
N |
| 20111030 |
208 |
編集記(豊田啓文)「今年の八月五日、父清史が突然意識を失い、救急病院に運ばれました。検査の結果、脳梗塞と診断され、意識が回復しないまま病床に寝たきりで今日に至っております。」 |
N |
| 同年11月24日没。 |
|
止
1979年4月『記録』を創刊。編集=記録の会、発行=記録社、発売元=すずさわ書店
発行状況
| 号 |
発行年月日(著者) |
備考(タイトルなど) |
| 01 |
19790401 |
|
|
記録の会 |
月刊誌『記録』発刊にあたって |
|
土本典昭 |
水俣―映画記録者として |
|
大峯雄輔 |
ロボトミー―人間管理の究極なるもの |
|
本多勝一 |
ルポルタージュの方法① |
|
松浦総三 |
日本のルポルタージュついて―覚え書き(上) |
|
松井やより |
鎖国と友好―わたしの中国滞在・往来記① |
|
上坪隆 |
非業の死を語りつづける―九州で取材して |
|
栗原貞子 |
反核意識の再構築を―第1回原爆問題総合研究会の記録 |
|
岡邦俊 |
キャロル① |
|
白基□(飛揚訳) |
民族の分断と人権(上) |
|
コラム |
微罪で全裸にされ |
|
|
TVドキュメント‘79『原爆の子・百合子』 |
|
|
よみがえれ国際人民相互の信頼と連帯 |
|
|
箙田鶴子『他者への旅』 |
|
|
松本竣介の大回顧展 |
|
|
無知の告白―『朝鮮通信使』のこと |
|
|
身障児から教えられる関係 |
| 02 |
19790501 |
|
|
大牟田稔 |
二枚の認定書―被爆者母娘をめぐる生と死 |
| 03 |
|
|
| 04 |
|
|
| 05 |
|
|
| 06 |
|
|
| 07 |
19790701 |
|
|
丸木位里・丸木俊・石川保夫・長岡弘芳 |
|
|
民衆をいかに絵できろくするか―丸木位里・丸木俊夫妻を囲む座談会 |
| 08 |
|
|
| 09 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 |
19800801 |
|
|
吉川土竜・吉川敏 |
広島日記―ある銀行員の原爆投下前後の日記から |
| 18 |
|
|
| 19 |
|
|
| 20 |
19801101 |
|
現代史研究会(1957年)
『戦後日本の国家権力』(現代史研究会<著者代表:石井金一郎>、三一書房、1960年8月25日)
同上「はしがき」
本書は、広島に在住する社会科学者の有志の共同研究によって成ったものである。共同研究は、政治学・経済学・歴史学のそれぞれの専攻の立場から、一つの研究会で討論することによって、進められた。テーマを定めて、専攻分野の異なる研究者が共同研究を進めていくということは、困難でもあったが、有益でもあった。
われわれの研究会が発足したのは、いまから三年ほど前である。メンバーの全員が社会科学(政治・経済・歴史)を専攻している者だといっても、各人の研究対象は区々なので、普通の研究会ではなかなか討議が発展しない。それで、専攻はちがっても社会科学者として現在の日本の問題に関心をもつ点では一致しているのだから、この一致している対象を共通の場にして研究会をつくろうということで会が出発した。
その後、研究の対象を、さらに戦後の日本の従属と自立の問題にしぼり、これを中心にして、各人が一応分担をきめ、報告・討議の形式をとって研究会を進め、今日に至った。
その間には、参加者のなかで、外国留学・国内研修のため広島を離れ、研究会参加を中断した人もでた。また今年になって転勤のため広島を離れた人もある。
いまその結果を公にするわけであるが、研究会の全員が共同執筆に参加したのではない。表題のテーマで問題を分担した者だけが執筆に参加した。
本書で取り扱うテーマは、実践的な問題につながるものであるが、われわれは、これを学問的立場から共同討議していった。本書のテーマは、すでにこの数年来実践的立場から論争されている問題であるが、われわれは、論争に直接に参加するのでなく、論争の基礎となるべき事柄を、資料の問題・概念整理の問題を中心に、提起したいと思う。
本書の構成は、戦後日本の権力論と、政治過程論の二部構成をとった。
権力論においては、第一章において、戦後日本の権力問題についての通観を試みた。したがって、第一章は、本書全体の通論的性格をもっている。
政治過程については、戦後の時代を大きく三つにわけて、問題史的なとりあげをおこなっている。ただ、政治過程の部は、問題史的に扱っているので、簡単にしかふれられていないところもあり、また、三人の問題意識も異なっているので、通史としての役割は、果しえていない。第二章は占領中のアメリカの対日政策をとりあげたものであり、第二章においては、講和後(鳩山内閣まで)の政治過程を通じて、当時の日米関係を追及している。第三章は、日本独占資本の現時点における要求が岸内閣の諸政策の中に、どのように反映しているかを明らかにしたものである。
このように、第二部における三つの章は、それぞれ、視角を異にしているので、三つは章でつながっているが、個々の章は、それぞれ、独立論文として読んでいただきたい。
補論はいわば、第一部の補足的意味をもつものであり、中国の公的な発表にもとづいて、中国の日本国家にたいする権力規定を時代的に整理したものである。
本書の内容については、できるだけ共同討議によって意思統一することにつとめ、また分担執筆後も、第一次原稿にもとづいて討論し、その討論の結果書き改められたものについてさらに討議をおこない、最後原稿についても調整をするという手続きをとって意見の統一につとめたが、研究会の性質上、意見の統一は強制しなかったので、本書のすべての部分について、共同研究者が見解を一にしているわけではない。とくに、第一部第一章において取り扱われている中立の問題については、他の部分と同じように、共同執筆者の討論をへて執筆されているのであるけれども、
この問題について、他の共同執筆者に充分な理論的準備がなかったため、共同執筆者の一致した見解となっていない。
しかし、細部においては必ずしも見解の一致がないにもかかわらず、本書の全体を通じて、理論の不一致にもとづく混乱はない筈である。本書は、一つのまとまった戦後権力の研究となっていると思う。
なぜならば、我々は、戦後の日本の権力の把握において、もっとも基本的な点では意見が一致しているからである。
それではわれわれの一致致している点、言葉をかえていえば、本書を一貫して貫いている理論的立場は、どのような立場であるのか。
第一は、従属の問題を、上部構造と下部構造との相関に於いてとらえようとする点である。(中略) 第二は、戦後の日本は、占領中も含めて、一貫して、民族国家として存在していたという認識である。(中略) 以上の二点において、共同執筆者は全員の見解が一致している。したがって本書を通じて、各執筆者の間に、基本的な点では相違が無い。
われわれの共同研究は、まだ未熟であって、残された問題も多く、掘り下げの弱い部分も多々あることを痛感している。それにもかかわらずあえて本書を公にするのは、それによって読者の厳正な御批判をいただき、今後の研究の大きな助けとしたいと思うからである。
われわれは、今後も共同研究をつづけていきたいと思っている。読者諸氏が厳しい御批判をよせられることを期待してやまない。(石井金一郎)
<著者略歴抄>
中村義知
なかむら よしとも
1926年生る
1949年東京大学法学部政治学科卒業
現在広島大学助教授
山田浩
やまだ ひろし
1925年生る
九州大学法学部卒業
現在広島大学助教授
石井金一郎
いしい きんいちろう
1922年生る
京都大学法学部卒業
現在広島女子短期大学助教授
大江志乃夫
おおえ しのぶ
1928年生る
名古屋大学経済学部卒業
現在東京教育大学助教授
横山英
よこやま すぐる
1924年生る
広島文理科大学卒業
現在広島大学講師
広島原爆被災撮影者の会
設立準備会?:19780715
関係資料
「芸備地方史研究」目次(抄)
| 号 |
発行年月日 |
著者 |
備考(論文名など) |
所蔵 |
| 001 |
1953.07 |
魚澄惣五郎 |
創刊をよろこびて |
|
| 011 |
1955.03 |
熊田重邦 |
書評 「概観広島市史」 |
|
| 016 |
1956.02 |
|
歴史教育と地方史研究 |
|
| 017・018 |
1956.07 |
人物広島史 |
P |
|
|
今堀誠二 |
原爆戦争に抗して峠三吉 |
|
| 019 |
1956.11 |
山代巴著≪荷車の歌≫をめぐって |
|
|
金井利博 |
時間の貧しさということ |
|
|
|
山手茂 |
村落研究をめぐる若干の問題 |
|
| 035 |
1960.12 |
佐久間澄 |
今堀誠二著『原水爆時代』を読んで |
|
| 041・042 |
1962.6 |
天野卓郎 |
『原水爆被害白書』 |
|
| 045 |
|
|
小倉豊文「中国文化賞受賞」 |
|
| 051 |
19640705 |
戦後における広島県地方史の成果と課題Ⅱ |
P |
| 055 |
1965.5 |
|
国立史料センター設立について |
|
| 060 |
1966.4 |
|
広島県立文書館設立のために(一) |
|
| 061 |
1966.6 |
土井作治 |
動向「県立文書館設立推進のために(その二)ー全国公共図書館研究集会に参加してー」 |
|
| 062・063 |
1966.11 |
|
「建国記念日問題について」 |
|
|
|
|
動向「県立文書館設立のために(三)」 |
|
| 64 |
1967.2 |
動向・時評 |
「教科書検定問題をめぐる懇談会」報告 |
|
|
|
|
「広島県立文書館設立のために(四)」 |
|
| 065・066 |
|
|
「広島県立文書館設立のために(五)」 |
|
|
|
|
「建国記念の日」のヒロシマ |
|
| 068 |
1967.9 |
|
動向「広島県立文書館設立のために(七)」 |
|
| 072 |
1968.6 |
志水清 |
調査報告 「爆心地の追跡調査について」 |
P |
|
|
田村裕 |
「爆心地(中島本町)第一次調査に参加して」 |
|
|
|
|
動向・時評 「建国記念の日」のヒロシマ(2) |
|
| 076 |
1969.1 |
今堀誠二 |
広島原爆被害資料の保存をめぐって |
P |
| 077 |
1969.5 |
|
動向 「明治百年祭」と広島 |
P |
| 078 |
1969.6 |
小堺吉光 |
広島原爆戦災誌の編集にあたって |
P |
| 080 |
19700531 |
|
「建国記念の日」のヒロシマ(4) |
P |
| 081・082 |
1970.6 |
|
合評『広島県の歴史』 |
P |
|
|
横山英 |
新刊紹介『未来を語りつづけてー原爆体験と教育の原点ー』 |
|
| 090 |
1972.3 |
上原敏子 |
論稿「在広朝鮮人被爆者についての一考察(1)」 |
P |
| 091 |
19720615 |
|
論稿「在広朝鮮人被爆者の現況(2)」 |
P |
| 096 |
1973.12 |
常任委員会 |
動向 「広島県文書館設立のために」 |
|
| 097・098 |
1974.5 |
小倉豊文 |
創刊二十周年に際し |
|
| 099 |
1974.8 |
宇吹暁 |
史料紹介 明治期県内発行の新聞・雑誌 |
|
| 108 |
1976.6 |
川島孝郎 |
論説 原爆教育の課題 |
|
| 140・141 |
1983.6 |
宇吹暁 |
論説 『被爆体験』の展開-原水爆禁止世界大会の宣言・決議を素材として- |
|
| 162 |
1987.11 |
石丸紀興 |
論説 『広島平和記念都市建設法』の法案とその形成過程に関する考察 |
|
| 171 |
1989.12 |
今正秀 |
書評 大田英雄『父は沖縄で死んだ-沖縄海軍部隊司令官とその息子の歩いた道-』 |
|
| 178 |
1991.10 |
千田武志 |
論説 英連邦占領軍の日本進駐-宥和政策の推移を中心として- |
|
| 186・186 |
1993.9 |
小特集 「建国記念の日」ルポの成果と課題 |
|
|
三沢純 |
広島における「建国記念の日」をめぐる諸潮流 |
|
|
|
委員会 |
座談会 継続企画『「建国記念の日」のヒロシマ』二十七年を振り返って |
|
| 200 |
1996.6 |
道重哲男 |
芸史創刊のころ |
|
| 202 |
1996.10 |
シンポジウム特集号―あ097/らためて原爆遺跡保存を考える― |
|
|
村中好穂 |
原爆遺跡を考える |
|
|
|
楠忠之 |
この声にどう応えるか |
|
|
|
小原誠 |
旧大正屋呉服店存廃についての市長発言への反論 |
|
|
|
今正秀 |
『被爆建物』保存の論理・破壊の論理 |
|
|
|
基調報告 |
|
|
山瀬明 |
爆心地の実相を語るレストハウス保存について |
|
|
|
石丸紀興 |
増田清と大正屋呉服店 |
|
|
|
長谷川博史 |
原爆遺跡保存の歴史的意義について |
|
| 207・208 |
1997.12 |
特集 原爆ドーム・厳島神社の世界遺産登録Ⅰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 209 |
1998.3 |
特集 原爆ドーム・厳島神社の世界遺産登録Ⅱ 原爆ドームの世界遺産登録 |
|
|
村中好穂 |
原爆ドームが語る戦後広島の奇跡―何が、どのように世界遺産に登録されたか― |
|
|
|
石川まゆみ |
原爆ドームが私たちに語るものを伝えるために―授業実践例― |
|
|
|
吉川生美 |
被爆者の分身 原爆ドーム |
|
| 230 |
2002.4 |
広島県地方史研究の成果と課題Ⅲ 近現代-原爆・強制連行・大久野島- |
| 231・232 |
2002.6 |
|
動向 「日の丸・君が代」新聞記事目録 |
|
| 237 |
2003.6 |
道重哲男 |
後藤陽一先生を悼む |
|
| 239 |
2004.2 |
松下宏・千田武志 |
呉空襲後の住宅難を救った「三角兵舎」 |
|
| 247 |
2005.06 |
石田雅春 |
占領期広島県における高校再編成と軍政部の役割 |
|
|
|
|
|
|
| 250・251 |
2006.04 |
小特集 「被爆60年と史・史料保存-現状と課題を考える-」 シンポジウムの記録 |
|
|
石丸紀興 |
建造物の観点から |
|
|
|
宇吹暁 |
文献資料の観点から |
|
|
|
高野和彦 |
モノ資料の観点から |
|
|
|
高木泰伸 |
参加記 |
|
|
|
橋本啓紀 |
書評 こうの史代著『夕凪の街 桜の国』 |
|
|
|
小宮山道夫 |
「平和学術文庫」の開設について |
|
| 253 |
2006.01 |
土井作治 |
追悼 道重・畑中両先輩を悼む |
|
| 254 |
2007.06 |
石田雅春 |
新刊紹介 広島大学文書館編『広島から平和について考える』 |
|
| 255 |
2007.04 |
菅真城 |
新刊紹介 原爆遺跡保存運動懇談会編『広島 爆心地 中島』 |
|
|
|
渡邊誠 |
頼祺一編『街道の日本史41広島・福山と山陽道』 |
|
| 258・259 |
2008.02 |
特集 厳島研究の過去・現在・未来 ―厳島神社世界遺産登録10周年記念― |
| 266 |
2009.06 |
特集 呉の近代と海軍―モノと文書から考える |
|
|
秦郁彦 |
ミッドウェー海戦の再考 |
|
|
|
小池聖一 |
水野広徳と海軍、そして軍縮 |
|
| 272 |
2010.06 |
小特集 広島平和記念都市法制定60周年にあたり理学部一号館の保存・活用を考える ―声なき証言者を次の世代に伝えるために― |
|
|
布川弘 |
広島の復興と広島平和記念都市法 |
|
|
|
石田雅春 |
広島大学旧理学部一号館のあゆみ |
|
|
|
渡辺一雄 |
自然史系博物館の必要性と旧理学部一号館の活用 |
|
| 304 |
2017.2 |
|
小特集 「『建国記念の日』のヒロシマの五〇年」 |
|
|
|
石川遥 |
広島における「建国記念の日」関連行事の動向 |
|
|
|
石川遥 |
広島における「建国記念の日」関連行事一覧 |
|
被爆の遺言-被災カメラマン写真集(広島原爆被災撮影者の会 著・刊、1985/08/01)内容
|
|
| [はじめに] |
松重美人(広島原爆被災撮影者の会代表) |
|
被爆から40年。当時の状況を撮影する20人の被爆カメラマンも、時の流れに7人を失う。 |
| 原子雲 昭和20年8月6日8時15分 |
|
|
|
| 8/6日7日 |
|
|
|
| 救護活動 |
|
|
|
| 崩壊 |
|
|
|
| 爆風 |
|
|
|
| 熱線・流失 |
|
|
|
| 日赤 |
|
|
|
| 救護所 |
|
|
|
| 人体 |
|
|
|
| 私たちが見たあの日 |
尾糠政美、尾木正己、鴉田藤太郎、川原四儀、川本俊雄、岸田貢宜、岸本吉太、北勲、林寿麿、黒石勝、木村権一、空博行、斎藤誠二、森本太一、深田敏夫、松重三男、山田精三、松重美人。 |
|
|
|
|
原爆被害相談員の会からの報告(IPSHU研究報告シリーズ No.23 広島大学平和科学研究センター 1996年3月1 日)
| 著者 |
タイトル |
| 相良カヨ(原爆被害者相談員の会) |
被爆者とABCC |
| 三村正弘(広島県保険医協会) |
原爆被害者援護法と社会保障の一考察 |
| 若林節美(広島YMCA健康福祉専門学校) |
被爆者は今 |
| 船橋喜恵(広島大学総合科学部) |
原爆被害者相談員の会の歩み |
|
|
ヒロシマの歴史を残された言葉や資料をもとにたどるサイトです。