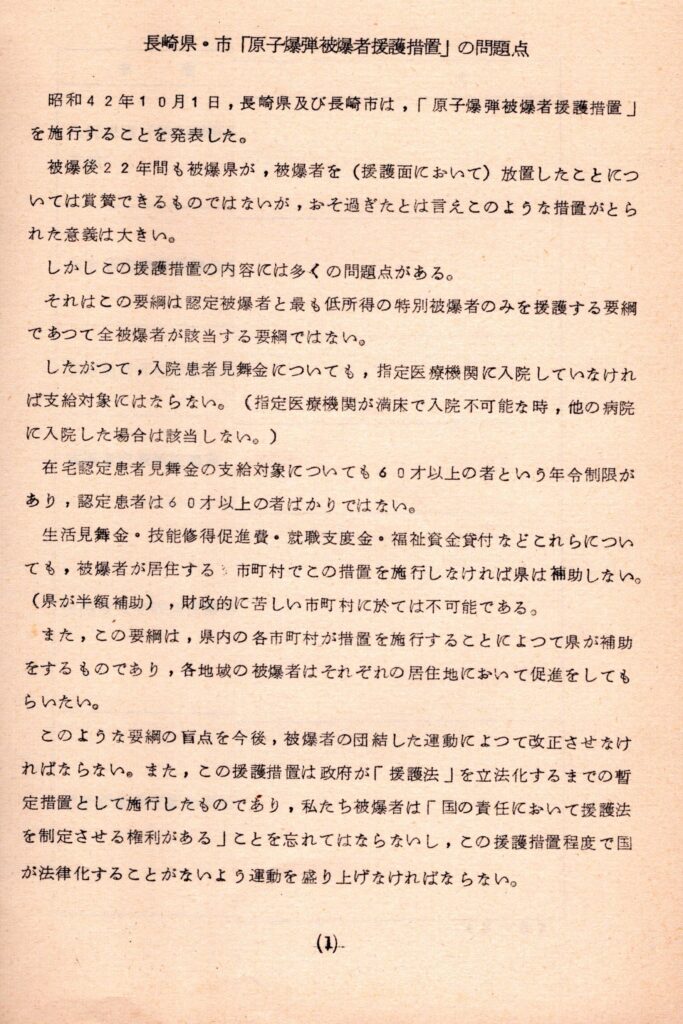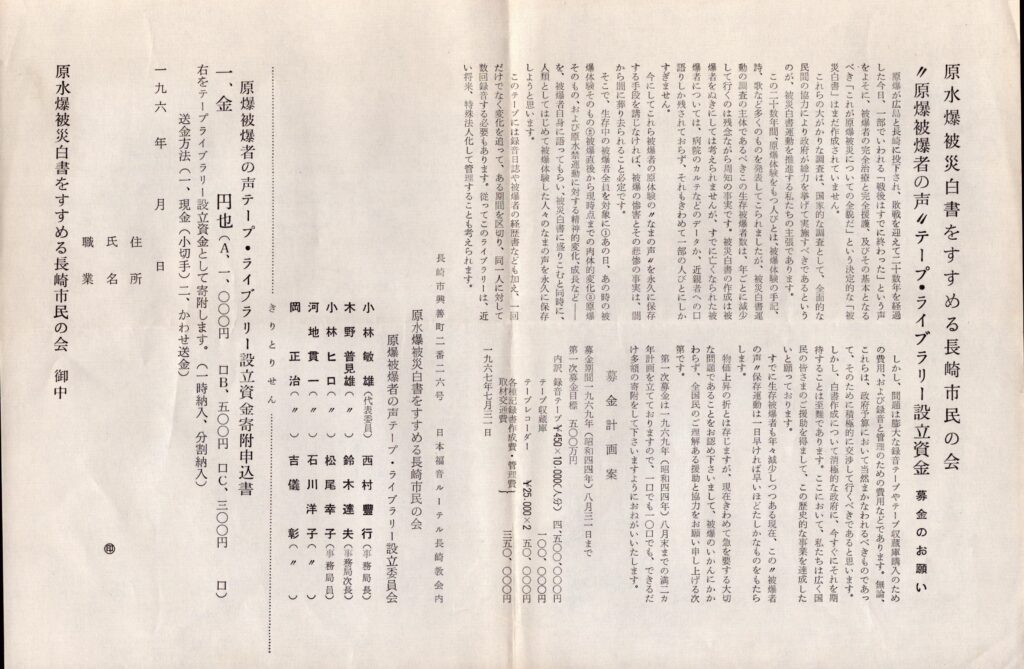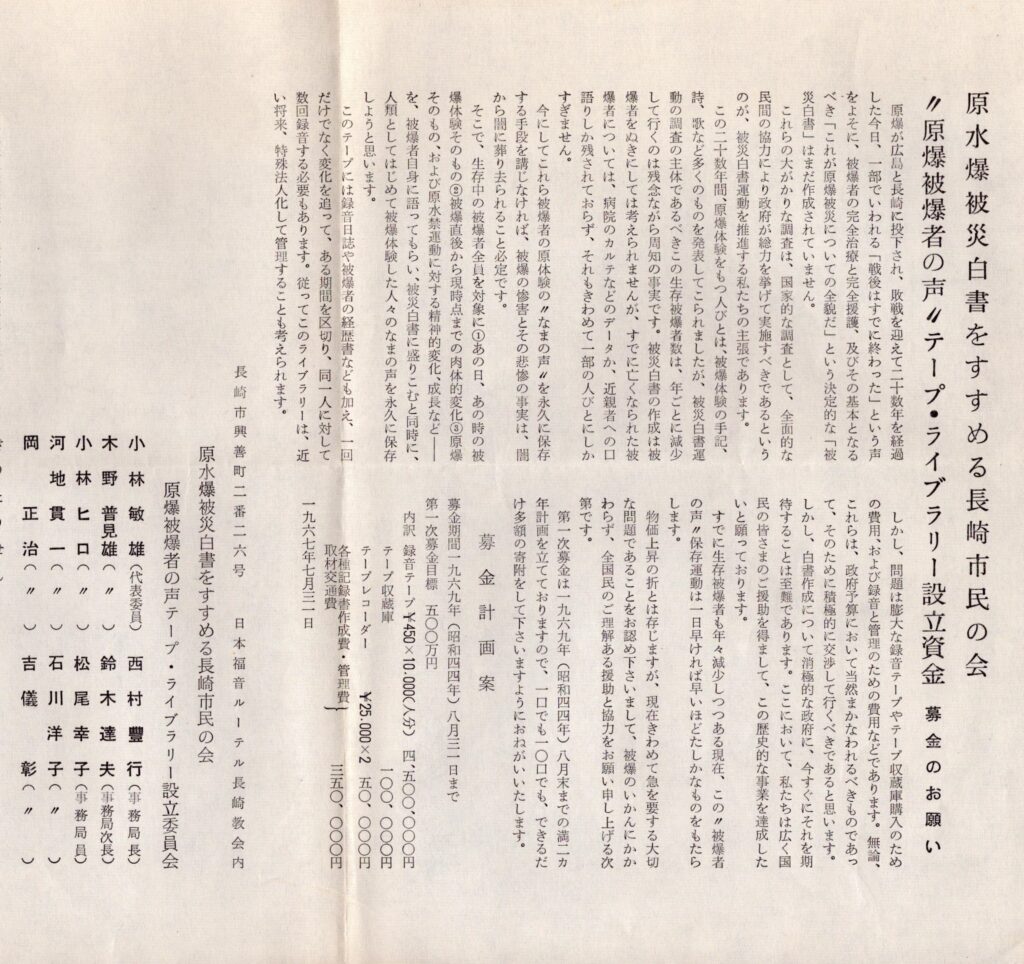|
|
|
|
〔版画〕
和蘭陀船
唐人舟
原爆の遺跡浦上天主堂
日本二十六聖人殉教の聖地
〔写真〕
文化黎明の長崎
国宝崇福寺堂内仏佛像
国宝大浦天主堂堂内
新緑の長崎
坂の長崎石畳
国宝興福寺
国立公園雲仙ゴルフ場
〔特集〕
天皇陛下行幸記
聖フランシスコ・ザビエル来訪400年記念祭 |
|
|
〔本文〕 |
|
|
総論
長崎年表 1
長崎史 5
地理的に見たる長崎 7
面積
地形 8
海面
陸地
海岸
潮流
海流
長崎史の地勢
外国駐在機関
県外務課に於ける渉外事務 9
長崎民事部
原爆傷害調査委員會(A・B・C・C)
中華民国駐日代表団長崎僑分処 10
デンマーク代表団
フランス領事館
自治行政
地方自治 11
長崎県に於ける有権者
郡市別有権者
長崎市選挙管理委員会
長崎市議会議員名簿
長崎市議会常任委員 12
長崎市議会議席表
長崎史歴代市会議長名 13
長崎県選挙管理委員会
長崎県会議員名簿
長崎県議会議席表 14
長崎県議会常任委員会名簿
長崎県議会議員所属党派別名簿 15
長崎県選出衆議院議員
長崎県選出参議院議員
佐世保市議会議員名簿
諫早市議会議員名簿
大村市議会議員名簿 16
島原市議会議員名簿
町村会議長名簿 |
|
|
|
|
|
○政党及協会
民主自由党長崎県支部 17
民主党長崎県支部
日本社会党長崎市支部
国民協同党長崎県連合会支部
日本共産党長崎地方委員会
新政会
ソ同盟帰還者生活擁護同盟長崎市部
長崎中日公会
中日文化懇親会
労働民生協会
民生日本建設促進会
九州青年連盟長崎市部
水ノ浦町振興会
行政官庁
長崎市役所18
長崎市歴代市長
長崎市役所職員名簿
市政60周年記念表彰者
長崎市役所事務分掌 19
長崎市校区別町名並に世帯敷人口 20
長崎県庁 24
長崎県歴代知事
長崎県庁職員名簿
長崎県庁事務分掌 25
市町村別面積及人口 28
地方事務所所在地並職員 31
市長助役収入役名簿(全市町村) 33 |
|
|
○市財政
昭和24年度一般会計予算 33
同 特別会計
監査制度 34
長崎県監査委員
長崎市同 |
|
|
警察消防
○警察制度
公安委員会の任務 35
県市町村公安委員名簿
国家地方警察長崎県本部職員 36
築警察署所在地並管轄区域
国家地方警察長崎県本部事務分掌 37
同 警察学校
自治警察長崎市警察署
長崎市警察署事務分掌
同 各地区警部補派出所 39
福岡管区本部長崎県通信出張所
警察電話と接続出来る公衆電話番号
表彰20年以上勤続警察官
長崎県昭和23年中刑法犯発生検挙表 40
○消防制度
消防に就いて
長崎市消防署 41
長崎市消防組織
長崎市消防本部事務分掌
消防自動車の整備状況
長崎消防団本部
梅ケ崎同
稲佐 同
土井首同 42
水上 同
火災発生件数 |
|
|
司法
裁判所、検察庁、地方法務局機構一覧 43
新憲法による裁判所
長崎地方裁判所
長崎家庭裁判所
長崎簡易裁判所… 44
長崎県下家庭裁判所並職員名簿
長崎県下簡易裁判所並職員名簿
地方裁判所第一審刑受件数調
地方裁判所民事新受件数調 45
家庭裁判所新受件数調
簡易裁判所民事新受件数調
簡易裁判所刑事新受件数調
昭和23年度一審科刑罪名別比較表 46
検察審査会
検察審査会とは?
長崎地方、区検察庁 47
長崎地方、区検察庁職員名簿
長崎地方、区検察庁機構図 48
23年度罪名別並に受理件数
長崎弁護士会 49
観察保護の状況
支部区別処理件数総括表 51
浦上拘置支所
犯罪予防更生法による官庁機構 52
司法保護委員会の任務 53
長崎区司法保護協議会委員名簿
人権保護会 54
長崎少年保護観察所
長崎成人同
司法委員等名簿並敷調
公証人役場
長崎地方法務局所属司法書士連合会 55
司法委員等の任務と選任
調停委員等の種別と関与事件一覧 |
|
|
教育
教育委員会制度化の教育運営 57
教育委員会事務局機構 58
教育委員会委員 60
教育委員会職員名簿
教育委員会事務分掌
不就学児童 61
長崎市立小学校一覧
長崎市立中学校一覧 62
長崎市所在高等学校、特殊学校
国立長崎大学 63
佐世保市所在学校一覧
諫早市所在学校一覧 64
大村市所在学校一覧
島原市所在学校一覧 65
西彼杵郡所在学校一覧 66
北高来郡所在学校一覧
南高来郡所在学校一覧 67
南松浦郡所在学校一覧 68
北松浦郡所在学校一覧 69
壹岐郡所在学校一覧 70
下県郡所在学校一覧
上県郡所在学校一覧 71
長崎市小中学校P・T・A
郡市別高等学校数 72
制度別高等学校数
県立長崎女史短期大学
幼稚園組織数及幼児数
小学校児童数
中学校児童数
高等学校生徒数 73
教員数
長崎外国語学校
活水女子専門学校 74
CIE図書館
同 夜間講演会 75
同 閲覧者調査表
同 閲覧人員 76
県立長崎図書館
郡市別図書館一覧 77
長崎市博物館 78
県立長崎図書館蔵書分類表 80
長崎市博物館資料明細 81
同 博物館主要所蔵物目録 83
日本最初の印刷術… 85
同 写真術 |
|
|
海運
九州海運局長崎市局 87
港湾運送業の形態に就いて 88
港湾施設一覧
倉庫設備
長崎倉庫業組合
倉庫業者並に保有残高 89
倉庫の復興状況
長崎港における汽船出入港調
外国船の荷役状況
機帆船の地位とその運航体制の変遷 90
物資別輸送計画対実績表 91
西部海運長崎支店保有船
中央機帆船輸送実績表 92
地区機帆船輸送用燃料割当
年度別長崎機帆船腹表
長崎を中心とせる交通船の現状
交通船組合
定期交通船航路主要度判定基準 93
定期交通船経営者別航路調
経営者別定期交通船燃料割当量及輸送実績 94
船員法に就て 96
船員法適用船舶の実態調 97
船用米購入通帳交付状況
船員用主要食糧受配状況 98
船員用調味品副食物配給状況
陸上米と比較したる船用米配給状況
24年度船用主要食糧配給状況
海運局指定船舶食糧配給機関 99
船員厚生施設
船舶登録件数調
監査状況調
在籍船舶数調
船舶検査件数調 100
船舶測度件数調
輸出船の問題
全国鋼造船工場数及従業員数
終戦後建造を許可された船舶
造船工場の能力 101
全国中在長崎工場の能力順位
西日本重工業株式会社長崎造船所
施設及能力 102
乾船渠、船台
21年度以降の生産実績
イ 新造船
ロ 修理船 103
川南香焼島造船所
船舶用機関政策及修繕実績調
木造建造用修繕実績調 104
昭和23年度木造船舶造修実績
造船関連工場実績 105
長崎海上保安部 106
長崎港湾事務所
主要港の泊地面積及水深
船舶運営会長崎市部
川南工業株式会社香焼島造船所職員名簿
同 深堀造船所職員名簿
同 サルベージ部
同 小型船舶修理部職員名簿 |
|
|
陸運
○鉄道
長崎管理部 107
鉄道延長粁
自動車線路延長粁
駅区所在人員
旅客輸送概況 108
旅客関係運輸統計 109
不正乗車処理状況 110
荷物運輸統計
線区別交通量 111
引揚邦人及び復員軍人輸送実績
現在車使用車運用効率 112
貨物輸送概況
貨物統計総合表
雑貨主要品別発送噸数統計表 113
貨物発送噸数、貨物収入一日平均
月別発送噸数統計表
貨物輸送要請計画及実績 114
貨物収入
小口貨物輸送状況
主要品名別貨物発送噸数 115
石炭輸送状況
輸入貨物輸送状況 116
鮮魚輸送状況
陶器輸送状況
石炭地区別発送噸数 117
枇杷輸送状況
鮮魚輸送仕様車
客貨車洗滌設備
機関車走行粁
機関車配置数
貨車の修理輌数
長与勾配牽引輌数
特殊貨車常備数
客車常備輌数
機関車の石炭、砂、水一日使用量 118
転車台の長さ
客貨車給水洗滌用一日水量並塵埃量
客車一日平均消毒清掃輌数
客車の記号
貨車の記号
長崎駅引込線
長崎駅運輸統計
長崎駅発送貨物統計 119
長崎駅到着貨物統計
佐世保駅運輸統計 120
諫早駅運輸統計 121
大村駅運輸統計
有田駅運輸統計
平戸口駅運輸統計 122
早岐駅運輸統計
島原鉄道車線主要品名別発送噸数
鉄道弘済会長崎営業所 123
○自動車
福岡陸運局長崎分室
自動車運転者数
自動車測度制度
自転車台数
国有鉄道長崎自動車区
長崎自動車区運輸統計
地区別車輌統計表
一般乗合自動車一覧
長崎県公共事業部
同 旅客収入統計
長崎自動車株式会社
島原鉄道株式会社
西肥自動車株式会社
佐世保市交通課
五島自動車有限会社
壹岐交通株式会社
対馬交通株式会社
北対馬自動車株式会社
一般貸切旅客自動車運送事業
一般貨物旅客自動車運送事業
特定貸切貨物自動車運送事業
一般積合貨物自動車運送事業
○電車
長崎電気軌道株式会社 |
|
|
通信
長崎郵便局 128
本博多郵便局
長崎市内特定郵便局
長崎市内配達区域町名
長崎郵便局業務統計 129
外国郵便差出国別小包数
簡易生命保険 130
郵便年金
長崎電気通信部 131
長崎電気通信管理所
電気通信省長崎関係組織表
長崎電話局
長崎電話局5月中調査日に於ける統計
海底電話線使用区間 132
電信線架設状況主要回線
長崎電報局
長崎市内電報受付局及配達局
長崎国際電報局
海外宛電報の発信方法 133
対外電信通信回路
通信設備
長崎貯金支局
振替貯金状況 134
郵便振替貯金法に於ける小切手払の制度
社会
共同募金 135
長崎県共同募金委員会
23年度共同募金の配分 136
24年度共同募金郡市別目標割当額 |
|
|
民生員に就いて
長崎市民生常務委員地区別指名
6月末現在援助世帯 137
生活保護法に依る保護施設
生活扶助費基準額
長崎市社会事業助成協会
生活困窮者統計表 138
要援護者統計表
同胞援護会長崎県支部 139
同 長崎市支会 140
日本赤十字社長崎支部
済生会長崎病院
○児童保護
長崎中央児童相談所 141
児童福祉施設
里親制度に就いて 142
児童身体検診査計
長崎市内幼稚園一覧 143
中学生児童刑法犯統計
○引揚援護
長崎県の引揚者宿泊所一覧
未復員届について
帰還輸送船 144
長崎県引揚者残留者調
長崎県引揚者数
佐世保揚陸年次別表
送出員数調
方面別管内軍人軍属復員状況
傷痍者保護 145
長崎県傷痍者保護対策委員
ララ救援物資
厚生年金保険給付状況
社会保険加入状況
健康保険給付状況 146
失業保険金支給総額
災害救助 |
|
|
保健
長崎市保健所 147
同署業務日程
栄養指導業務成績表 148
母子保健事業
乳幼児相談一覧表
乳幼児健康診査成績表
栄養種別7ケ月未満調査
健康婦の業務 149
保健所に於ける妊産婦保護状況
保健所に於ける乳幼児保護状況
結核予防 150
性病診療
救ライ運動
本県の風土病について 151
鼠族昆虫駆除及都市清掃事業 152
伝染病一覧
死亡率統計図表 153
結核五才別死亡数
婚姻率統計図表 154
離婚率統計図表
肺炎、麻疹、百日咳発生数統計図表 155
性病職業別分類統計図表
主要死因別死亡者数統計図表 156
出生率統計図表 157
医療施設一覧
長崎地区優生保護委員会 158
長崎市医師会
三菱病院 159 |
|
|
文化スポーツ
長崎海洋気象台沿革他 163
長崎放送局 164
ラヂオ聴取者数調
発明協会長崎県支部165
長崎民友新聞社
長崎日々新聞社
夕刊ナガサキ
夕刊長崎タイムズ
佐世保時事新聞社長崎支社
新島原新聞社
時事通信社長崎市局
共同通信社長崎市局
毎日新聞社長崎市局
朝日新聞社長崎市局
西日本新聞社長崎市局
長崎市婦人団体名簿 166
長崎市青年団体名簿
長崎市文化団体名簿 167
日本国際連合協会長崎支部
長崎ユネスコ協力会
ユネスコに就いて 168
長崎YMCA 170
長崎ピエル・ロチ協会 171
長崎手工芸文化協会
長崎洋書家クラブ
音楽文化団体 172
短歌研修会
俳句研究会
茶道研究
華道
舞踊
長唄
清元 173
小唄
尺八
琴
映画
長崎市に於ける映画館
長崎県興行協会 |
|
|
○スポーツ
日本体育協会アマチュア規定
日本体育協会 174
同 傘下団体及競技人員調 175
各部支部所在一覧
公式野球場 176
陸上競技協会
第一回五勝八景訪問リレー
日本陸上競技連盟公認審判員
長崎地区陸上競技連盟
長崎市水泳連盟
県下水泳連盟 177
長崎市リクレーション振興会
長崎拳闘倶楽部
狩猟 178
長崎県猟友会一覧
禁猟区
銃猟禁止区域
史跡名勝天然記念物保存法適用鳥類 179
捕獲禁止鳥獣
釣猟
長崎県下囲碁有段者 180 |
|
|
宗教
○キリスト
フランシスコ・ザビエル小伝 181
日本二十六聖人殉教の旧跡西坂公園 184
天主公教大浦天主堂 187
天主公教聖職階級 188
長崎公教神学校 189
長崎市内の新教
キリスト教会一覧 190
○佛教
宗派別寺院教務所一覧
長崎市所在宗派別寺院一覧
佐世保市所在宗派別寺院一覧 191
大村市所在寺院一覧 192
諫早市所在宗派別寺院一覧
島原市所在宗派別寺院一覧
寺院統計
○神社
長崎市所在神社一覧 193
神社統計
神道教説教所統計 194
諏訪神社詳記 195
御大祭縦列序順
○神道
天理教 196
金光教
実行教
神理教
御岳教
黒住教
大社教
明治教 |
|
|
労働
○労働行政
長崎労働基準局
労働省婦人少年局長崎職員室
長崎労働基準監督署
監督を実施したる事業場数 198
労働者の申告件数及事業場数
保険給付状況統計
長崎労政事務所
県下各労政事務所 199
労働組合法改正の基本方針とその要領
労働組合法 200
長崎公共職業安定所 208
新規求職者統計 209
男女別各月指数比較表
常傭求職者の再来
男女別給食各月指数比較表
失業保険の請求件数 210
紹介就職充足率各月比較表
公共事業協同作業施設一覧 211
補導所一覧
長崎女子職業補導所
郡市別就業者調 212
産業別職業紹介並就業状況
長崎県地方労働委員会 214
○労働組合
長崎市全官公庁労働組合一覧 215
長崎地区労働組合の結成
長崎地区労働組合会議加盟組合名簿
県下各地区労働組合協議会 216
対馬地区労働組合協議会 217
島原地区労働組合協議会
諫早地区労働組合
大村地区労働組合 218
川棚地区労働組合
五島地区労働組合 219
長崎県日傭労働組合連合会一覧
其の外の労働組合連合団体名 220
団体交渉件数及参加人員
月別登録単位労働組合設立解散状況
企業整備に伴う人員解雇
単位労働組合組織状況 226
規模別労働争議発生状況 |
|
|
経済
終戦後より現在に至る金融状況 227
長崎市所在金融機関 228
長崎市本店所在銀行十八銀行
長崎県下金融機関店舗数及貸出高 231
長崎銀行協会会員銀行
九州無尽株式会社長崎支店
生命保険業
生命保険新規契約高
収入保険料金
金融機関別月別一般預金増加類別 232
同 預金月別残高表
同 貸出金月別残高
部門別通貨分布状況 234
長崎佐世保手形交換所加盟銀行
送金為替取扱高及手形交換高
長崎信用組合 235
長崎復興貯蓄会
日本銀行券発行状況
長崎通貨安定推進功労表彰者
長崎所在証券会社一覧
長崎税務署
新税と旧税の相違 236
諸税収納状態 238
日本税務協会長崎市部 239
九州北部税務代理士会長崎県支会
日本計理士会長崎計理士会員
福岡財務部長崎市部
昭和24年1月末県税徴収成績表 240
長崎市に於ける見做す無尽会社 |
|
|
商工業
福岡通商産業局長崎分室 241
同 資材割当表 242
福岡通商産業局長崎電力事務所 243
電力使用違反処置状況
福岡通商産業局長崎アルコール事務所
長崎地方経済調査庁
各業界調査概況 244
経済犯罪統計 245
ヤミ価格調 246
長崎商工会議所
仝 役員及部会長名簿
仝 常議員名簿 247
長崎県経営者協会 248
仝 各地区会員名簿 250
長崎県中小企業連盟 251
商工業協同組合法と中小企業等協同組合違法の相違点 252
中小企業の概況 254
商工業協同組合 255
商業協同組合所在名称一覧 256
工業協同組合所在名称一覧 258
県下業種別会社数及従業員数 261
長崎市所在株式会社業種別名簿 262
長崎市所在有限会社業種別名簿 268
長崎市所在合資会社業種別名簿 270
長崎市所在合名会社業種別名簿 272
長崎市の商店街 273
長崎市の華僑
中華民国留日長崎華僑連合会
長崎木材市場
西日本重工業株式会社長崎精機製作所 247
三菱製鋼株式会社長崎製鋼所 278
三菱電機株式会社長崎製作所 280
川南工業株式会社長崎支店 281 |
|
|
貿易
長崎貿易界の足跡と見透 283
輸出実績表 284
長崎通商事務所
門司税関長崎市署
門司動植物検疫所長崎出張所 285
長崎検疫所
長崎県貿易会
長崎県貿易会役員名簿
長崎県貿易関係業者 287
鉱工品貿易公団長崎出張所 291 |
|
|
産業 |
|
|
○農業
農業概況 293
農林省長崎作物報告事務所
農林統計調査概況 294
作物報告事務所出張所一覧 295
米及甘藷生産高
麦類及春植馬鈴薯生産高 296
農作物生産費
耕地面積
農家戸数人口
主要食糧供出状況 297
産麦郡市別割当
農産物収穫高
長崎市農業委員会
農業協同組合概況
農業協同組合連動会一覧 298
農業協同組合
開拓農業協同組合 299
養蚕農業協同組合
畜産農業協同組合
肥料配給公団長崎県支所
長崎市農業調整委員会 300
農地委員会
県農地委員 301
市別農地委員
各町村農地委員会長 303
開拓事業の概況 303
食料品工業概況 304
長崎食糧事務所 305
戦時食糧を回顧しつつ今日の供出より配給までの道程 306
主要食糧の配給経路図 307
食糧事務所指定工場並び検査数量 308
主要食糧検査品目
いも粉の供出配給経路図 310
切干の供出配給経路図
食糧配給公団長崎県
仝 支局支所 312
長崎市内の配給所と受持区域表
日別業態別配給実績 313
茶業五ケ年計画 314
製茶生産額統計表 |
|
|
○養蚕
養蚕業概況
養蚕生産額統計表 315
○畜産
畜産業概況
畜産増殖五ケ年計画
牛馬頭数統計表 316
家兎養鶏飼育者数及頭羽数
法定家畜伝染病 317
資料配給公団長崎県支所
仝 指定販売店
長崎市所在獣医師 318
長崎市所在装蹄師
長崎県競走馬所有者
○林産
林業概況 319
長崎営林署
仝 業務実績統計 320
国有林産物払下方法
国有林払下に関して
松喰虫の被害状況
未墾地買収並国有林及旧軍用地移管面積 321
公私有林伐採面積及数量
公私有林副産物
農林省長崎木炭事務所
営林野面積及び石数 322
長崎市森林組合
長崎県森林組合連合会
日本専売公社長崎市局 323
塩について 324
いよう脳について
たばこ耕作概況
たばこ販売概況 325
専売取締概要
たばこ専売月別犯罪目別状況調
農林省長崎資材調整事務所 326
仝 諮問委員会
農林水産関係資材割当発券総括表
特殊林作業 328 |
|
|
○鉱業
石炭業概況 329
九州石炭鉱業連盟長崎支部
石炭年次生産状況 330
長崎県炭鉱(石炭)一覧
伊王島炭鉱
岩谷炭鉱
高島ニ子坑
崎戸炭鉱 331
端島炭鉱
江迎炭鉱
御厨炭鉱
平田山炭鉱
松浦炭鉱
新本山炭鉱 332
香焼炭鉱
大志佐炭鉱
里山炭鉱
飛島炭鉱
中島鉱業本部
福島炭鉱
中島江口炭鉱 333
神林炭鉱
徳義炭鉱
土肥ノ浦炭鉱
潜龍炭鉱
矢岳炭鉱
福井炭鉱
深江炭鉱
鯛ノ鼻炭鉱 334
長松炭鉱
芳野浦炭鉱
三船炭鉱
竹松炭鉱
名切炭鉱
日進炭鉱
石獄炭鉱
北松の新鉱“飛島” 335
石炭統制撤廃による業界の動向
炭鉱別出炭状況及労務者数統計 336
○稼業鉱山一覧
金属鉱山 337
非金属鉱山(石炭を除く)
亜鉛鉱山 |
|
|
○水産
水産業概況 338
漁獲物の供給実績
水産加工業概況
真珠養殖業
製氷業の概況
社団法人長崎市水産振興協会 339
長崎港を根拠とする漁業の大勢 241
漁業別鮮魚水揚高
仕向先別出荷実績表 342
鮮魚出棺月別実績表
鮮魚貨車使用実績表 343
鮮魚介水揚状況推移表
漁業別水揚高表 344
品種別水揚数量
出荷地別数量
漁業経営者数 345
種類別漁獲量
販売用水産加工品量
漁業協同組合設立状況 346
長崎県漁業協同組合連合会
長崎市所在漁業協同組合一覧
長崎市所在業種別漁業協同組合一覧
長崎魚市場沿革
長崎魚市組合
長崎県立水産学校
石油配給公団長崎出張所
長崎市所在製氷業者
長崎県水産試験場
仝 職員及事務分掌 348
各所在地及敷地
指導船及委託試験船
試験地
事業計画及内容 |
|
|
国際文化都市建設
○原爆一閃
人員の被害状況 353
主要建築物被害状況調
応援救護対出動状況調 354
原子爆弾の威力 355
国際文化都市建設法 359
長崎国際文化都市建設法讃否投票状況
長崎国際文化都市發足宣言
ユネスコ協會の平和宣言 358
長崎民事部長メッセージ
○長崎国際文化都市建設要綱
建設の基本理念
建設の指導的構想
長崎国際文化都市試案 360
教育都市建設計画
厚生都市建設計画 361
産業貿易都市建設計画 362
国際観光都市建設計画 363
国際文化都市への構想石田壽(裁判長)
仝 青山武雄(YMCA主事)
仝 小野京子(友の会リーダー)
仝 宇田道隆(海洋気象台長) 364
仝 山下繁造(県専門委員)
仝 秋山俊一郎(大洋漁業長崎支社長)
仝 大畑文七(前経専校長)
長崎在住各国人の期待 365
サーリー・バーグハイム嬢(民事部長令嬢)
アンドレ・ブクリー(フランス代理領事)
羅集誼(中國代表長崎僑務所長)
アントニオ・ミロハナ(聖母の騎士園長)
アルフ・ペーターセン(丁抹) |
|
|
○水道
長崎市水道概況 366
水道数一覧
市内水源池容水量
○電力
電力概況 367
九州配電株式会社長崎支店
送電経路
電力各種状況 368
九州地区火力発電所復旧状況
九州地区発電実績
電力制限方法 369
500kW以上大口電力使用量 370
長崎電力協議会役員名簿
電気工事業の現況 371
小口電力業樹別新増受電申込並に認可件数及平均kW明細表
○ガス
ガス事業概況 373
西部瓦斯株式会社長崎支店
ガス生産高 374 |
|
|
○住宅
長崎市、佐世保市の戦災復興都市計画事業概況
住宅建設の促進
市営住宅一覧 375
居住住宅数、居住人員、畳数 376
居住住宅の所有関係別、建築の時期別及び戦後建築住宅数所有関係別割合
○土木
長崎土木出張所 377
主要道路一覧
道路延長並に幅員 378
重要橋梁一覧
長崎兼工務所一覧 379
長崎県建設工業協同組合
長崎県長崎復興工事事務所 |
|
|
観光
西坂公園 381
出島
唐人屋敷 382
国際墓地
福済寺
悟真寺
春徳寺
中島聖堂 383
シーボルト宅跡
大浦天主堂
浦上天主堂
唐八景 384
崇福寺
諏訪神社
諏訪公園
眼鏡橋
中島川架設石橋一覧
丸山
長崎県観光連合会 385 |
|
|
史跡名勝天然記念物
国宝建造物
国宝宝物類
重要美術品 |
|
|
長崎の行事
ハタ揚げ
ペーロン 386
盆祭り
おくんち
各町さかぼこ詳解 |
|
|
長崎の土語 391
長崎の方言
長崎の童話と民謡 393
長崎の歌
長崎の史話 395
長崎の絵踏
じやがたらお春 |
|
|
長崎の名産 399
鼈甲細工
洗粉
口砂香、寒菊、一口香
トマトサージン
カマボコ
カステーラ
カラスミ 400
煙草
長崎の郷土玩具 |
|
|
長崎市内旅客総括表 401
長崎市所在旅館一覧
県下旅館一覧 402
長崎駅構内 日本食堂 404
長崎駅列車発着時刻表 |
|
|
特集雲仙
国立公園指定15周年を迎えた雲仙の概観 404
楽園「雲仙」
春の雲仙
夏の雲仙
秋の雲仙
冬の雲仙
雲仙の温泉 405
雲仙の名勝地
名勝案内
普賢岳
仁田峠と野岳
絹笠山 406
白雲池と雲仙キャンプ
高岩山
田代原
九千部岳
吾妻岳
諏訪池方面
つつじ
紅葉
霧氷
雲仙の諸施設
公園設備
公共施設 407
雲仙の旅館
新湯温泉場
古湯温泉場
小地獄温泉場
雲仙温泉中心観光日程
主要ハイキングコース |
|
|
|
|
|
○索引
○編集後記
○国際文化都市長崎市地番入地図 |
|
|
|
|