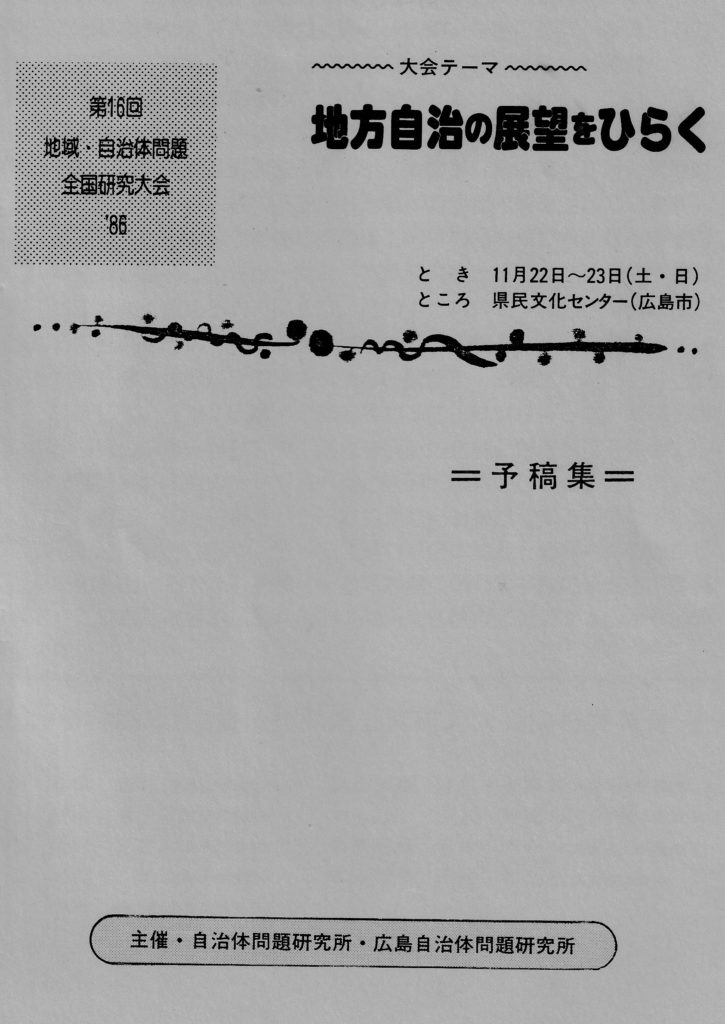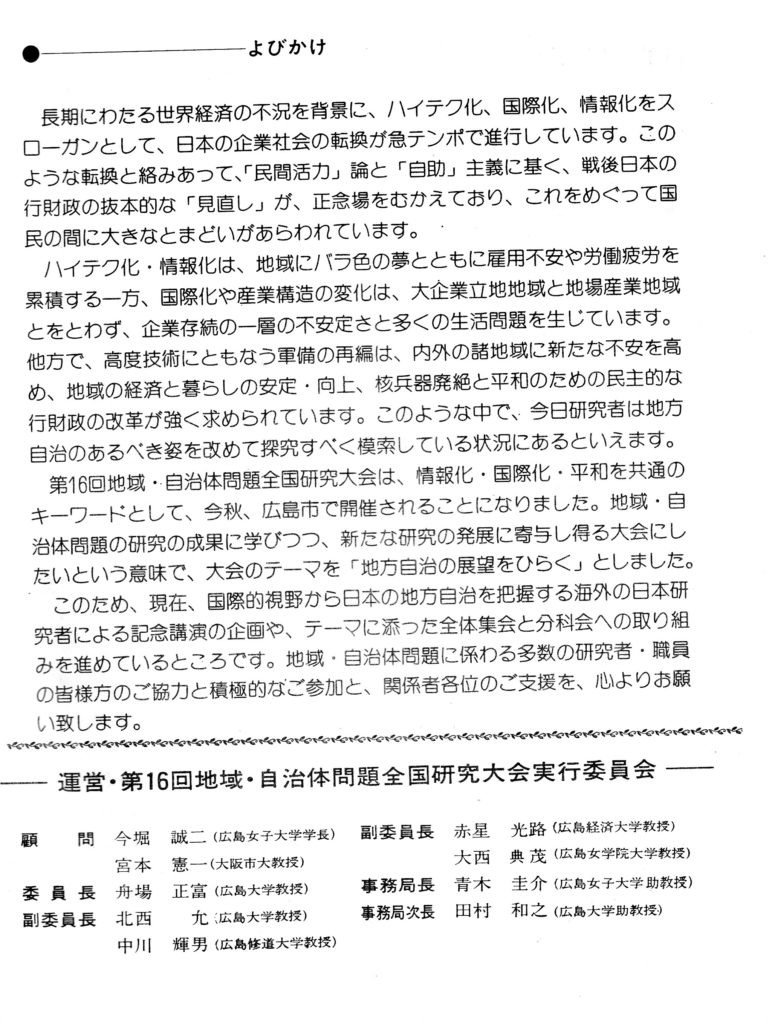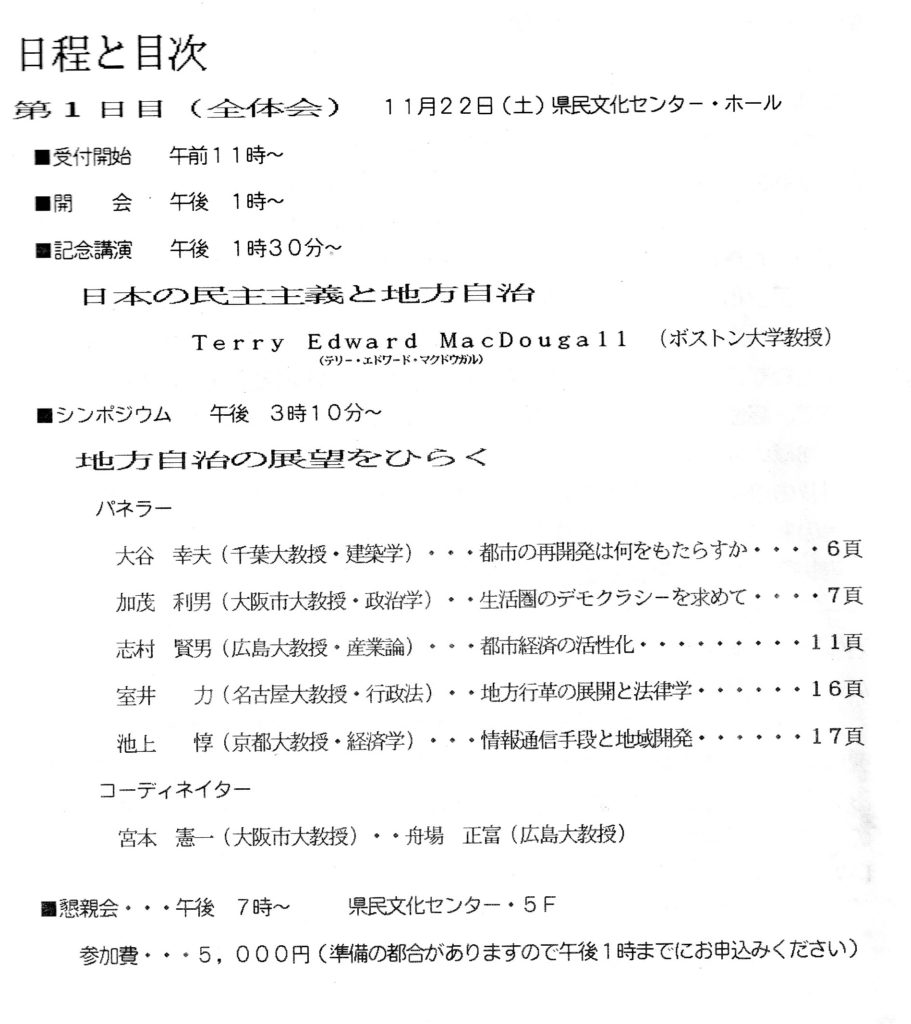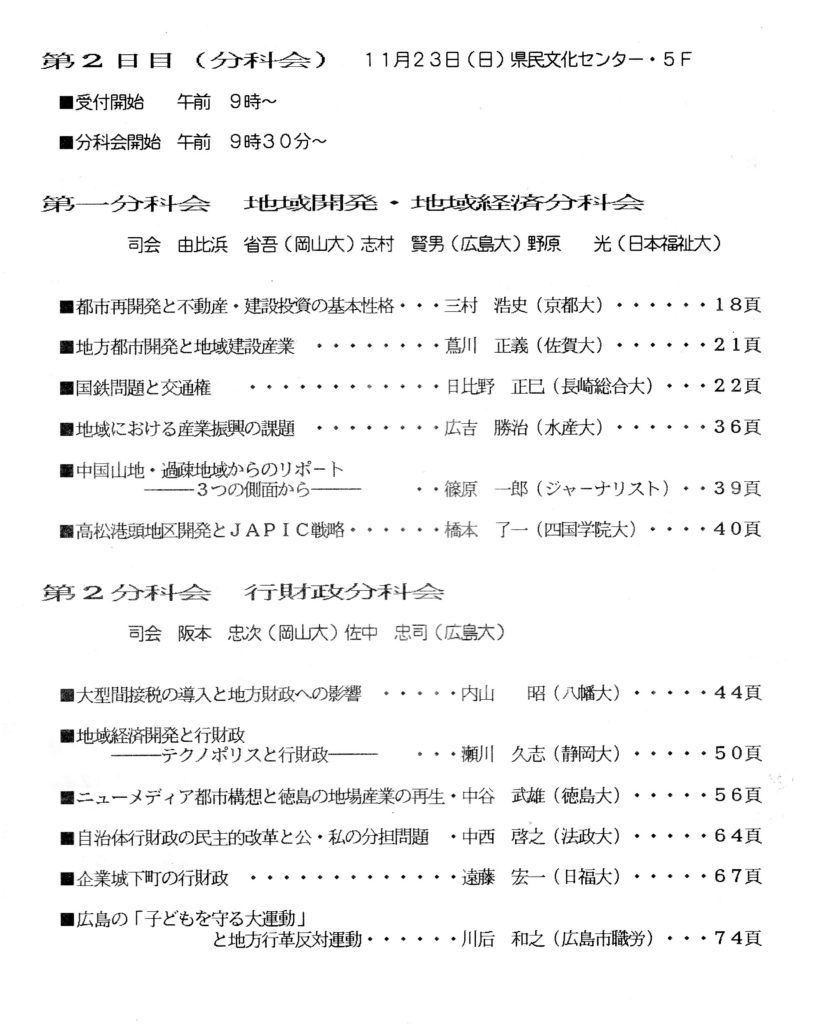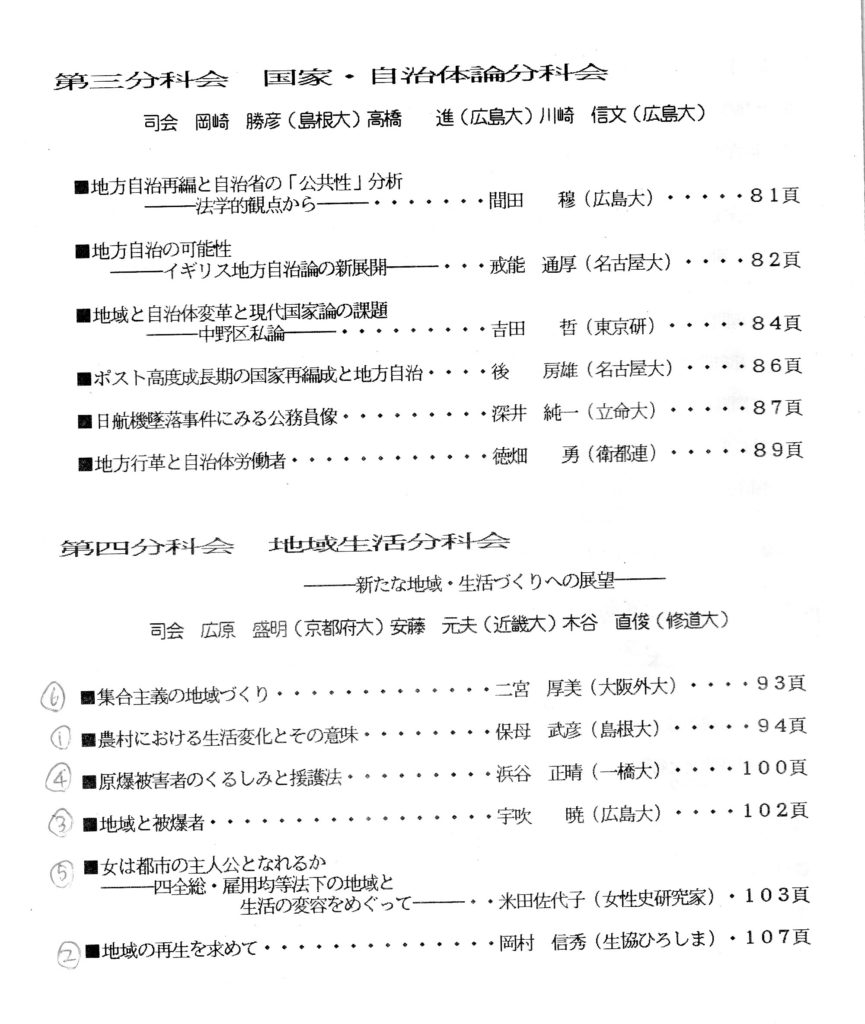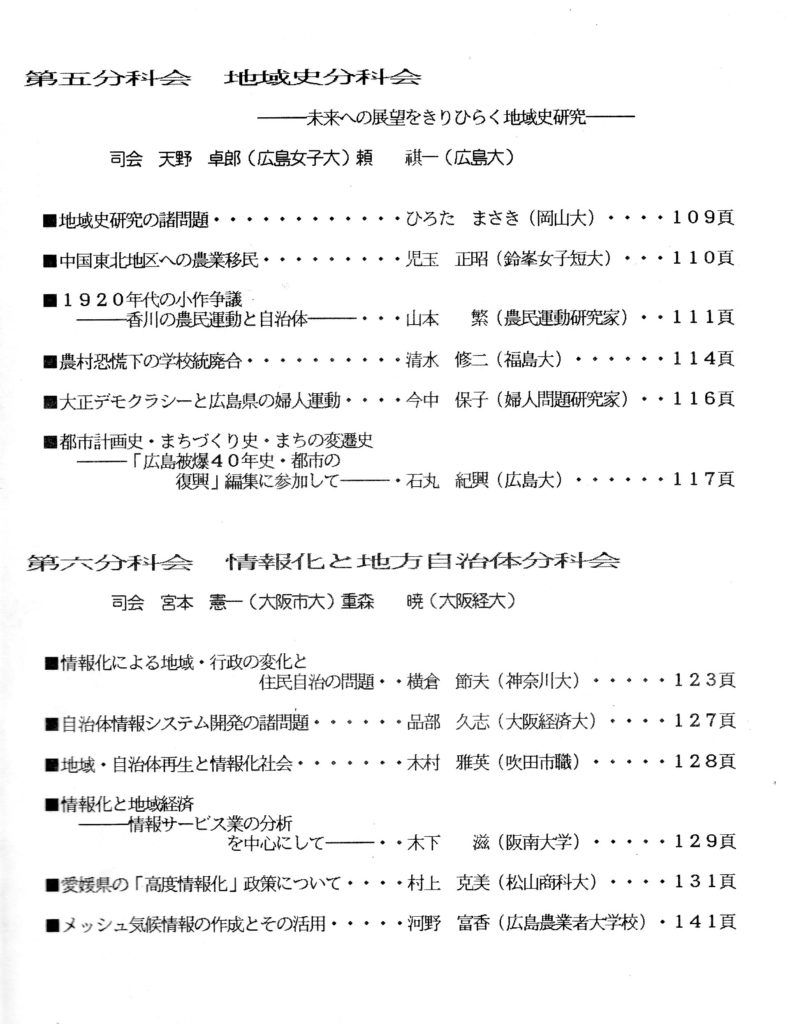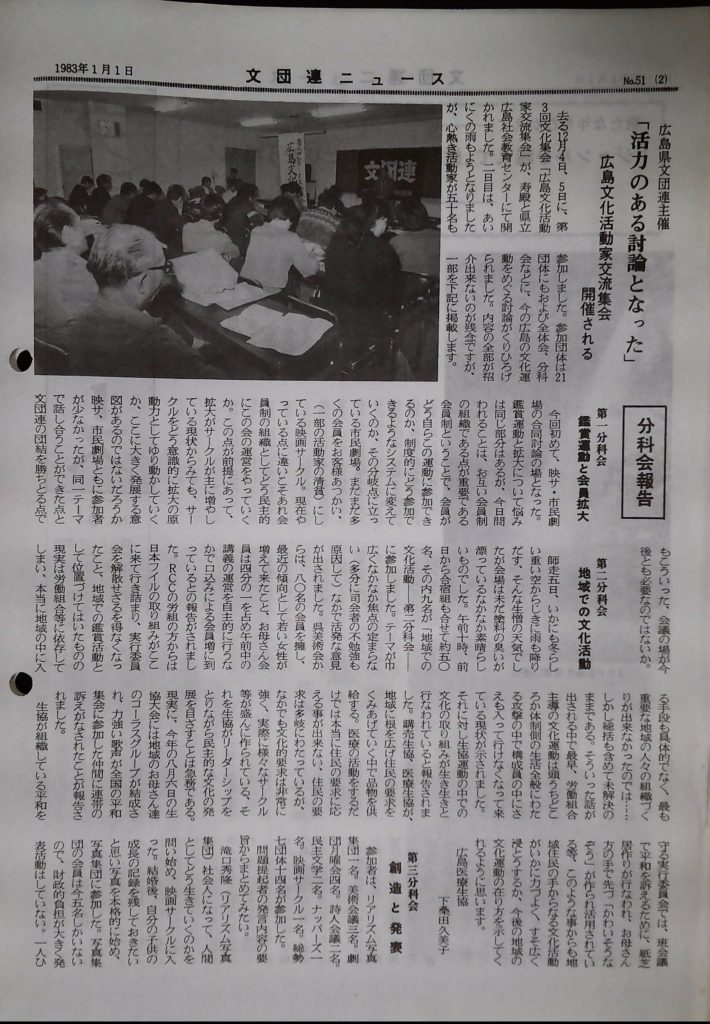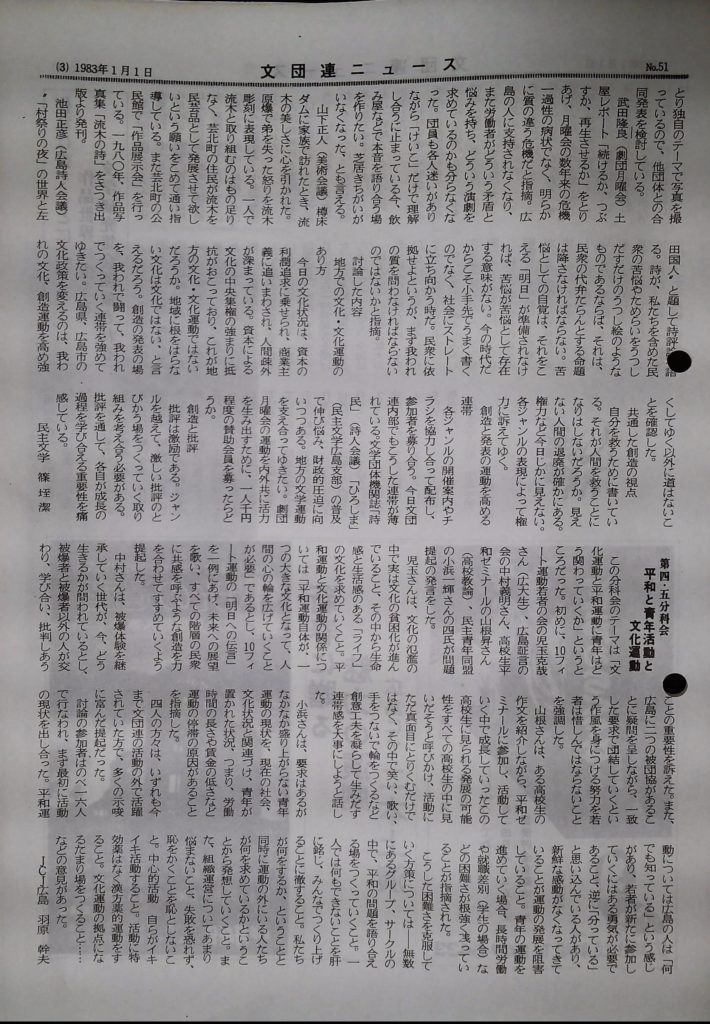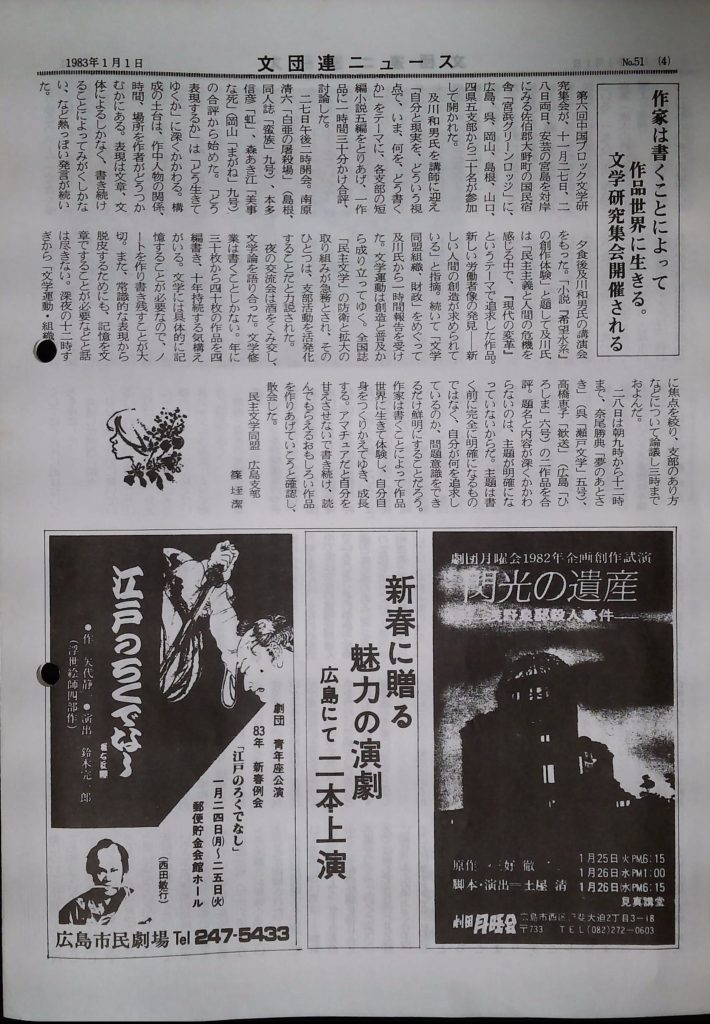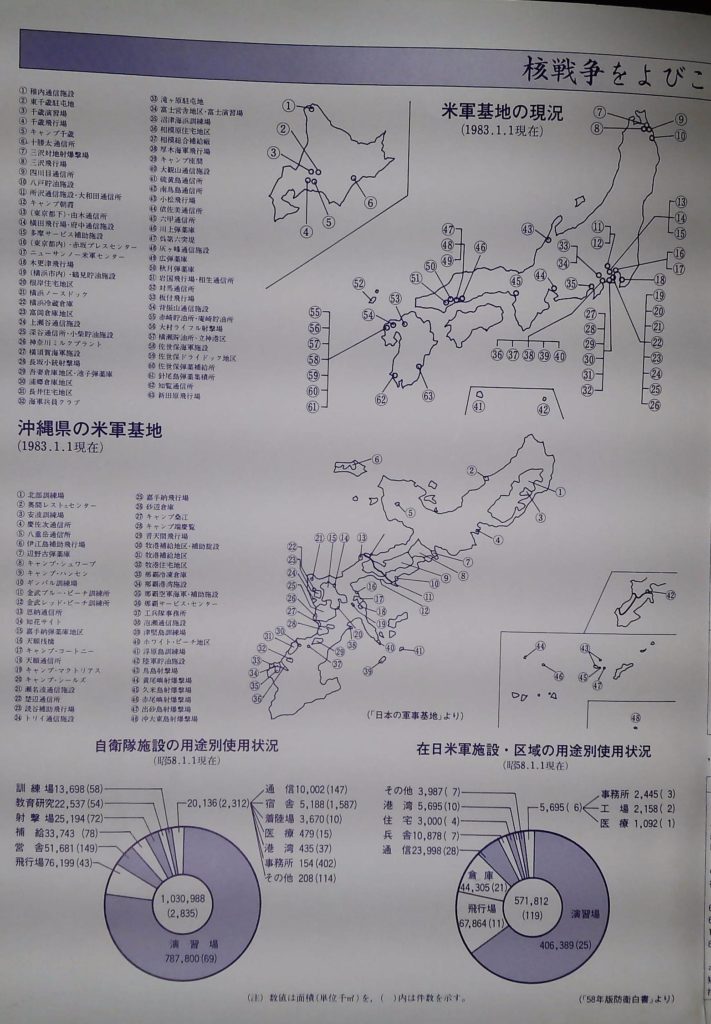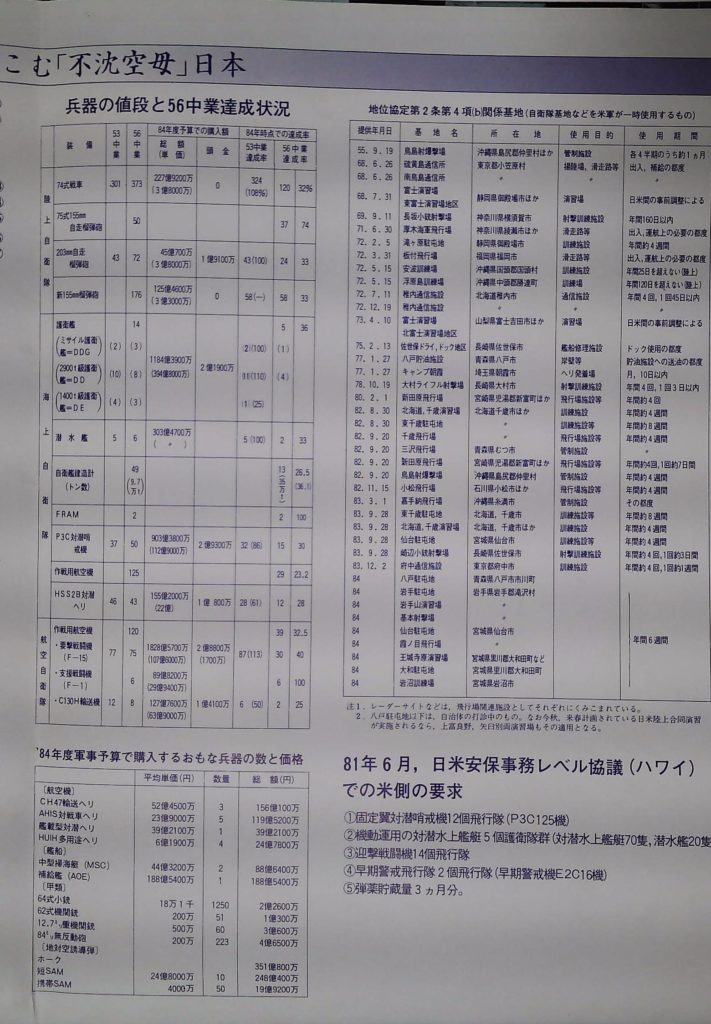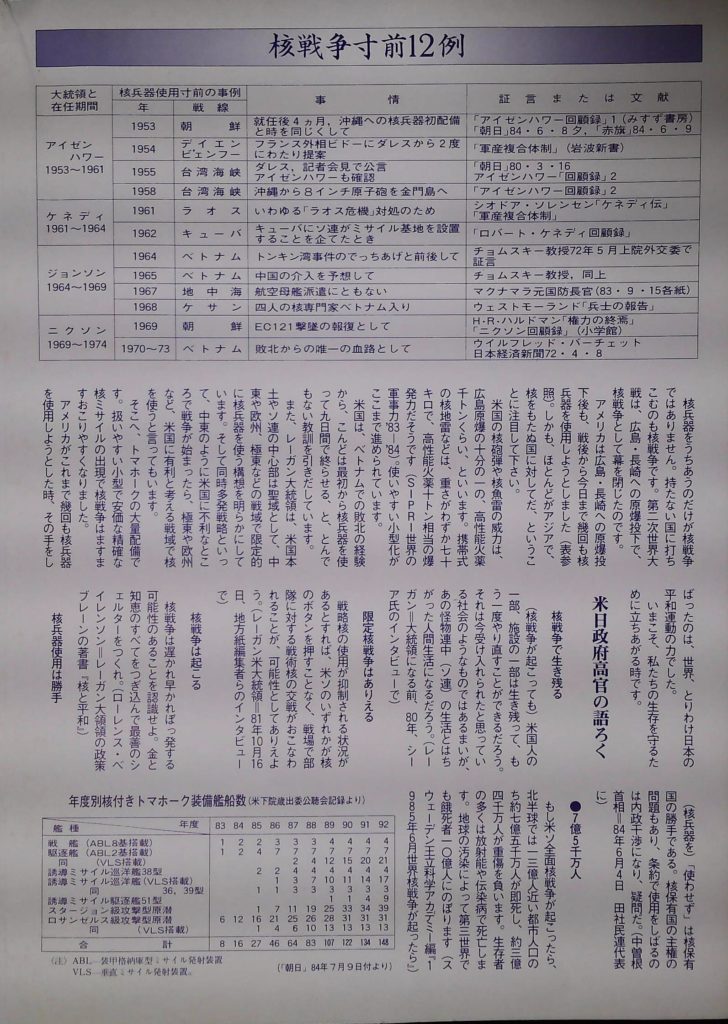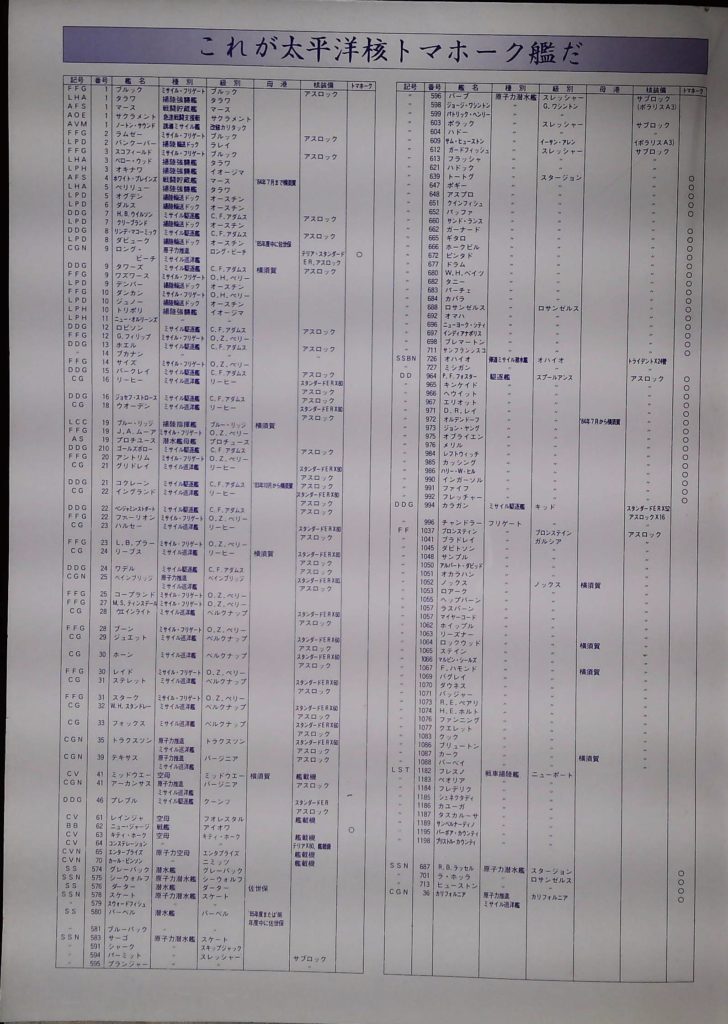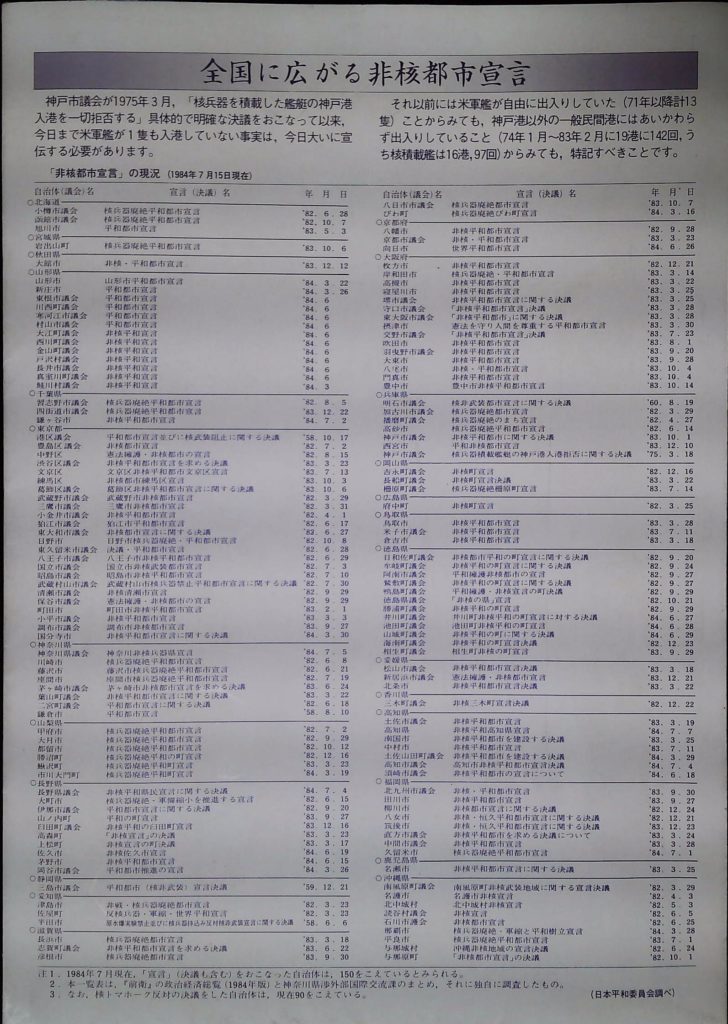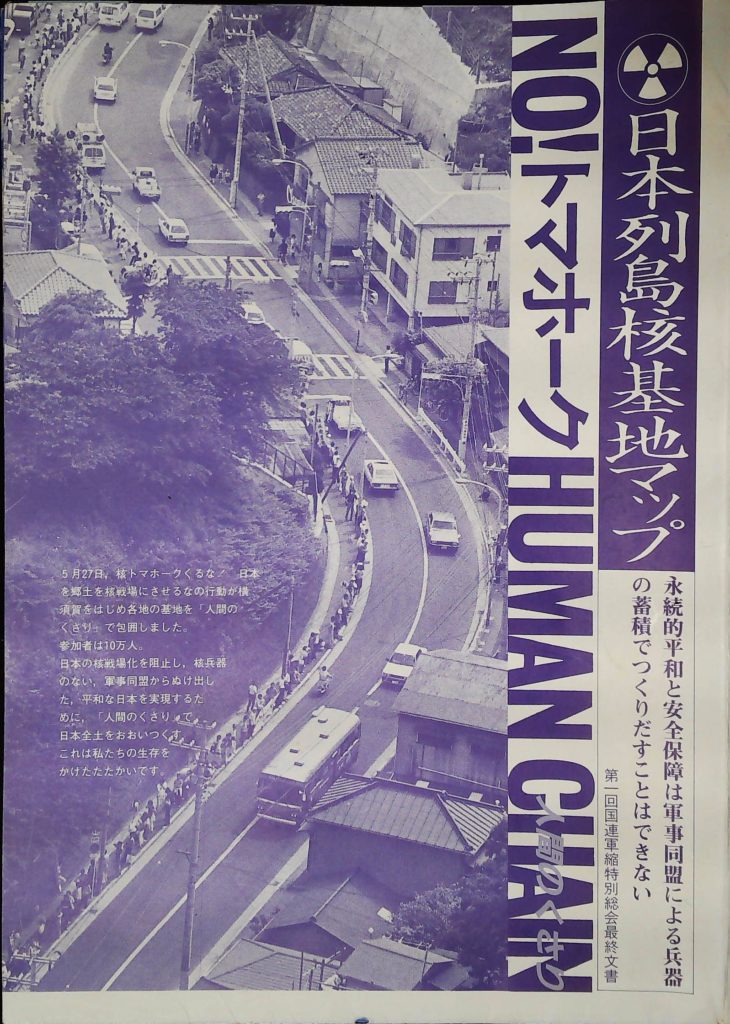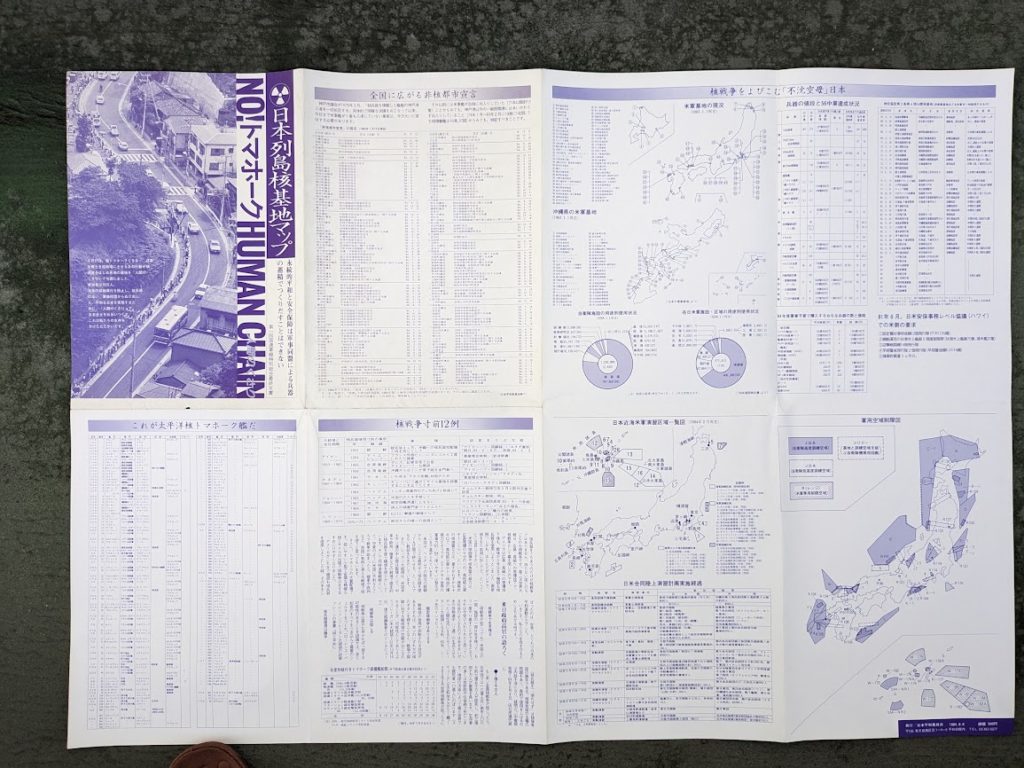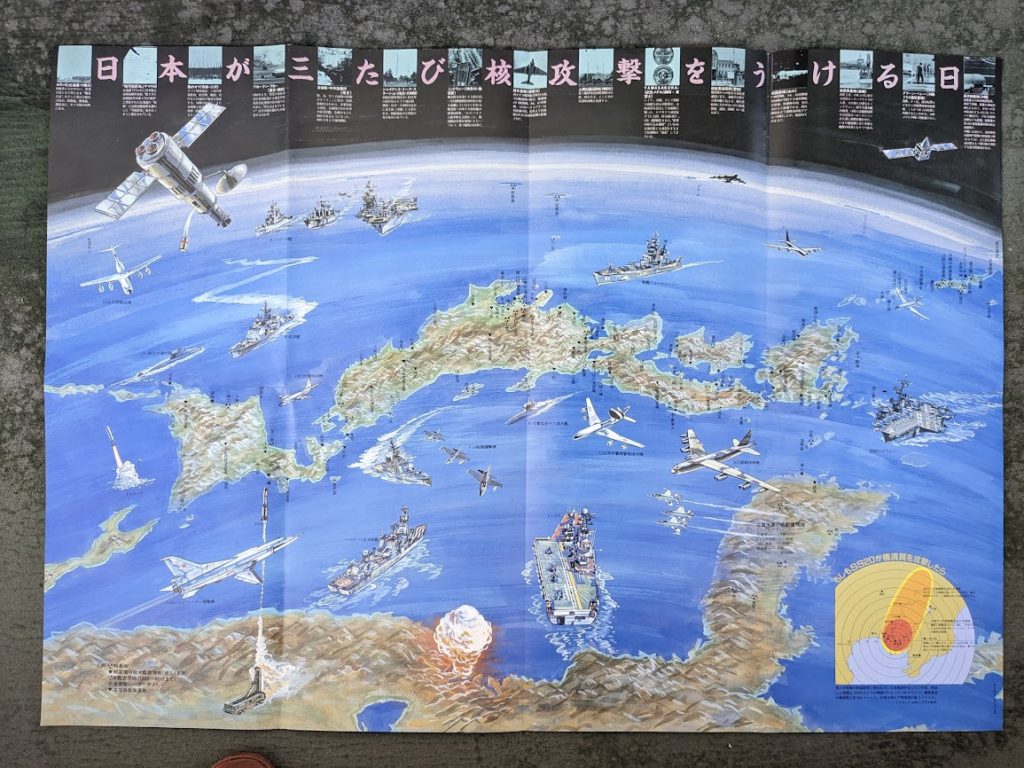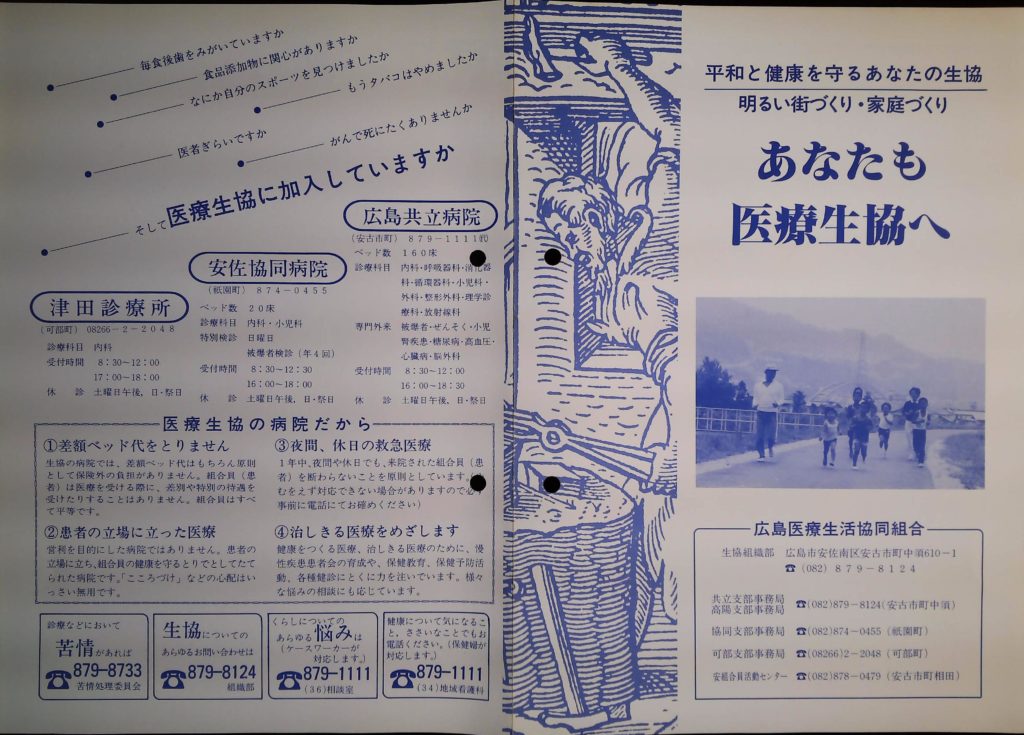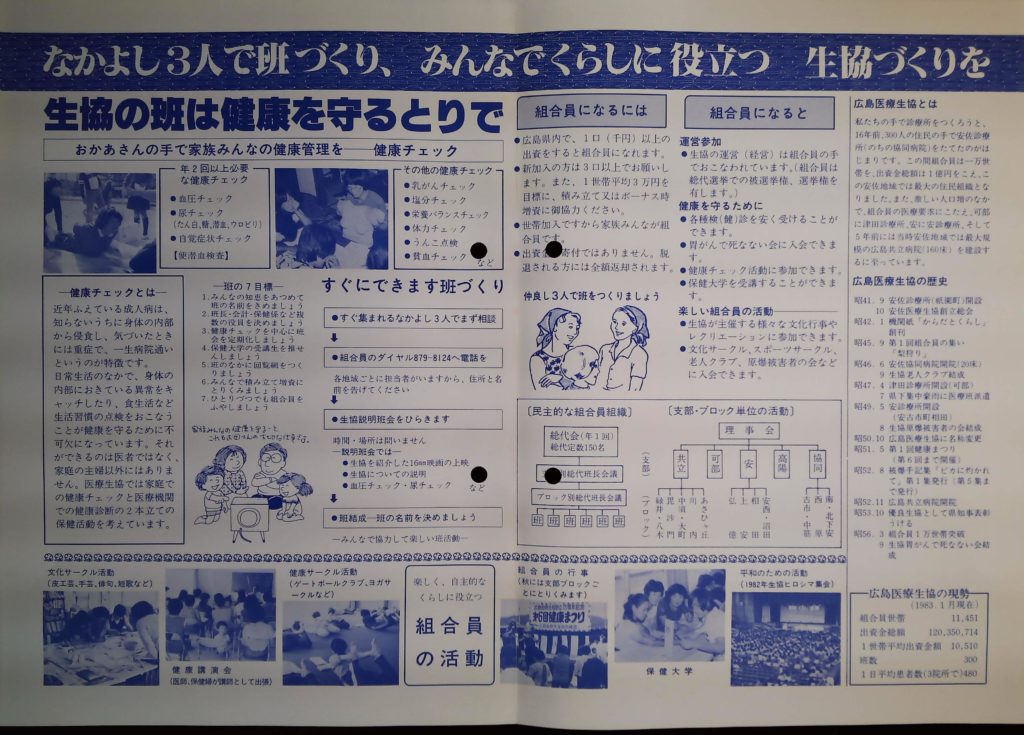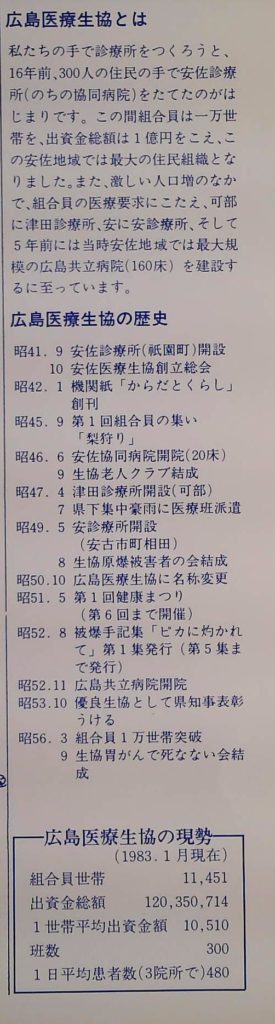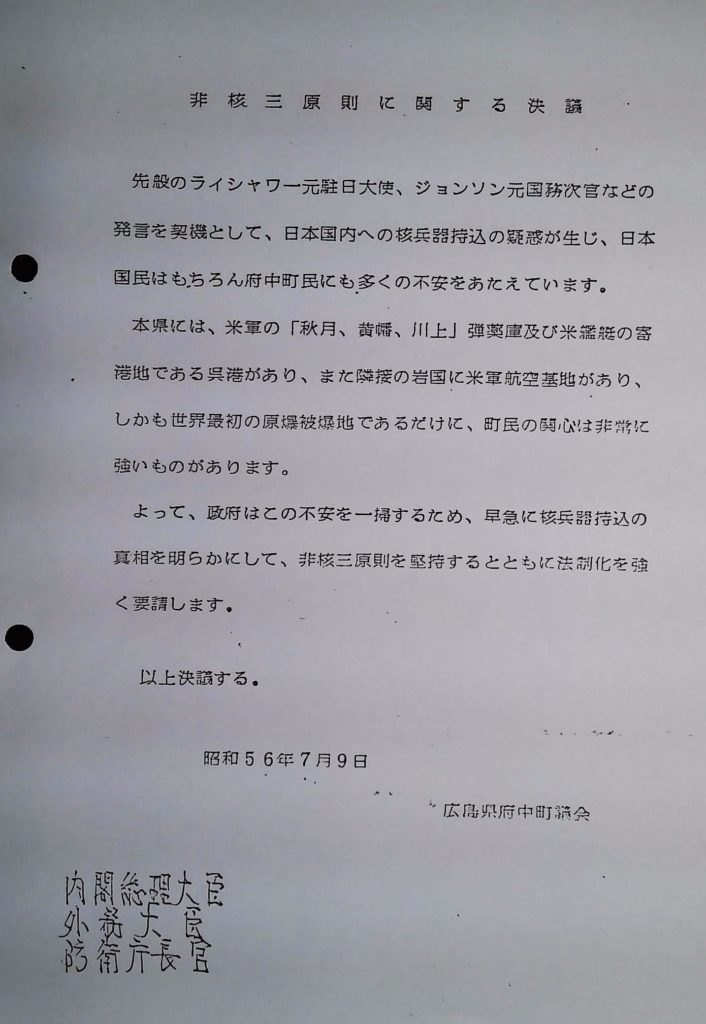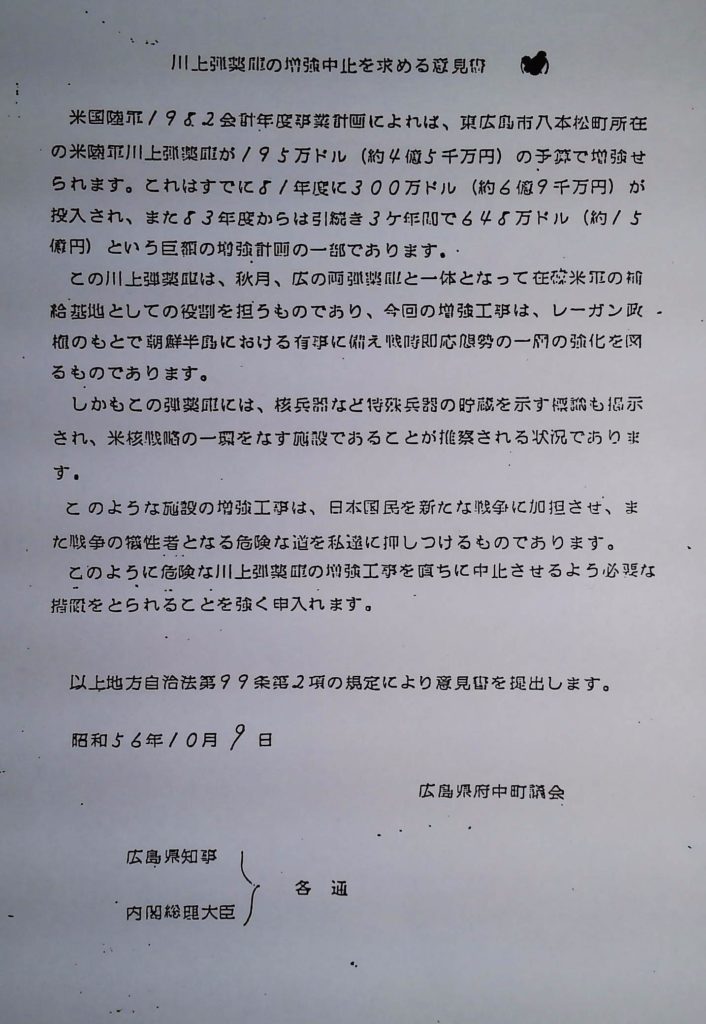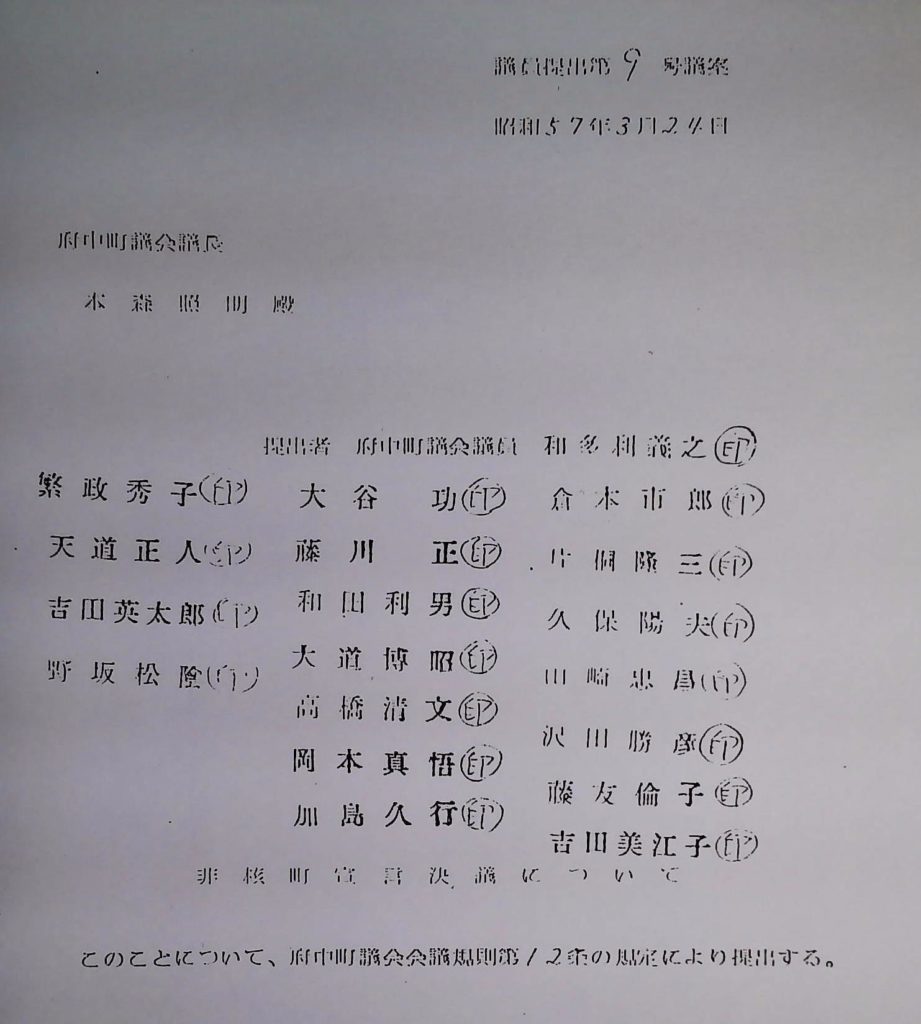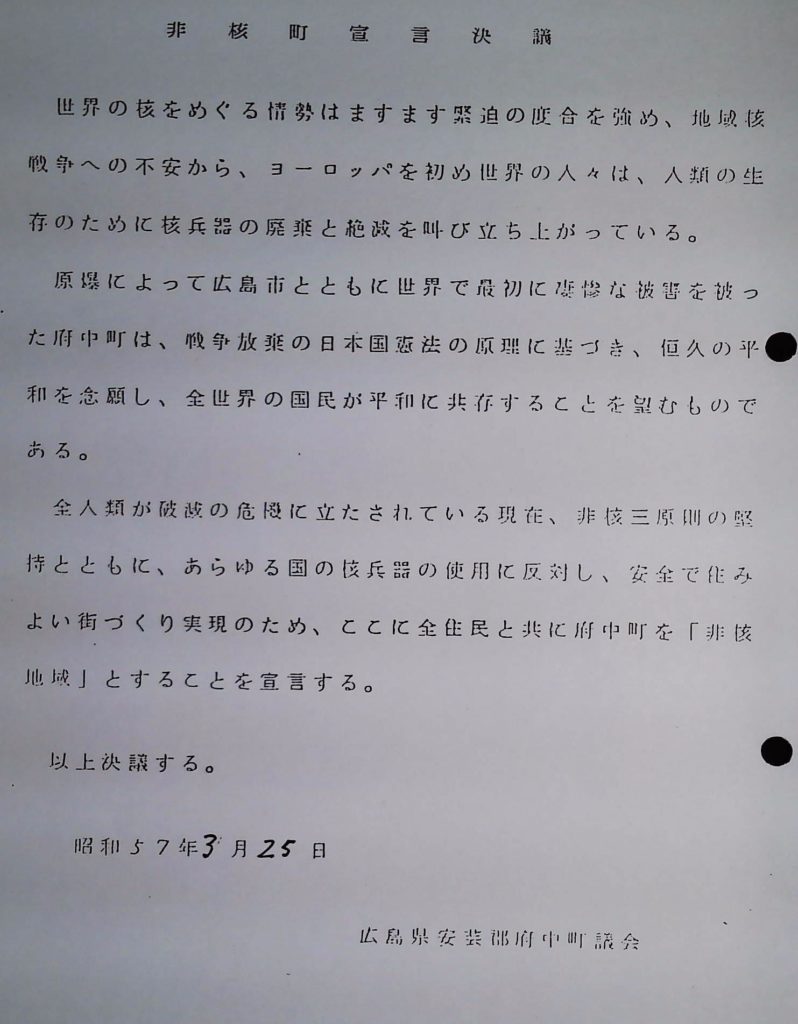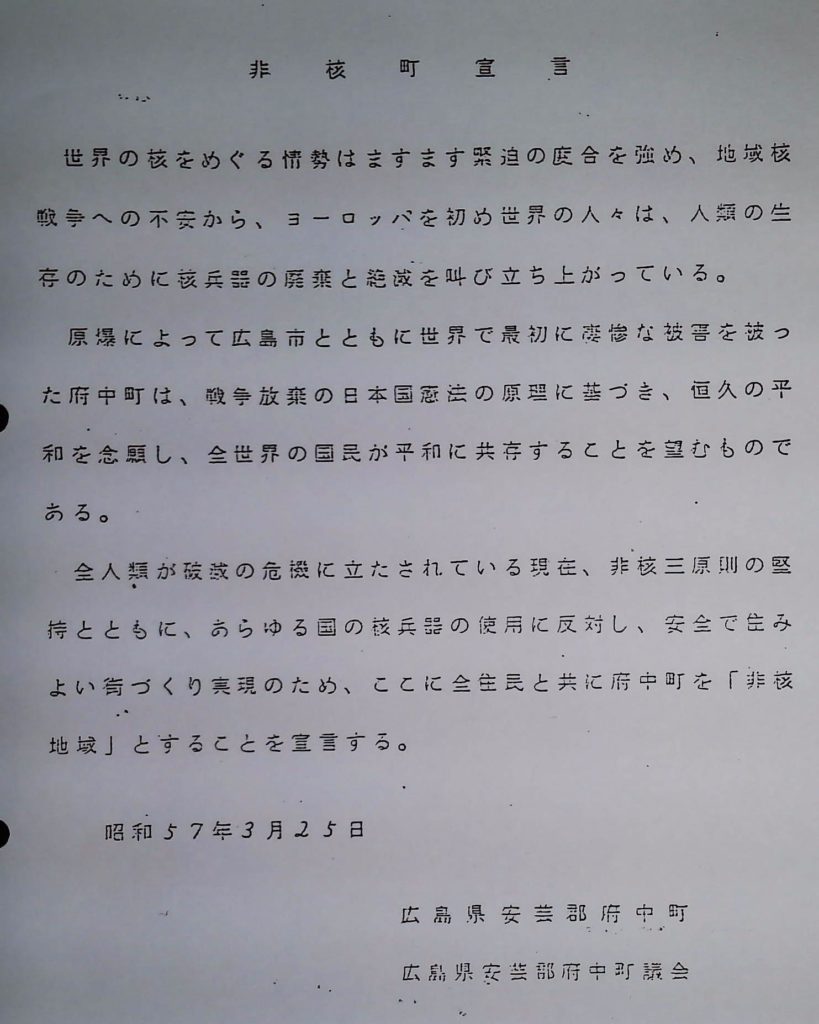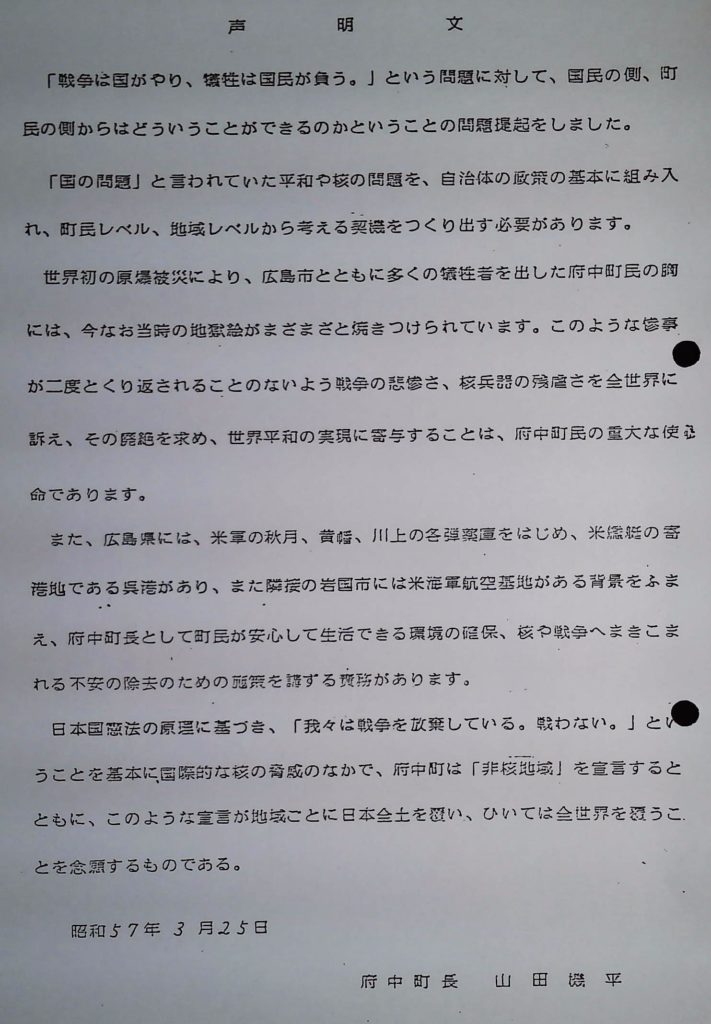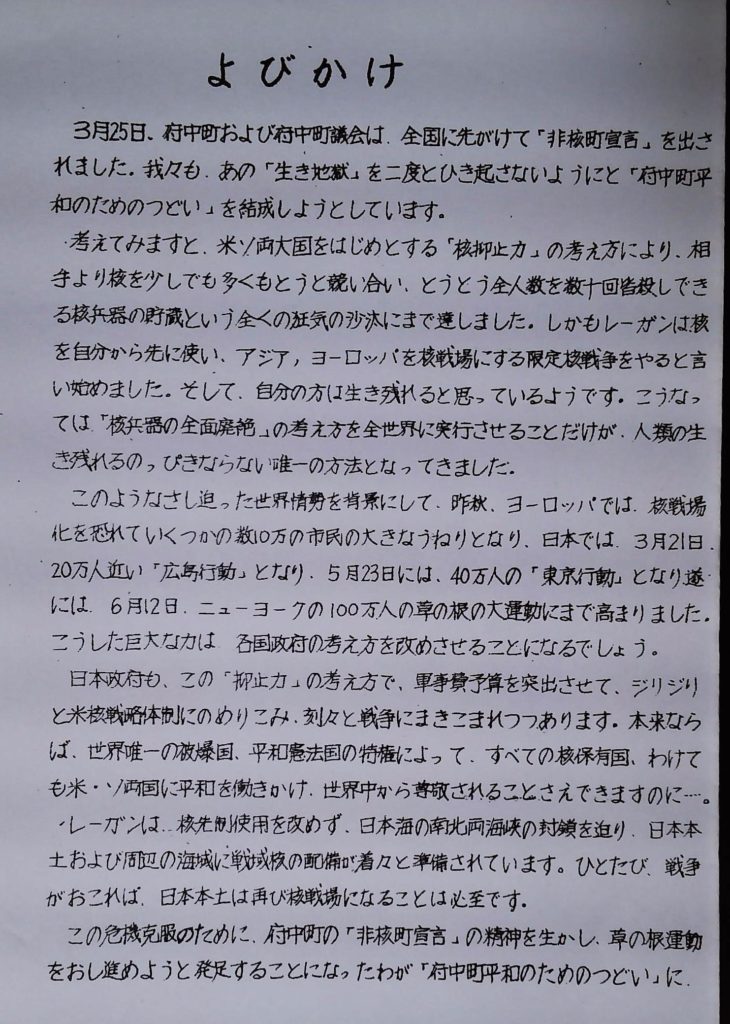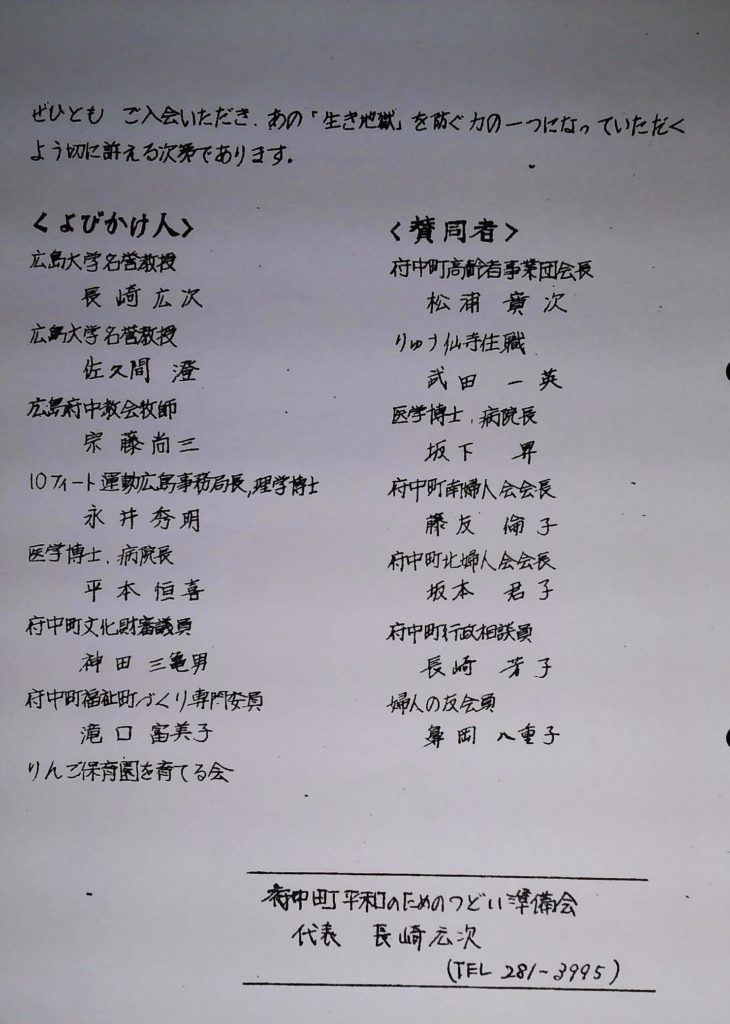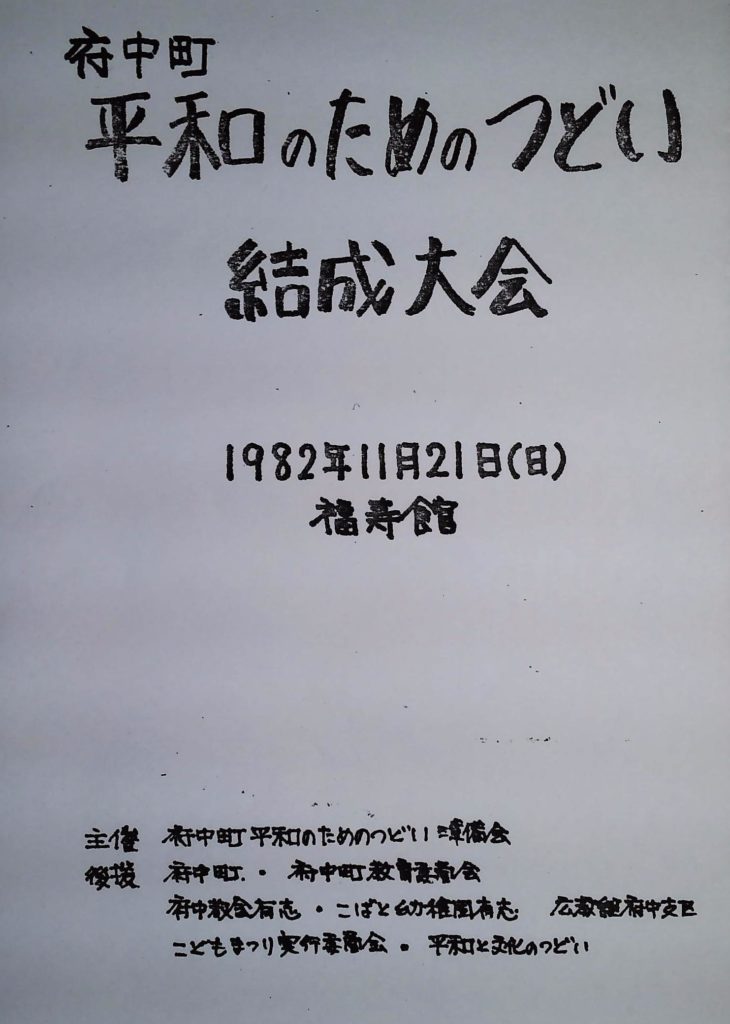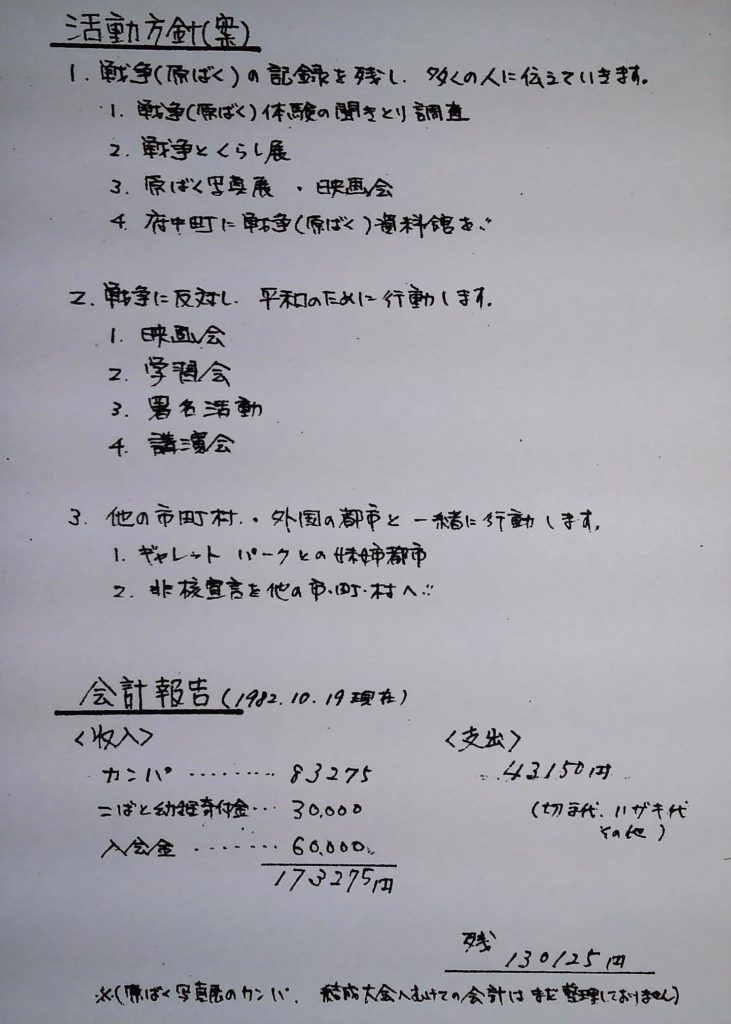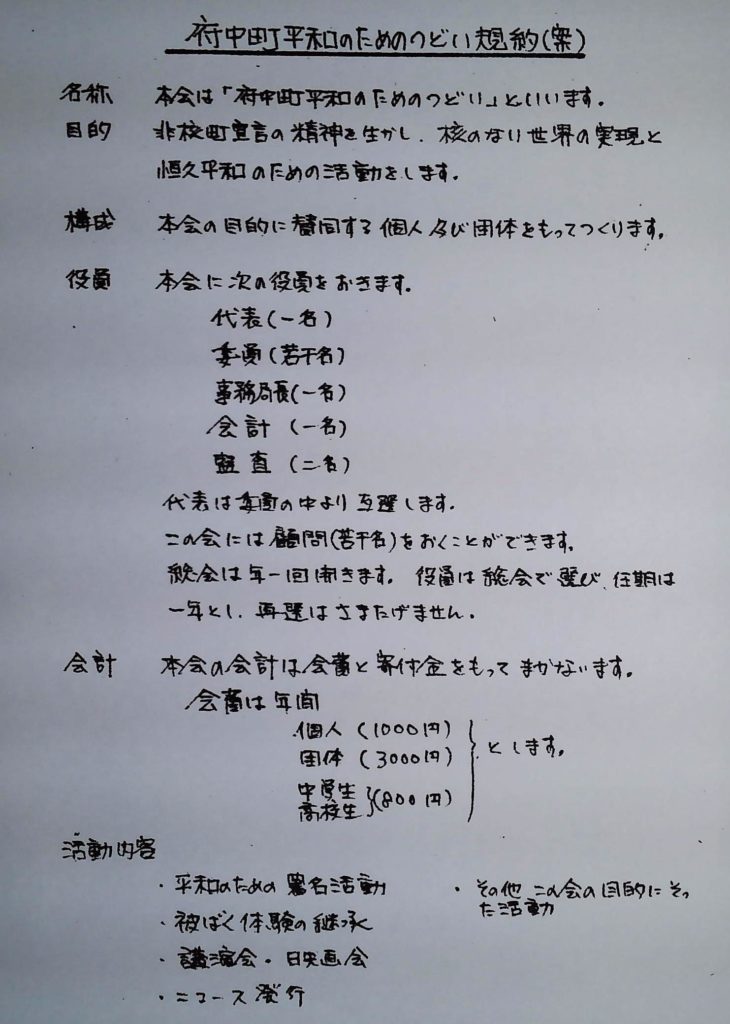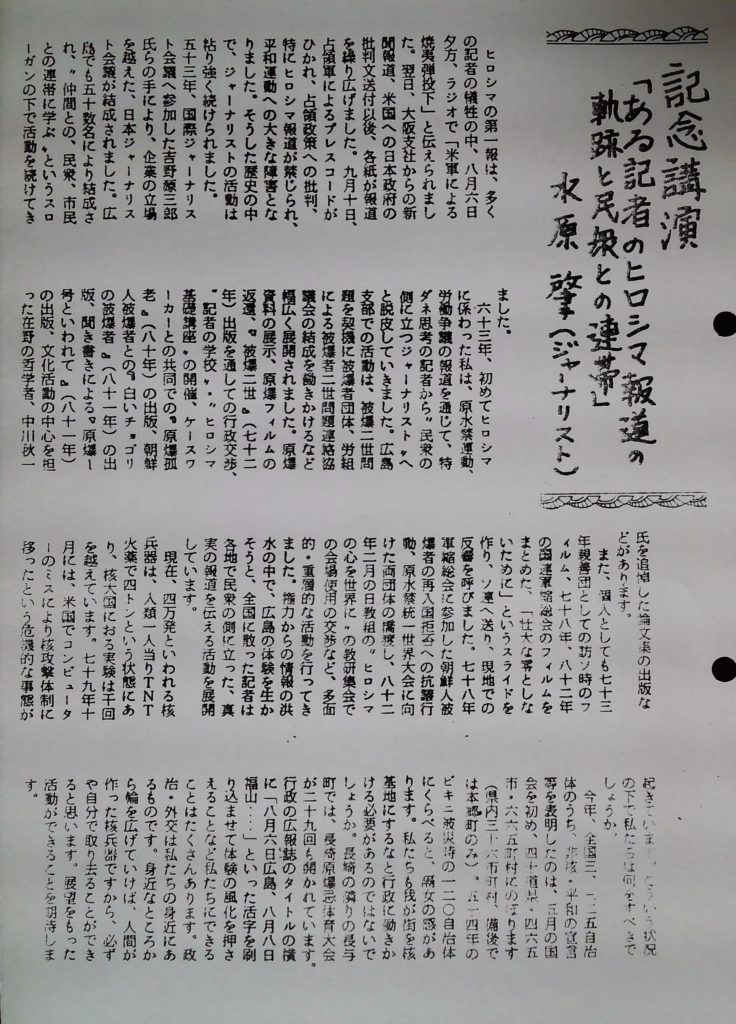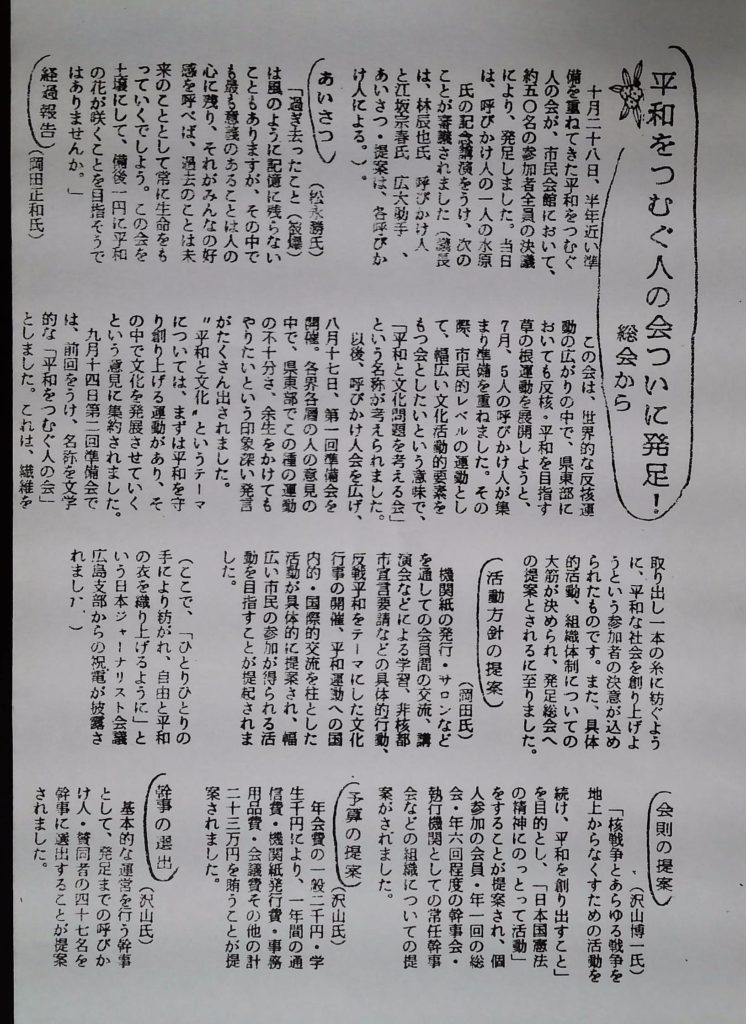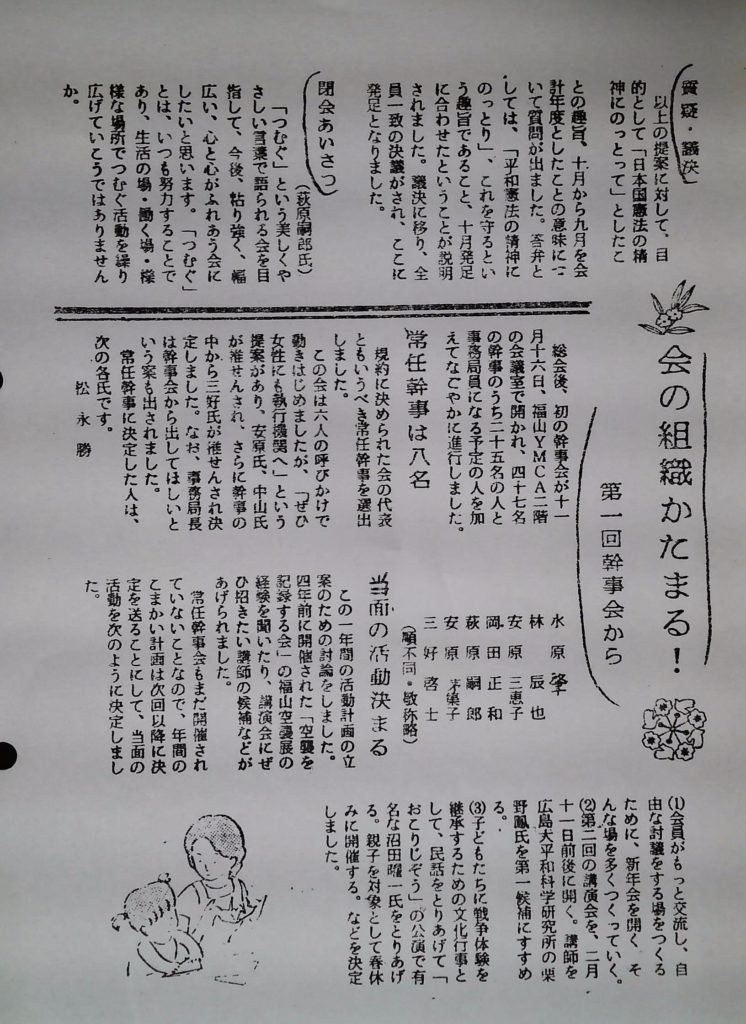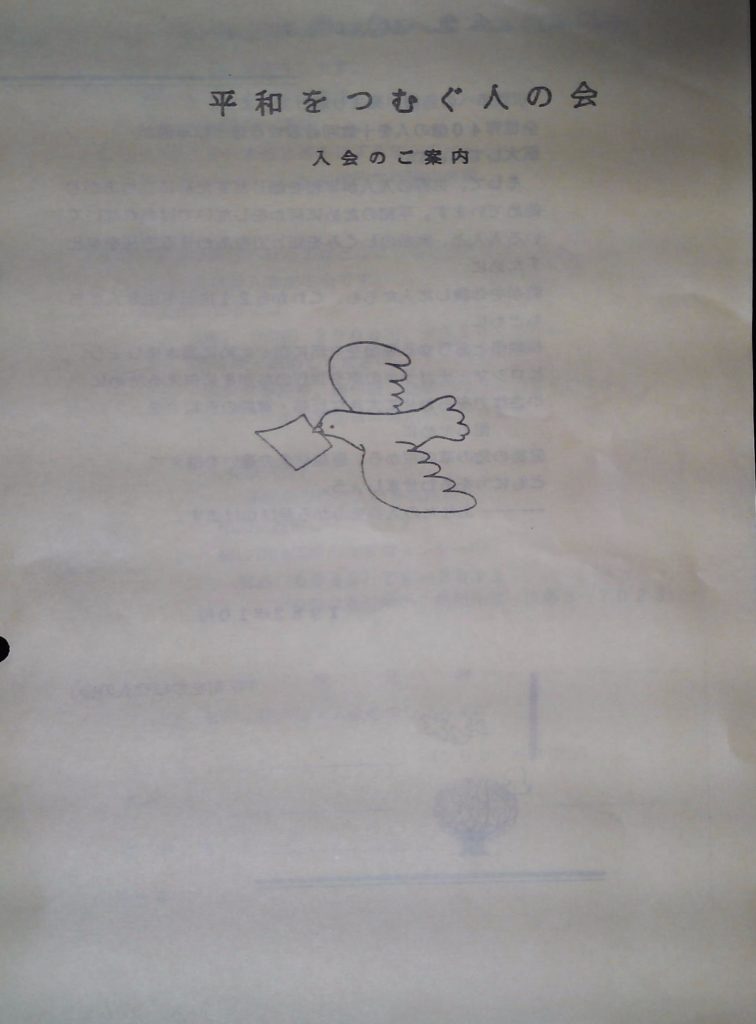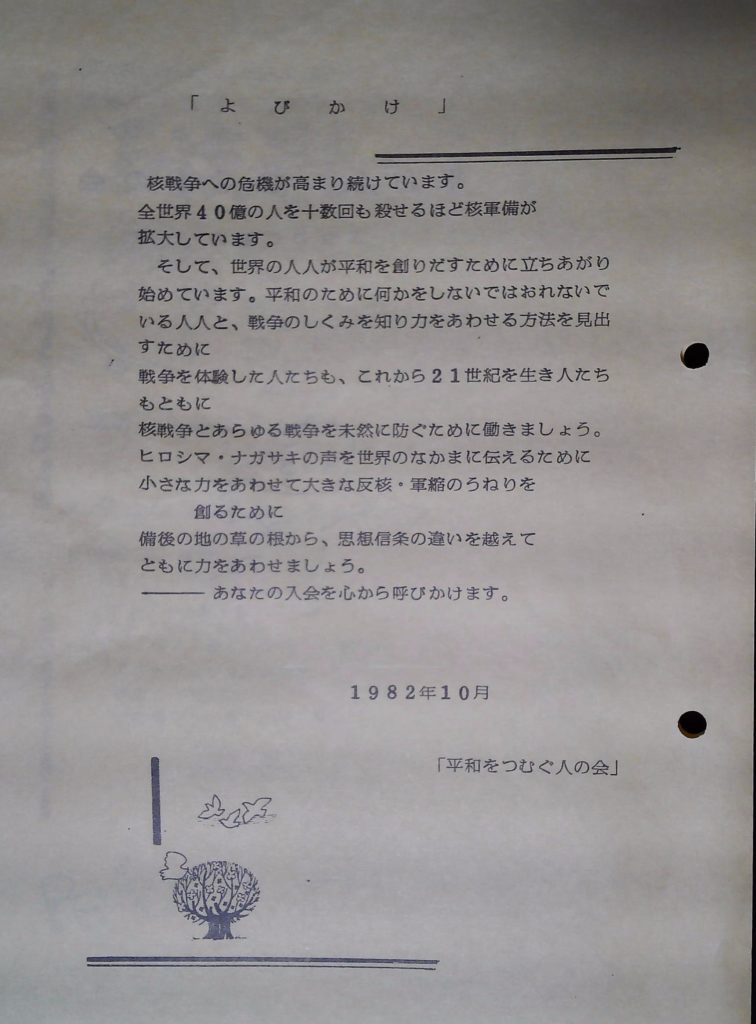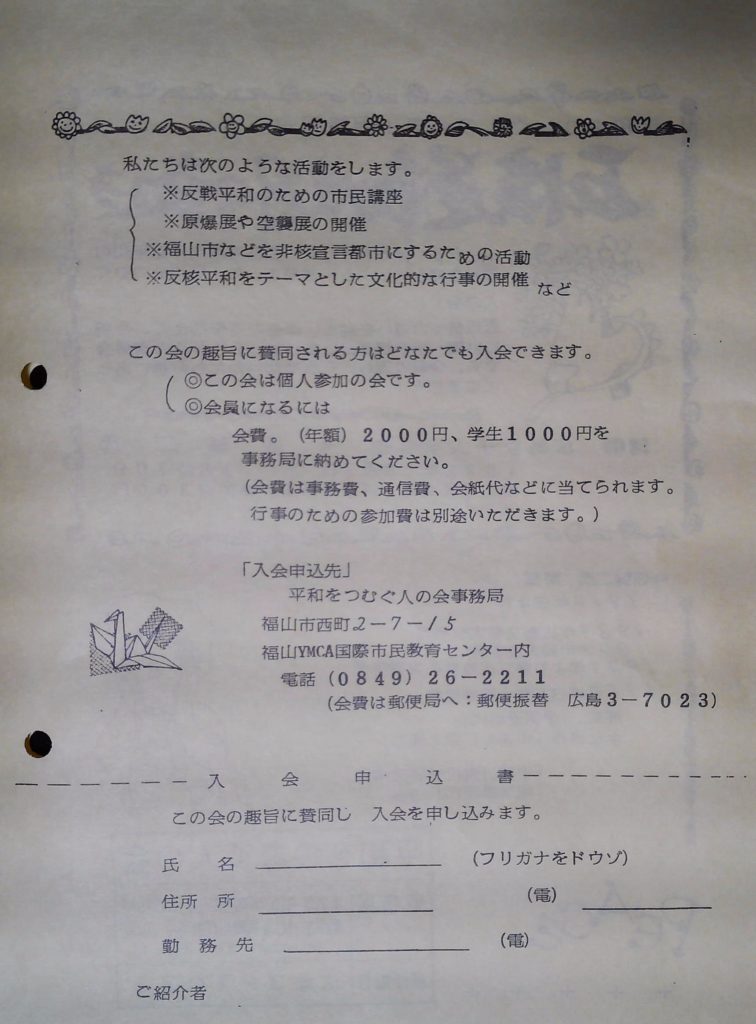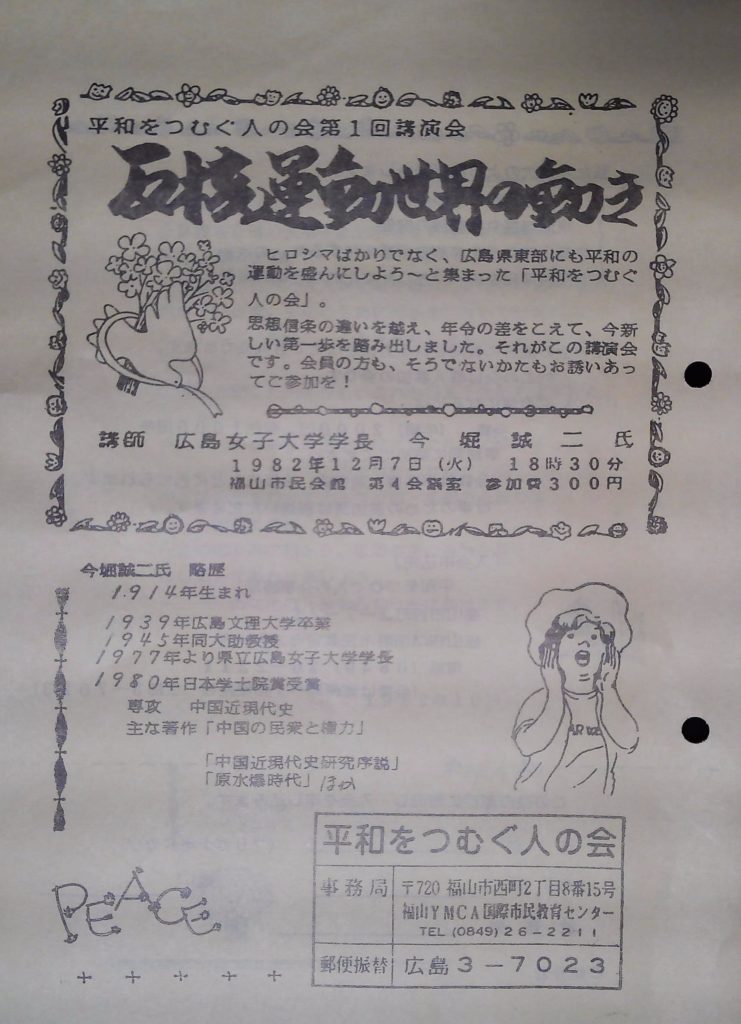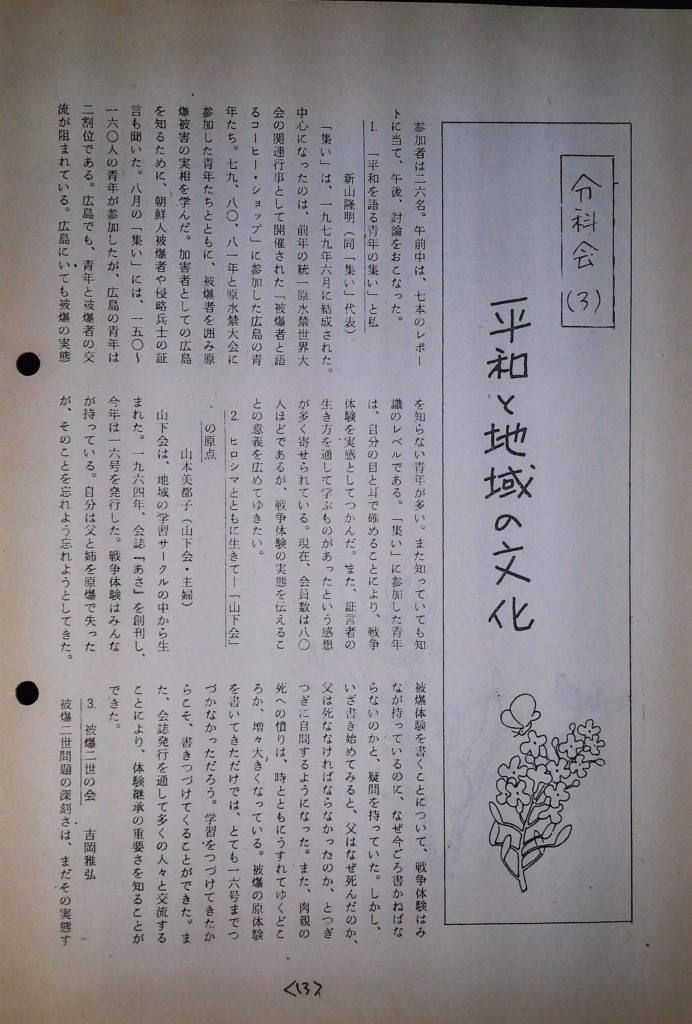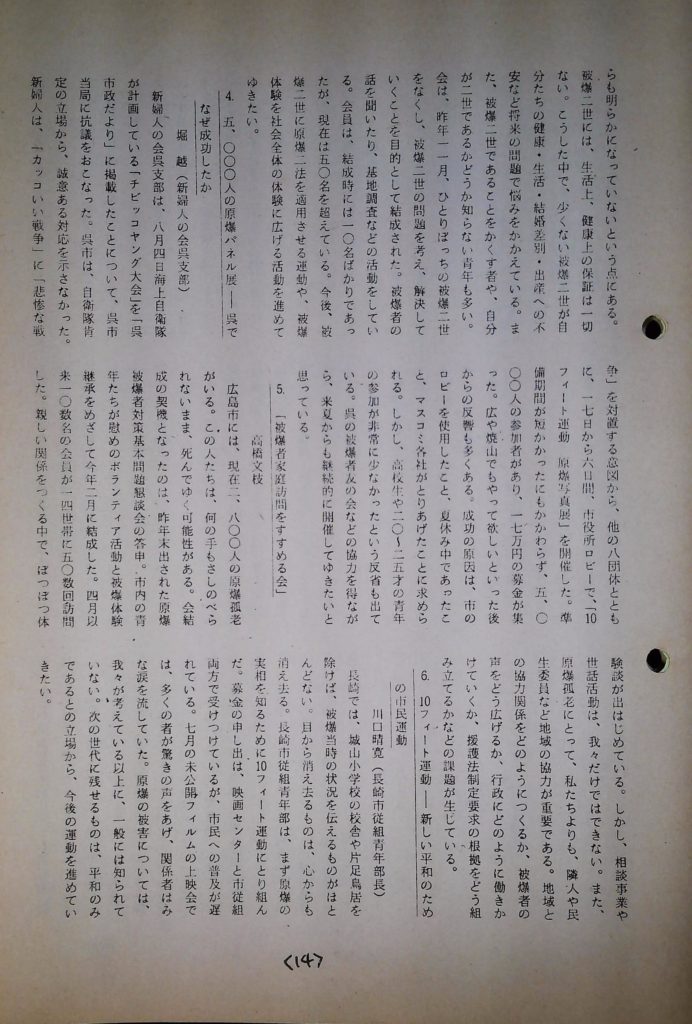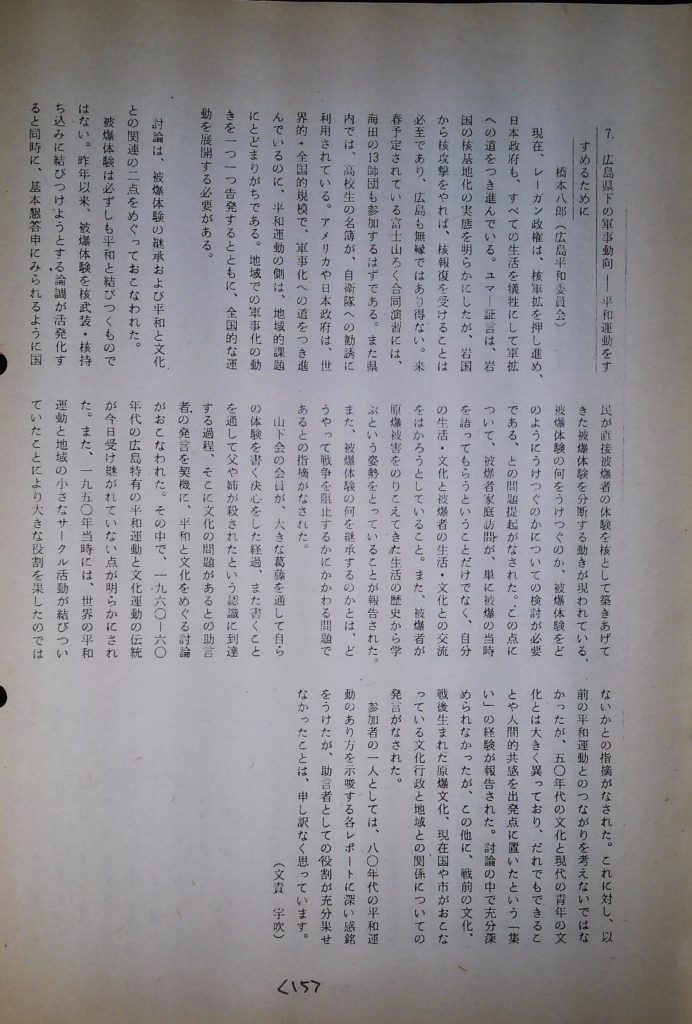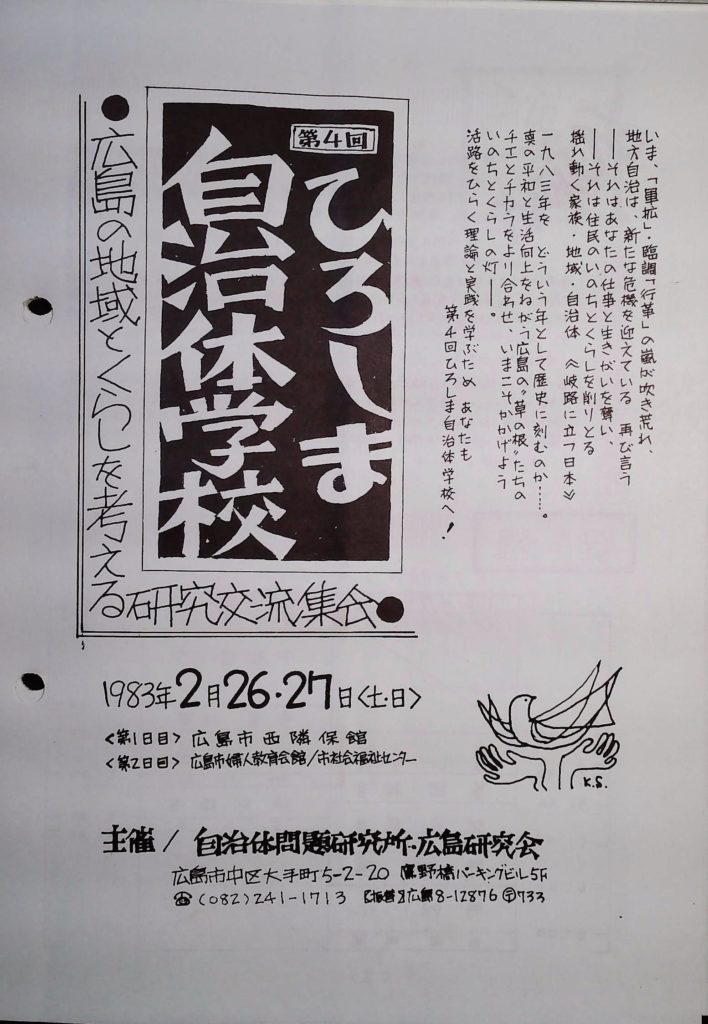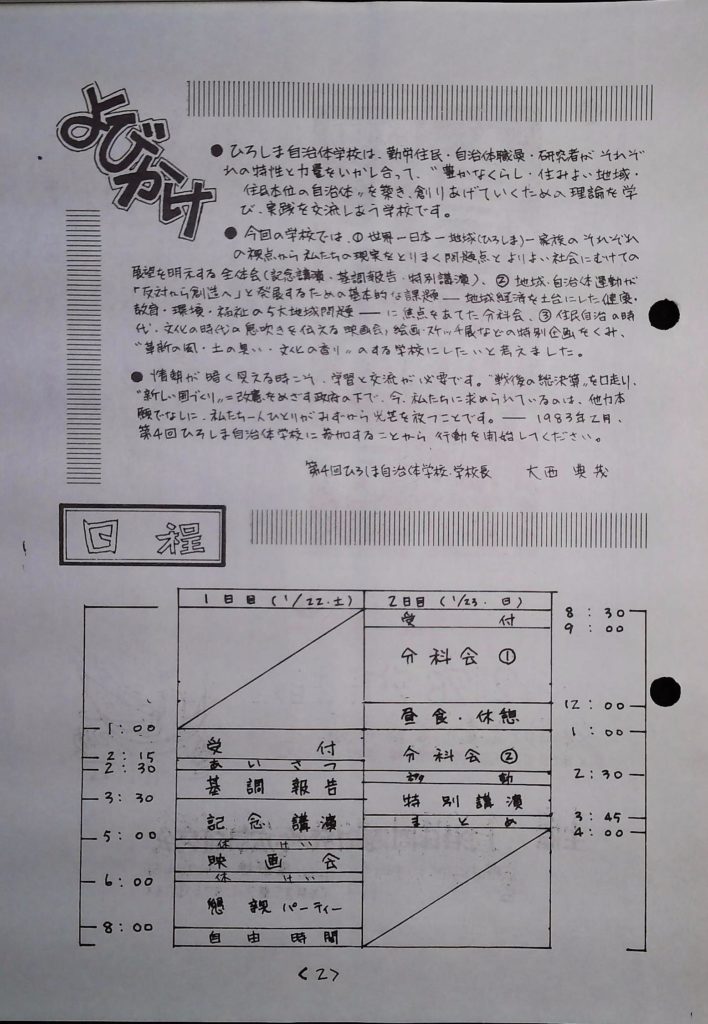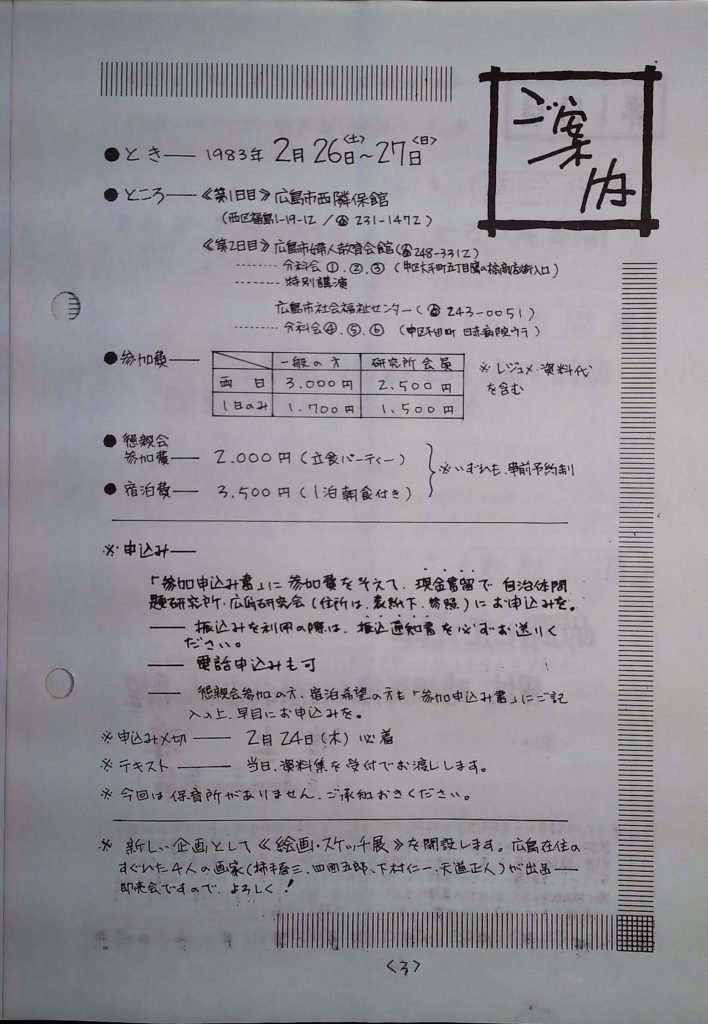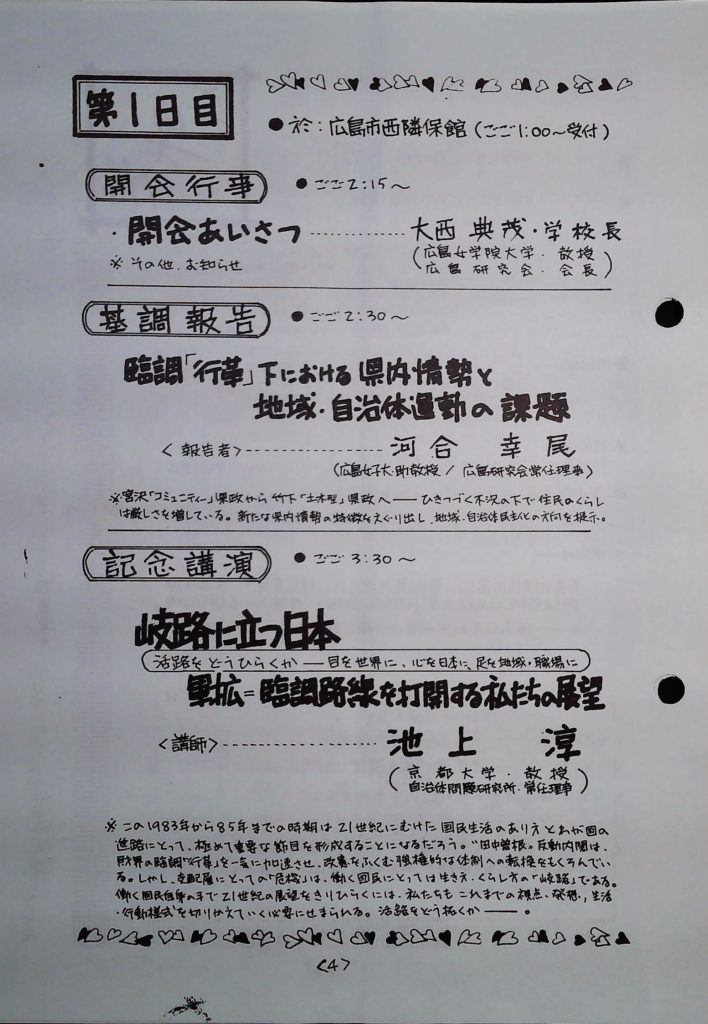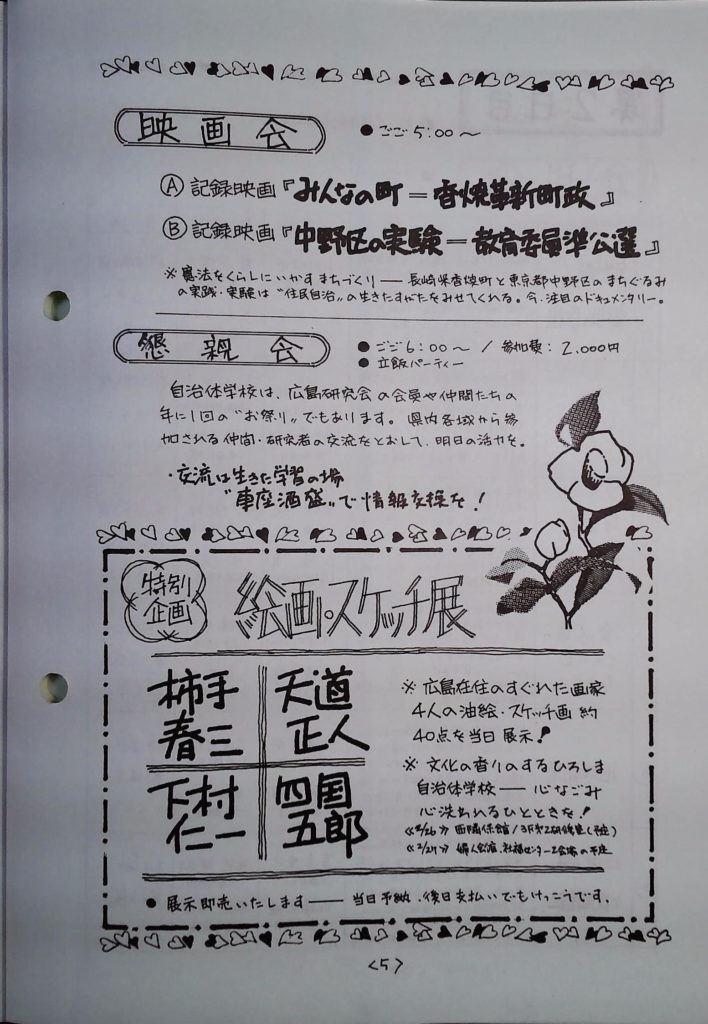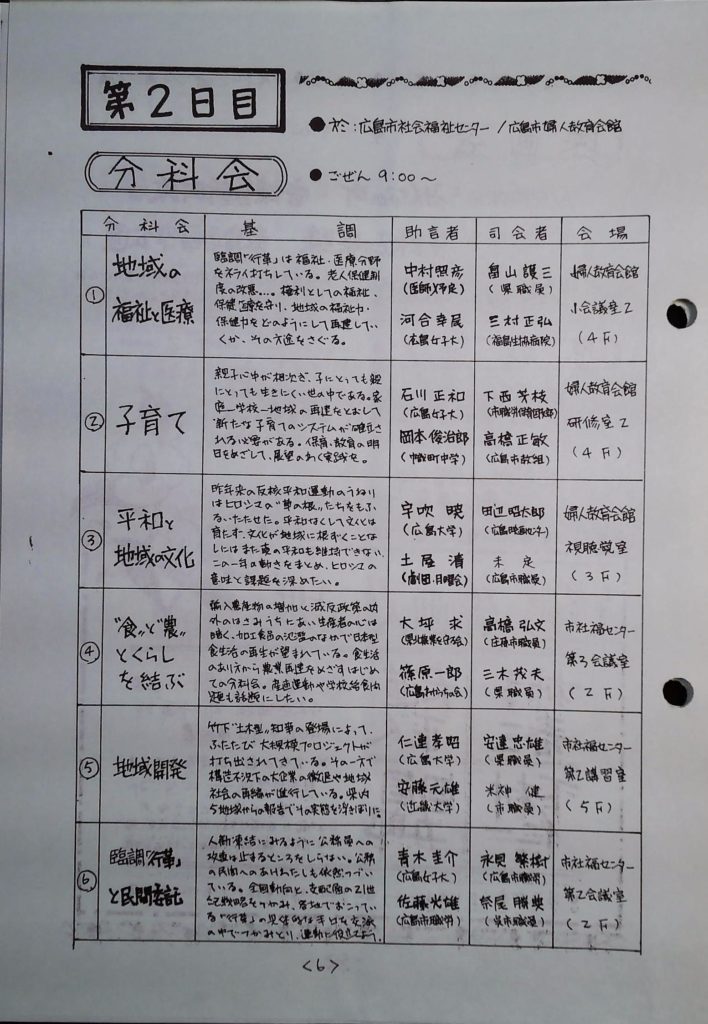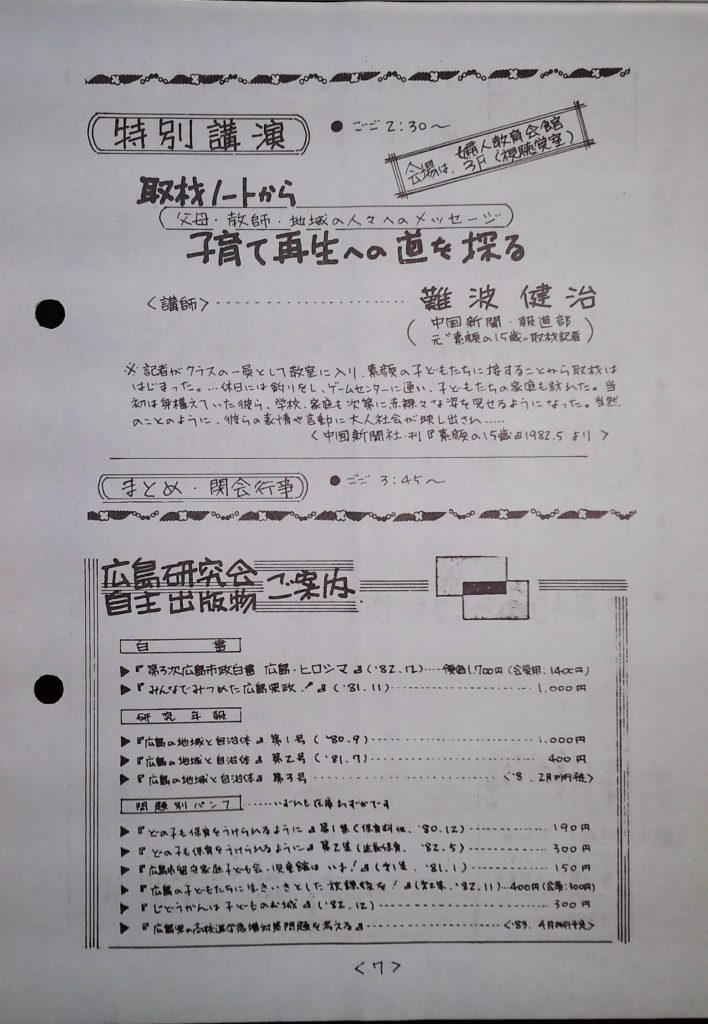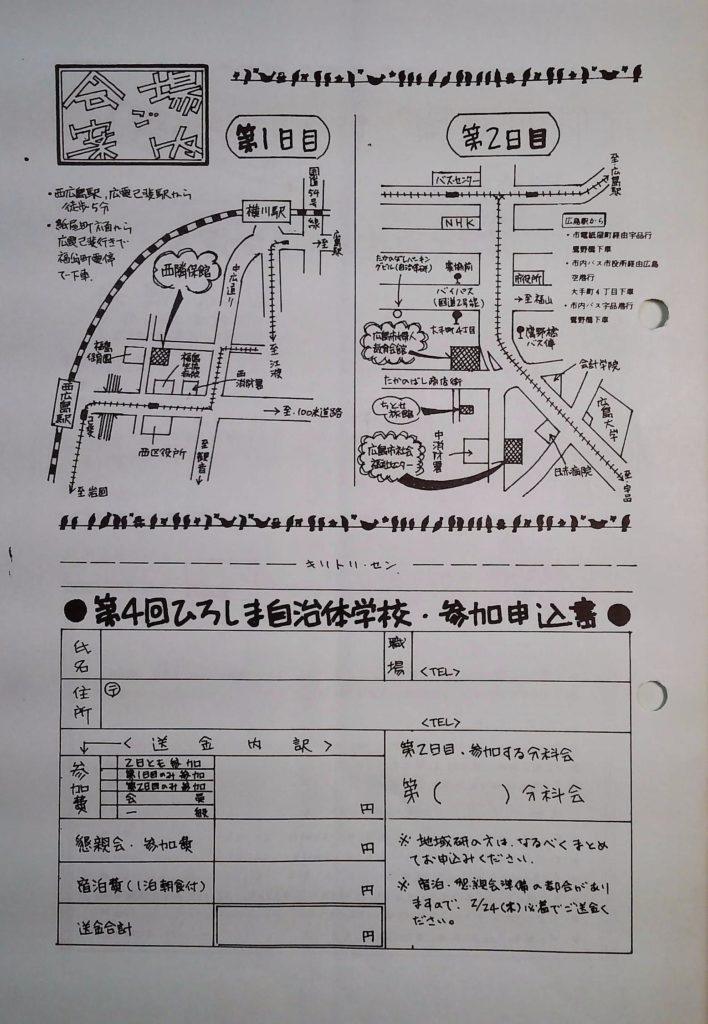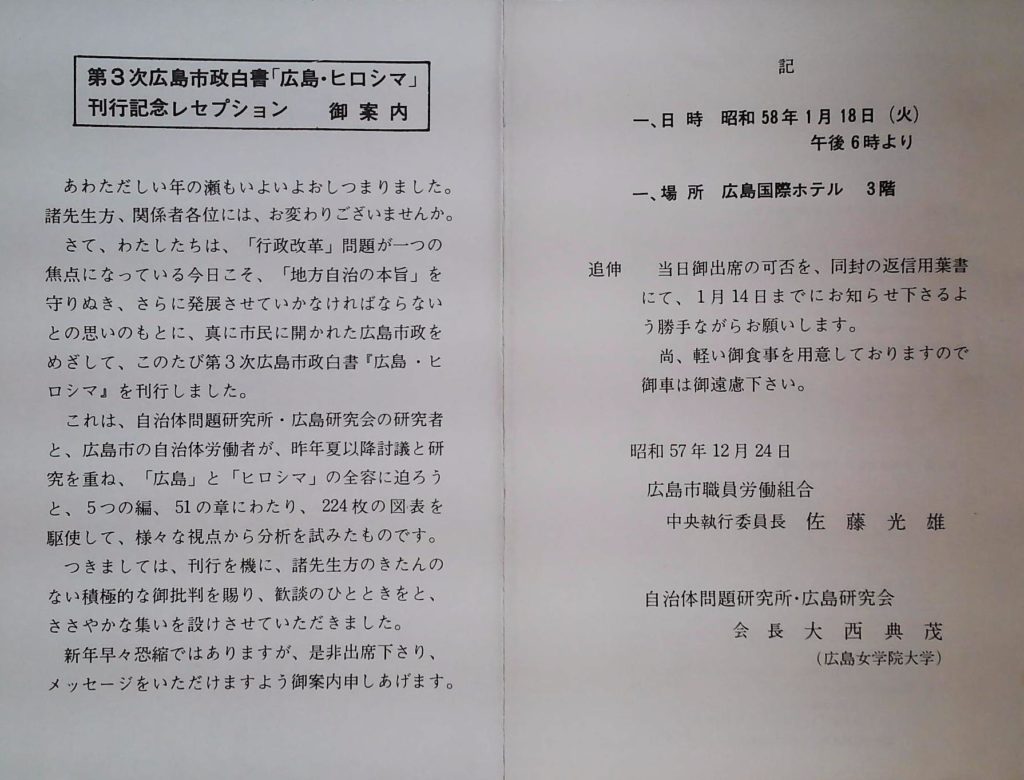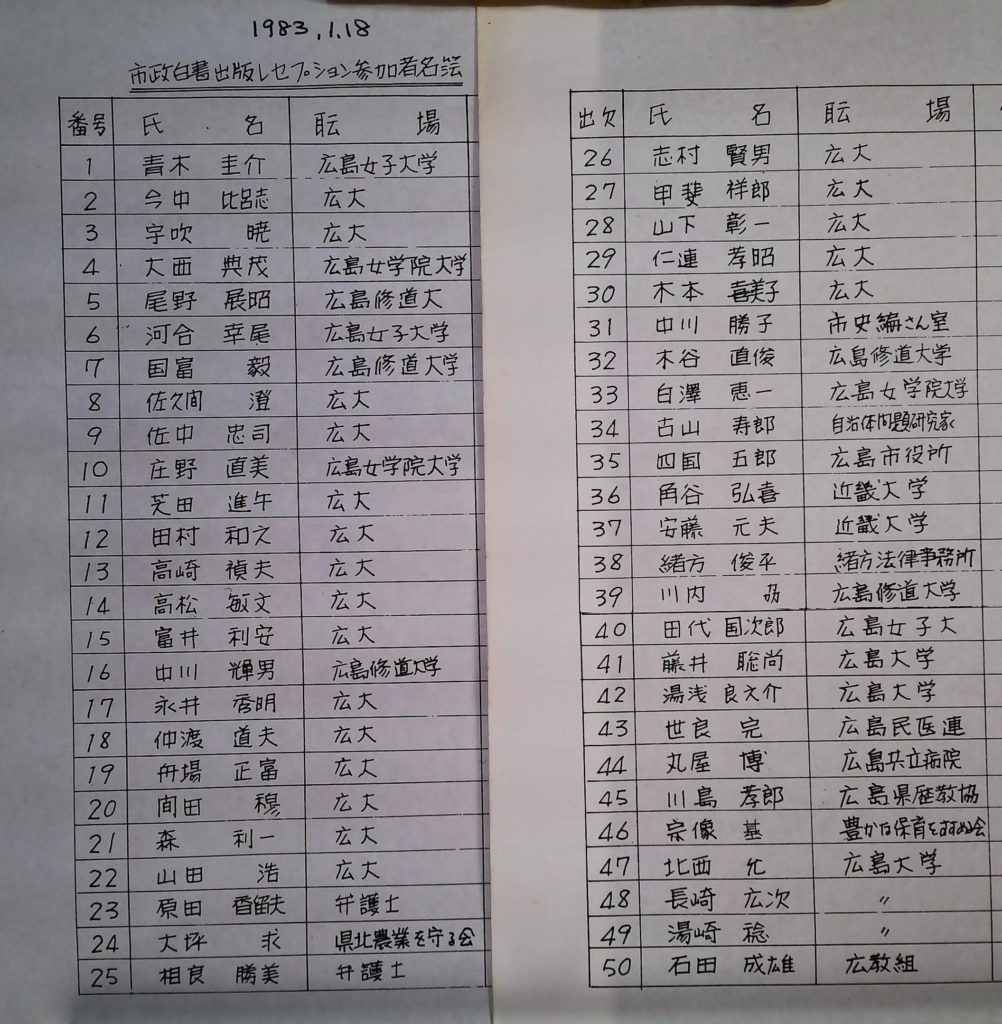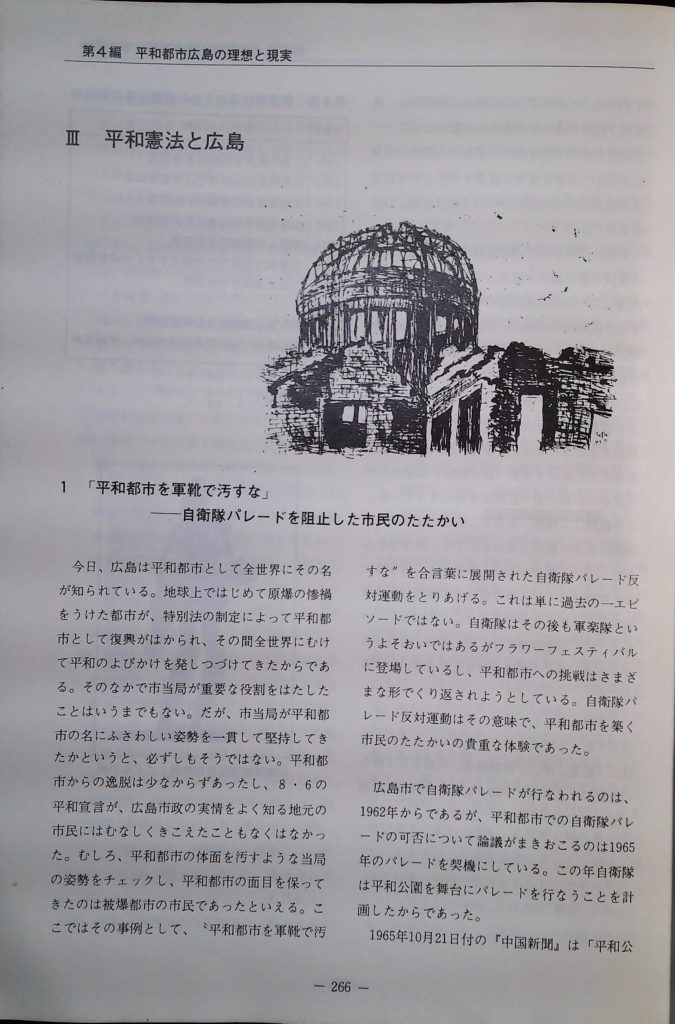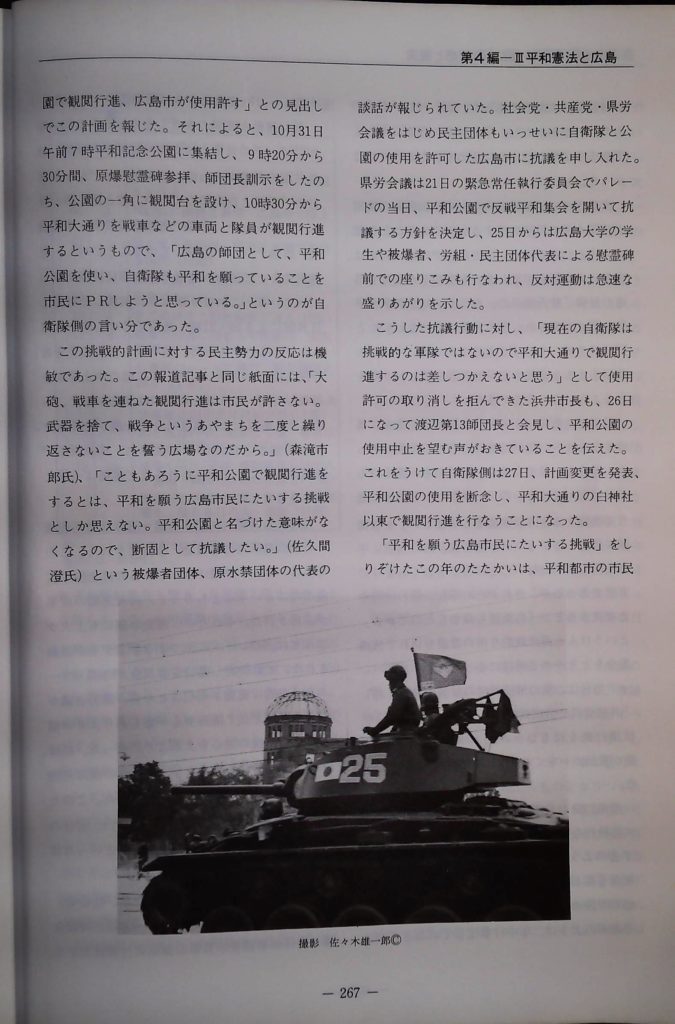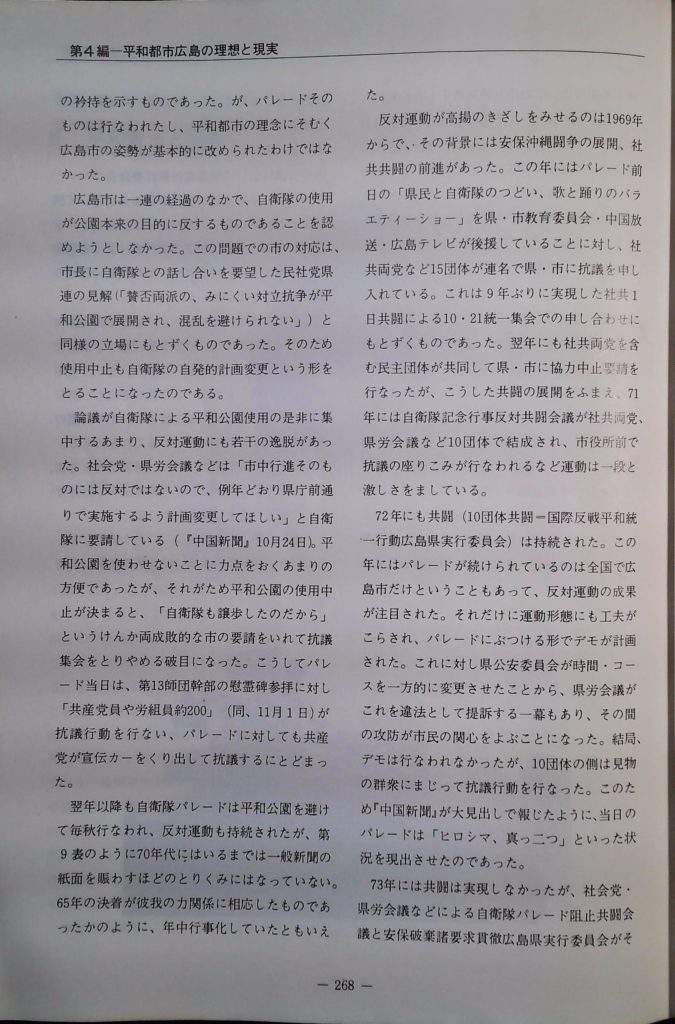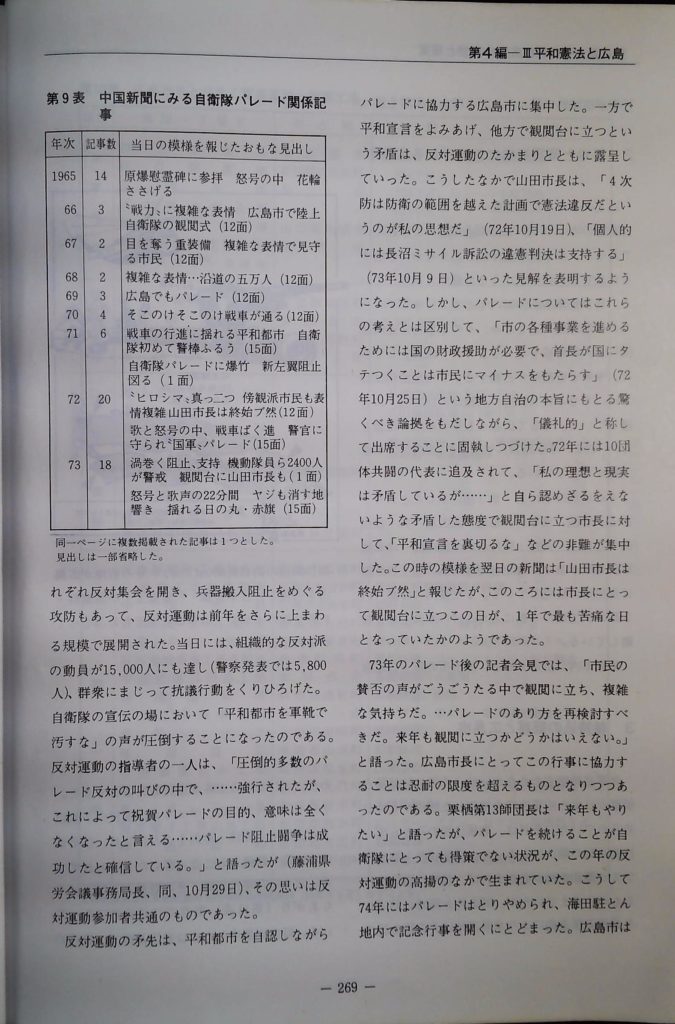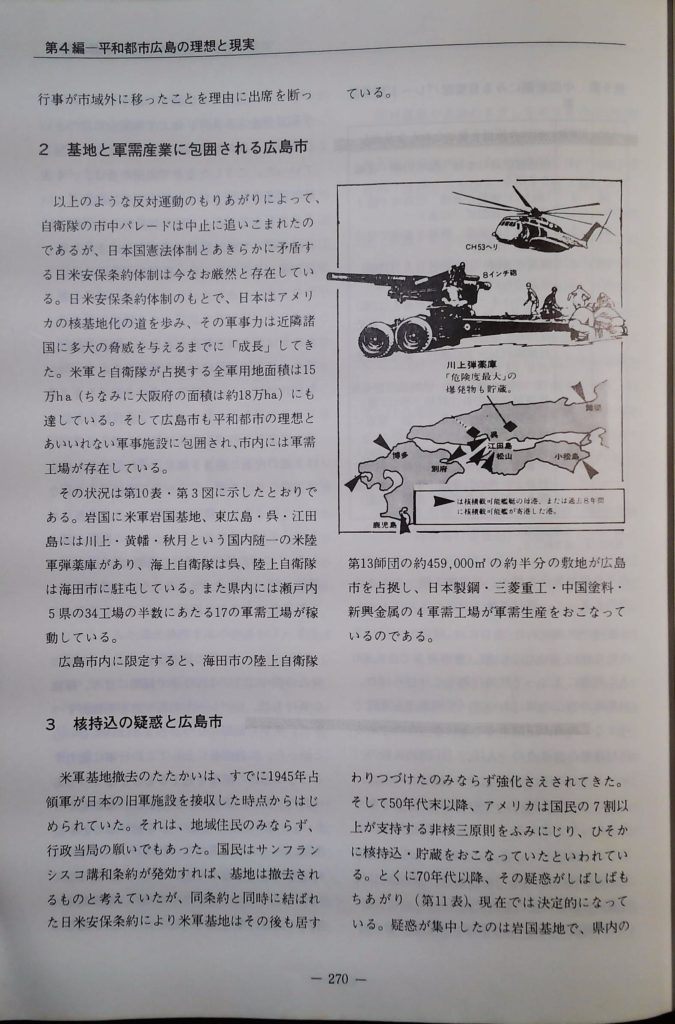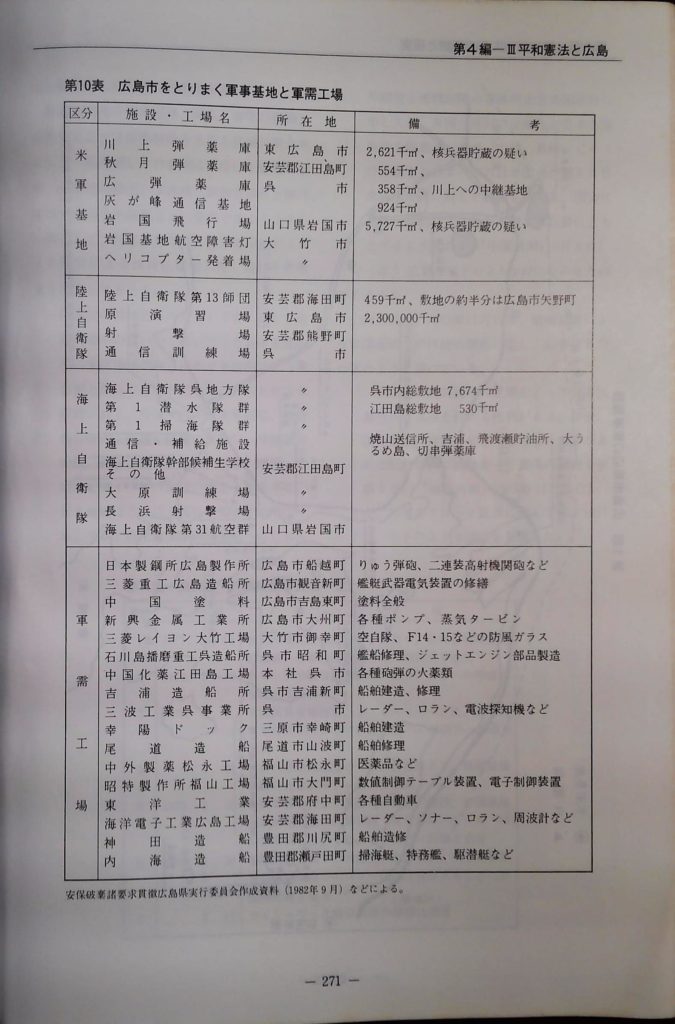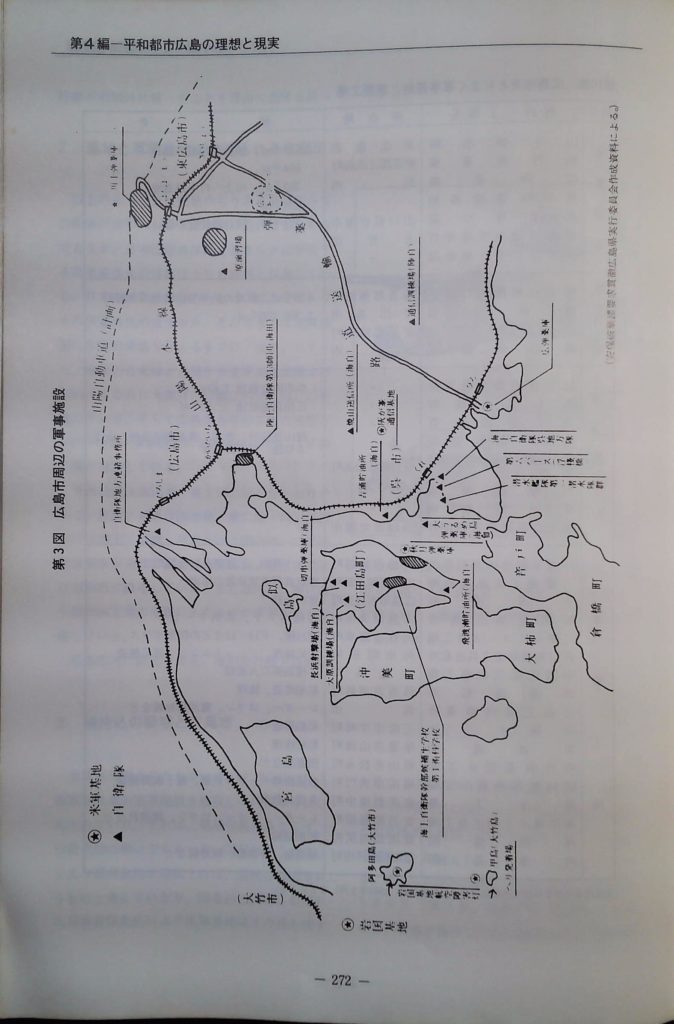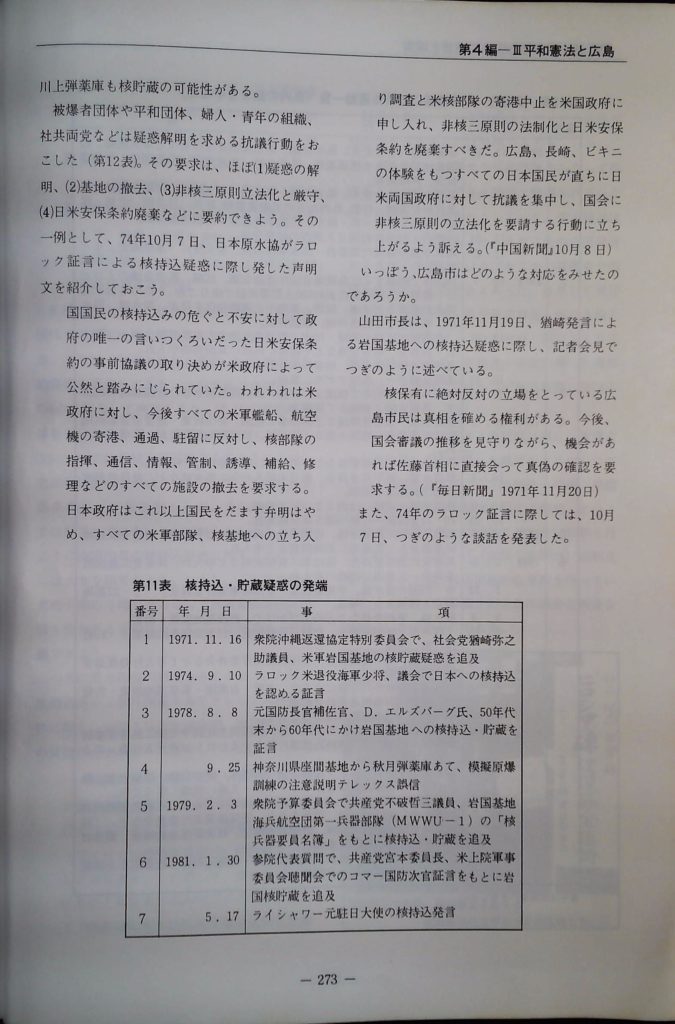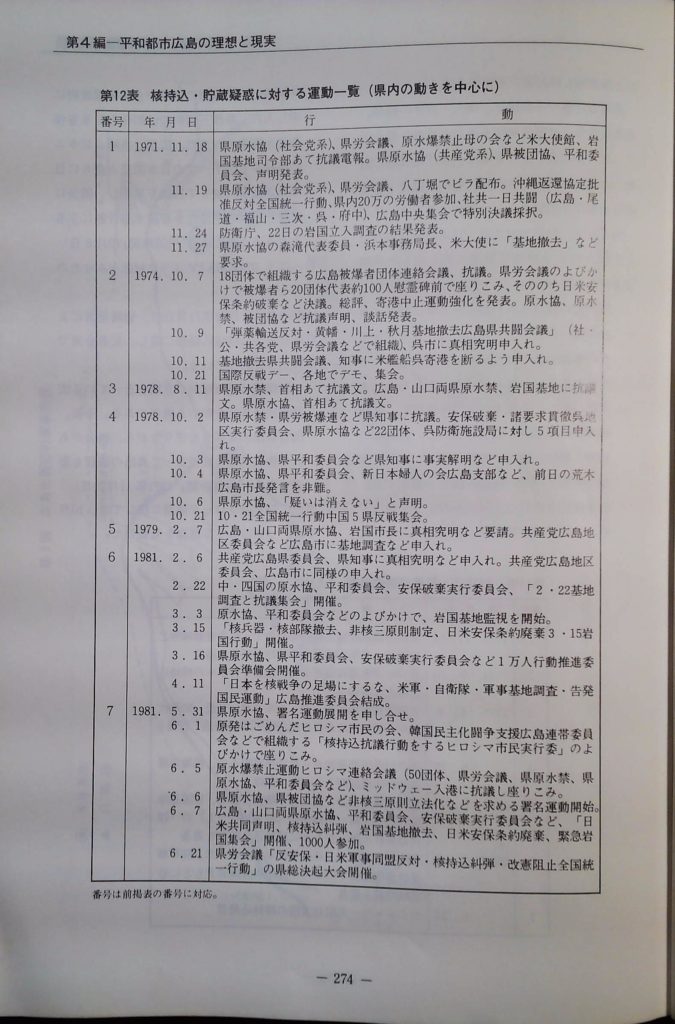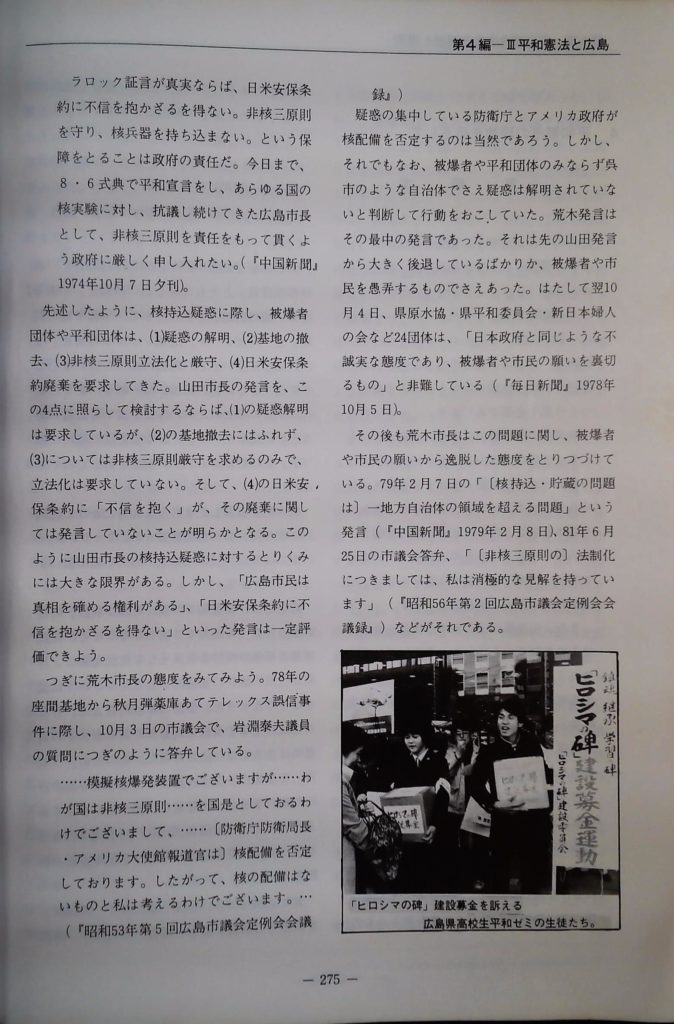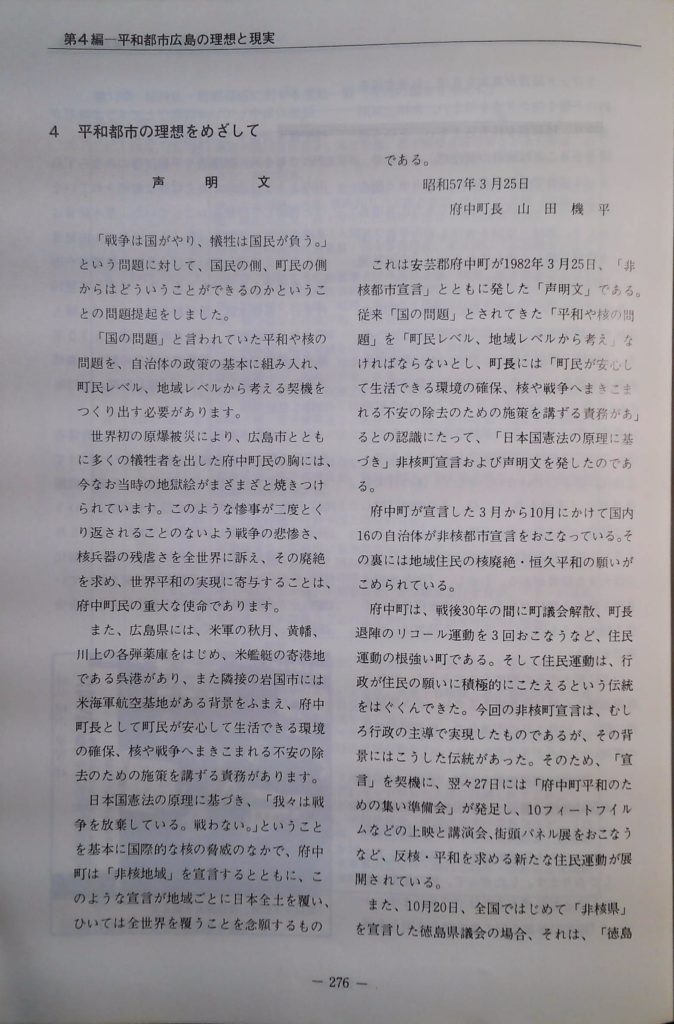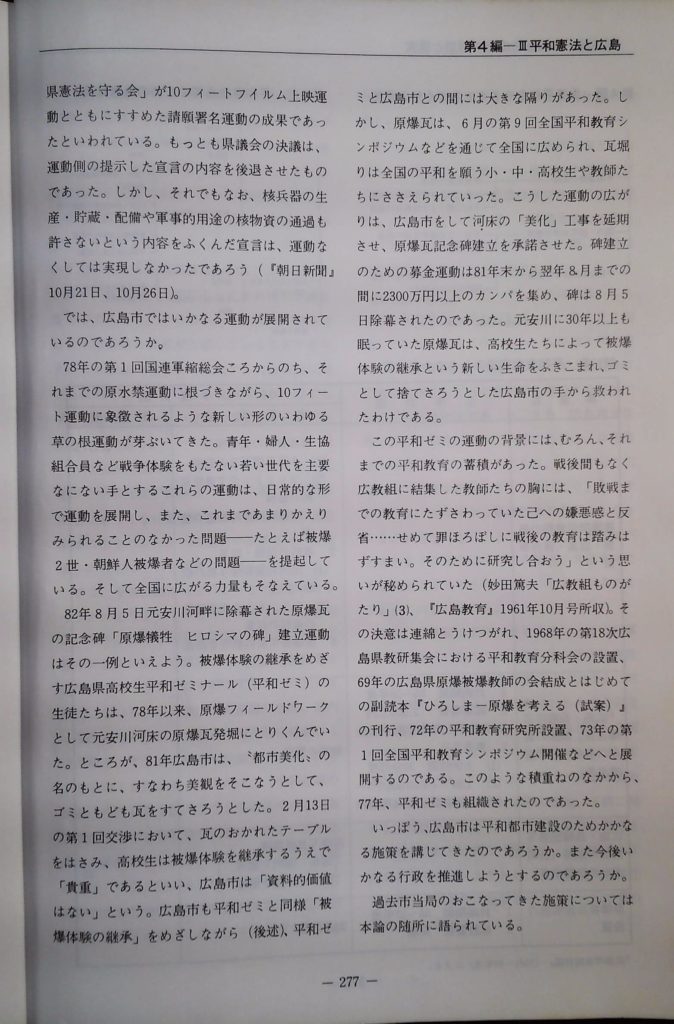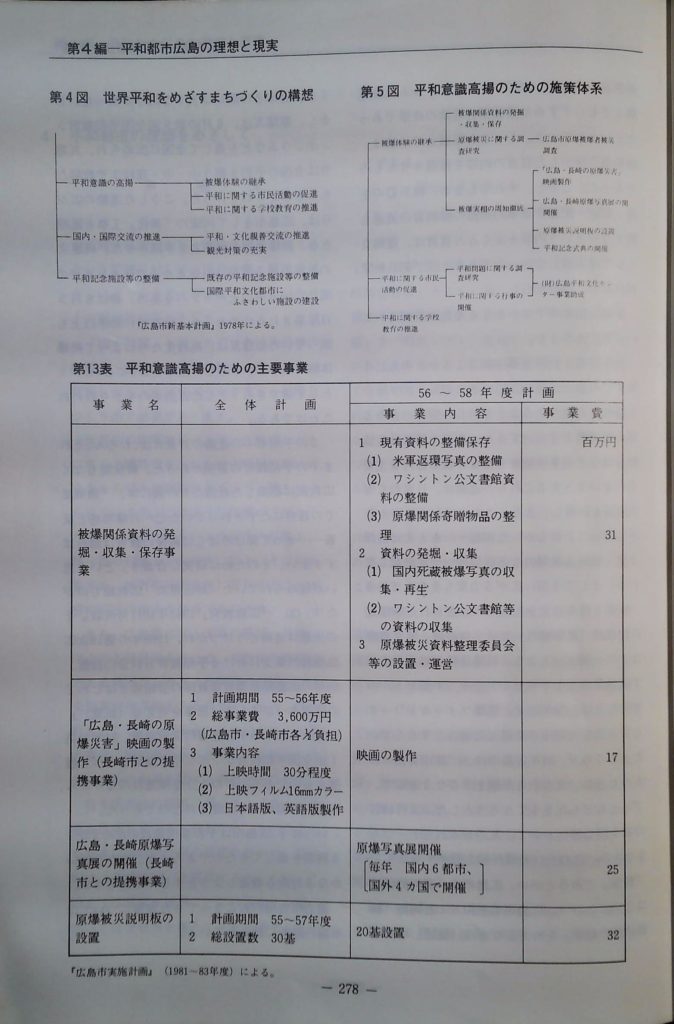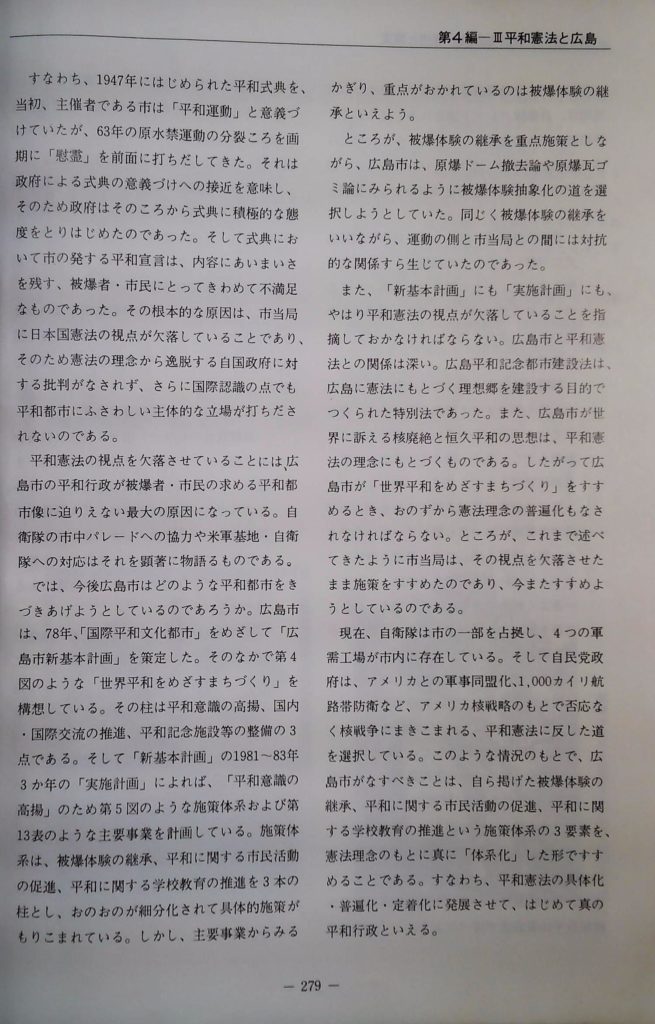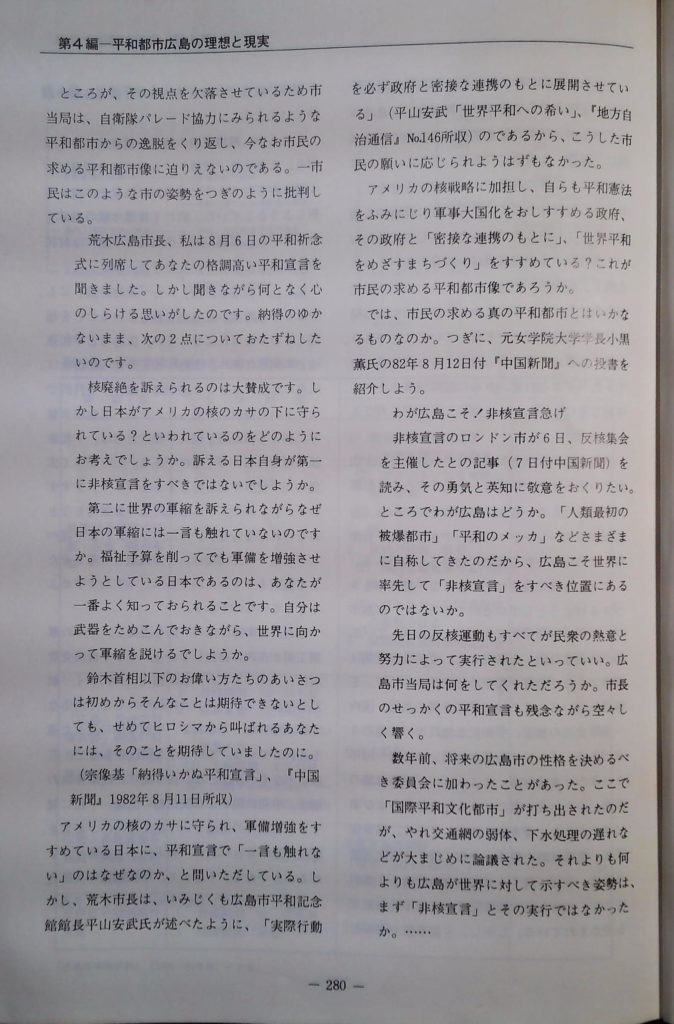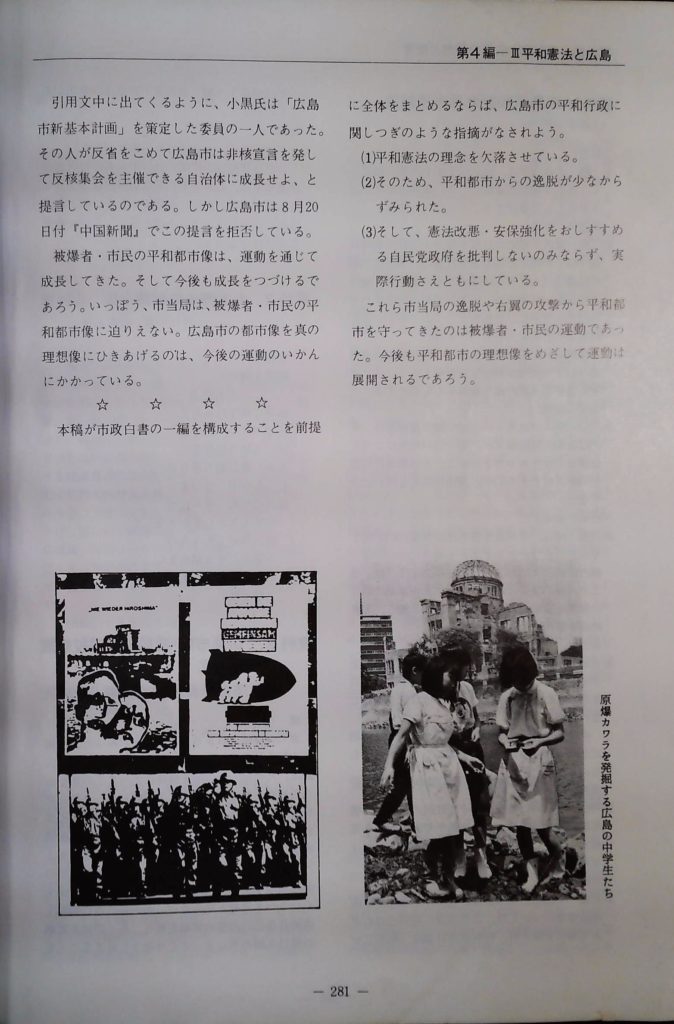『ピカに灼かれて―被爆体験記』(広島医療生活協同組合原爆被害者の会)<作業中>
発行状況
| 集 | 発行年 | 特集など | 備考 |
| 1 | 1977 | ||
| 発行月日はすべて8月6日 | |||
| 創刊号のタイトル=「炎の中の私」。2号から『ピカに灼かれて』。 | |||
| 2 | 1978 | 黒い雨の町の証言 | |
| 3 | 1979 | 子どもたちに平和な未来を | |
| 4 | 1980 | 子どもたちに平和な未来を | |
| 5 | 1981 | 被爆二世を考える | |
| 6 | 1983 | 特集/被爆二世は今 | |
| 座談会 被爆二世問題を考える (桶舎洋子・小嶋章吾・菅三恵・名越由樹・西江久美子・深川宗俊・丸屋博) | |||
| 生協原爆被害者の会役員会のひとこま 74 青原喜代三・桶舎洋子・加藤昭一・佐々木春三・佐々木雪枝・古田和三・丸屋博・渡辺瑩子 |
|||
| 7 | 1984 | 特集/安佐地域の被爆の傷痕めぐり | |
| 8 | 1985 | 安佐地域の被爆の傷痕めぐり | |
| 9 | 1986 | 特集/ひろがる交流の輪 | |
| 10 | 1987 | ||
| 11 | 1988 | ||
| 特集1 日本被団協「11月大行動」参加報告 7 特集2 国連軍縮特別総会参加報告 桶舎洋子 21 特集3 安佐地域の被爆の傷痕 37 |
|||
| 12 | 1989 | 特集・黒い雨の証言 | |
| 特集1 証言・黒い雨 | |||
| 特集2 癌の早期発見・早期治療体験談 | |||
| 特集3 生協原爆被害者の会第16回総会記念講演 加害者として、また被害者として 深川宗俊 72 |
|||
| 13 | 1990 | 特集1 今、なぜ「被爆者援護法」なのか? | |
| 特集2 生協原爆被害者の会第17回総会記念講演 被爆者の生きざまから学ぶこと 若林節美 98 |
|||
| 14 | 1991 | 特集・被爆45周年に被爆者援護法実現をめざす 10月中央行動参加報告集 |
|
| 15 | 1992 | 特集1 被爆カメラマン松重美人氏の証言…松島美人 | |
| 特集2 被爆者援護法実現をめざす中央行動参加報告集 | |||
| 16 | 1993 | 巻頭言 広島大学総合科学部教授 舟橋喜恵 2 | |
| 17 | 1994 | 特集 似島~被害と加害の跡を訪ねて~ 『似島のこと』 西川洋一・6 この水を主人が飲んだかも -念願かなって似島を訪ねる- 淋蒔絹子・11 似島で亡くなっていた娘 正本ハツ子・16 加害と被害の跡の凝縮するこの小さな島 井手本護・18 「似島」と僕の青春と 丸屋博・23 |
|
| -被爆五十周年を迎えるにあたって-―ヒロシマからのメッセージ 広島大学総合科学部数授 舟橋喜惠・62 |
|||
| 18 | 1995 | 表紙絵 四国五郎 短歌 蜂起・強制連行 深川宗俊 2 巻頭言アジアの中の広島 丸屋博 4 |
|
| 特集 韓国平和の旅 加害の跡を訪ねて 韓国平和旅行 企画と実現 三好典子 58 四日間の韓国平和の旅 目見田武市 60 独立記念館で感じたこと 植松由紀子 63 詩・韓国の旅 淋蒔絹子 64 日本人被爆者と同じように補償を・・・・ 韓国の被爆者に思いを馳せて 岡田八十吉 65 日本人のあまり行かないといわれる所に旅をして 桶舎洋子 67 改めて痛感する教育の重要さ 亀岡利子 71 外国から見たヒロシマ これからの証言に活かして 河ロ修三 74 若者達にお願い 木下常登 75 忘れられない植民地の悪 井手本護 77 理解と協力を築きあげて行くことを -被爆者として韓国で感じたこと- 丸屋博 87 往復書簡 通訳・案内人金清子さんへ 丸屋博 91 金 清子さんからの手紙 井手本護 93 金 清子さんへの返事 井手木護・95 |
|||
| 19 | 1996 | 詩 丸屋博 2 | |
| 特集 沖縄平和の旅 |
|||
| 20 | 1997 | 表紙絵 四国五郎 巻頭言 アメリカの臨海前核実験に想う 丸屋博 2 特別寄稿 岩村昇先生の紹介「生きるとは分かちあうこと、弱き者と」 丸屋博 8 小生とピカ・ドン 国際人材開発機構理事長 岩村昇 10 |
|
| 原爆被害者の会、岩国基地見学 基地強化・居すわる殴り込み部隊 丸屋博 78 実現する基地拡張 綿崎直子 80 岩国市の町並 水田春枝 80 岩国に想う 土岐山憲司 82 岩国基地見学参加者の感想より 87 |
|||
| 21 | 1998 | 巻頭言 被爆者の責任を思う 丸屋博 2 | |
| 特集 〈毒ガスの島“大久野島”を訪ねて〉 71 毒ガス工場開設に至る大久野島の歴史 目見田武市 73 青い海の島へ 佐々木春子 74 戦争は人を殺す 真田正裕 75 雑考 土岐山憲司 76 「過ち」は原爆だけか? 井手本護 78 日中友好の礎のために-毒ガス後遺症のこと- 丸屋博 80 大久野島を訪ねて 淋蒔絹子 81 大久野島見学参加者の感想より 82 |
|||
| 特集〈中国・歴史と平和の旅 -被害者の会旅行記〉 83 一、初めての中国 湊アサエ 83 二、紫禁城にて 植杉文枝 84 三、盧溝橋 丸屋博 86 四、万里の長城 福井彩夫 87 五、西安を偲ぶ 渡部輝枝 89 六、兵馬俑抗 亀岡利子 90 七、華清池 丸屋博 92 八、大雁塔 それは西遊記ではじまった 加太恂 93 九、黄浦江雑感 瀧本清也 94 十、旅を終わって 97 |
|||
| 22 | 1999 | ||
| 特集1〈県北の秘められた歴史〉~高暮ダム見学記~・60 | |||
| 特集2〈核廃絶のひろがりと運動のために〉~大阪北部地区での被爆体験の語り部~ | |||
| 23 | 2000 | 巻頭言 「劣化ウラン弾」という新しい「核兵器」 丸屋博 2 | |
| 特集1 〈海峡をこえて-在韓被爆者渡日治療-〉 | |||
| 特集2 〈鶴よ羽ばたけ-子供達が作った「折り鶴の碑」-〉 | |||
| 24 | 2001 | ||
| 特集1〈被爆者、国境をこえて「結縁」〉 | |||
| 特集2〈人間魚雷「回天」の基地へ〉 | |||
| 25 | 2002 | 表紙絵四国五郎 巻頭言韓国・欧州のヒロシマを想う…丸屋博・2 |
|
| 特別寄稿 原爆症認定、松谷勝訴後の取り組みと集団提訴について…青木克明・73 |
|||
| 特集〈在外被爆者に援護の手を〉 | |||
| 被爆者はどこにいても被爆者…豊永恵三郎・79 在外被爆者にも被爆者援護法の適用を 在韓被爆者渡日治療広島委員会のとりくみ…牛尾美保子・86 渡日治療を受け入れて…桧垣陽子・89 被爆者援護法に思う…広瀬雪枝・92 韓国原爆福祉会館を訪れて…若藤コマコ・92 被爆者はどこにいても被爆者…水田春枝・93 李在錫裁判の勝訴を祈る…野崎スズ子・94 |
|||
| 26 | 2003 | 表紙絵四国五郎 巻頭言原爆許すまじ、戦争許すまじ…青木克明・2 |
|
| 特集Ⅰ〈陝川「平和のどんぐり」記念植樹〉 「どんぐり」の実りを思う…丸屋博・44 三年の歳月一平和の「ドングリ」聾心植樹に参加して…野崎スズ子・47 1陜川を訪ねて…若藤コマコ・49 出会いの旅…亀岡利子・50 被爆者はどこにいても被爆者…水田春枝・53 |
|||
| 特集II〈黒い雨〉 あれから五十八年…曽里サダ子・54 黒い雨…原美智枝・57 黒く染まったハヤの群れ…笠井明子・58 母と安川を渡る…木本フミ子・60 降雨地域の見直し.拡大をめぐる「黒い雨の会」のとりくみ…渡辺力人・62 |
|||
| 27 | 2004 | 特集1〈在ブラジル被爆者を訪問して>…青木克明・50 | |
| 特集Ⅱ〈今、なぜ原爆症認定訴訟か〉…中野治子・60 死亡後に原爆症認定~佐々木春子さんの場合~…三村正弘・63 「負けるか」と思う…故佐々木春子・65 佐々木春子さんを偲ぶ…水田春枝・68 志賀笑子・68 長野サト子・69 野崎スズコ・70 |
|||
| 28 | 2005 | 発行月日:7月15日 終刊号 | |
止