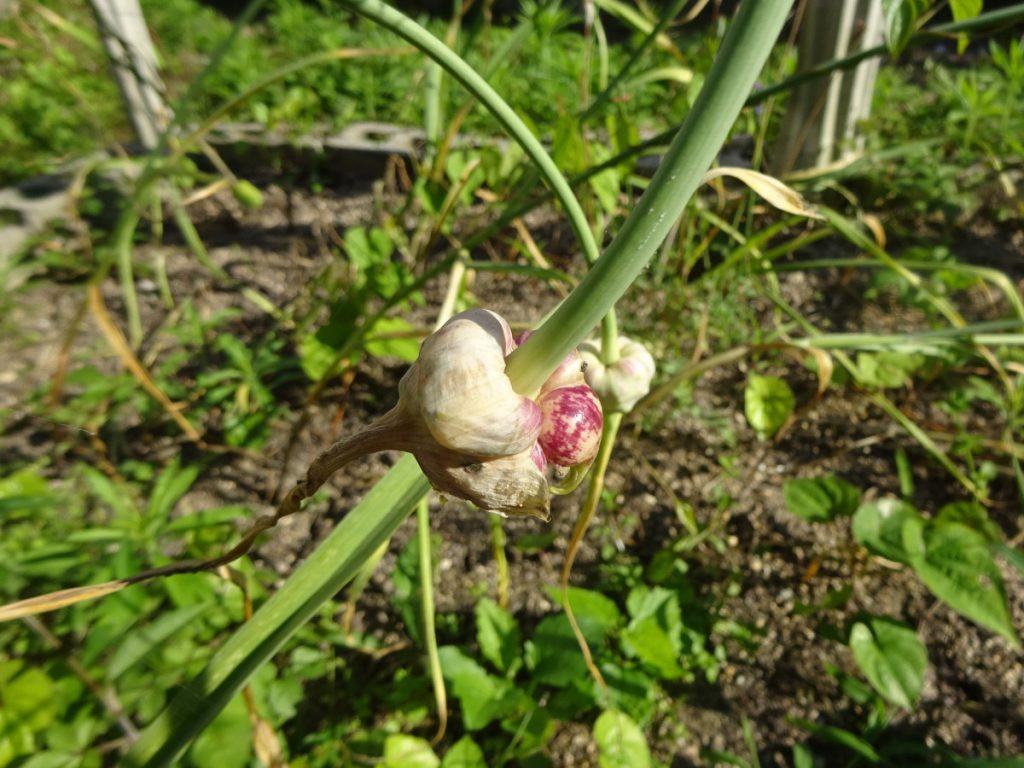ひろしまの碑をめぐる思想性1975年9月の宇吹報告
『平和教育研究』(広島平和教育研究所・年報1976年)所収
(1)
今日、平和公園をはじめとして広島市内で私が確認した限り、いわゆる「慰霊」を目的とした碑は90余りあります。歌碑とか詩碑で、慰霊の意味を含まない平和慰霊碑を会わせると120の碑があるという報告もありますが、慰霊の内容が確認できるものとしては、90余りだと思います。
これらの碑を訪れてみた感想としては、どの碑の場合も掃除がきちんとゆきとどき、今日もなお、市民や遺族の哀悼の念が戦後30年生き続けていることが非常によくわかりました。そして、慰霊碑そのものが、犠牲者なり遺族なりの戦後30年の歴史をさまざまな形で示しているようにも思ったわけです。それらが、今日生きている私たちにさまざまな事柄を強く訴えており、その内容をどう位置づけるかと言うことで、一つの史論的なものとして、「ひろしまの碑をめぐる思想性」を考えてみたいわけです。
そこで一つの例として、広島市立高等女学校の慰霊碑の経緯をみてみたいと思います。といいますのは、この経緯は他の慰霊碑と似かよったものがあり、他の慰霊碑もこれとよく似た歴史をもっているので、まずその流れを述べてみたいと思います。
終戦直後の昭和20年10月30日、この10月30日というのは戦前の教育勅語発布の記念日だそうですが、この日に、「殉職諸先生及び生徒の慰霊祭」が市立高女(現在の舟入高校)の破損した講堂で行われています。翌21年8月6日、多くの生徒と教職員が家屋疎開作業に出ていて原爆の犠牲となった現場で、一周忌法要という仏式の慰霊祭を行い、「殉職諸先生並生徒供養塔」と書き込んだ木碑をそこに建立しています。
2年後の昭和23年5月に新制高校が発足し、市女は二葉高校として出発しましたが、その年の8月6日に、母校市女の御真影奉安庫跡に石の祈念碑を建立し、慰霊碑とは呼ばずに「平和塔」と呼びました。正面は、少女が3人刻みこまれ、まん中にE=MC2(原子エネルギーの公式)という箱をもった少女がいます。裏側は「友垣にまもられながらやすらかに眠れみたまよこのくさ山に」という詩が刻んであります。
昭和25年、都市計画で最初に建てた木碑の「供養塔」地が百メートル道路の一部になるので、その年の8月6日に持明院というお寺の境内に木碑を移しています。同時に、広島市女原爆遺族会を結成し、以後は遺族会が中心となって追弔行事を行ってきました。さらに翌26年8月6日、持明院境内にもう一つの石碑「市女原爆追悼碑」を建立し、除幕しています。これは学校に建立した平和塔と同じものですが、正面のE=MC2がなくなったかわりに、「市女原爆追悼碑」と刻み込まれています。そして昭和32年8月6日、学校に建立した「平和塔」を現在地の元安川畔へ移し、今日にいたっているというのが大まかな経緯です。
(2)
この市女の例にみられるように、広島市内にある慰霊碑の多くは、慰霊祭とか慰霊法要という宗教的行事に結びついて建立されているようです。この点について、原爆投下後から翌21年8月までの一か年間に、当日の中国新聞に慰霊祭・慰霊法要を営むという宣伝広告がたくさん載りました。総計すると114種の慰霊祭・法要の通知が載っています。1年間でこれだけたくさんの慰霊祭・法要が営まれたわけですが、その際に、遭難地・火葬地・学校や職場・法要を営んだ寺などに木碑が多く建てられたと思われます。このようにして建てられた木の墓標とか、簡単な供養塔が広島における今日の慰霊碑の始まりのようです。
今日、これら初期の木碑は、そのままの形で残っているものはありませんが、当時のもので碑銘の明らかなものを調べてみると、戦死者31名之墓・船舶練習隊処理之墓・広島郵便局殉職者供養塔・神崎学区戦災死没者追善供養塔など、「原爆」という文字の出てこないのが注目されます。占領下では、こうした銘名が一般的であったようで、終戦直後のプレスコード(9月19日)などによって原爆に対する批判が封じられていた影響によると思われます。
占領下の当時は、原爆という文字が使えないだけでなく、学校などに慰霊碑を建てることにも制約が加えられています。昭和20年と22年に広島市から各国民学校長宛に出した公文書の中で、慰霊碑建立に対する制約のあることが確認できます。また当時、広島市立学校長に、学校に現存する忠魂碑とか戦没者記念碑などを撤去したかどうか報告せよという文書も出されています。そのほかに、学校を宗教行事に使用してはならないだけでなく、学外でも学校がこうしたことを主催するのを禁止しています。
昭和20年から22年に出されたこれら一連の通達は、それまでの軍国主義的な教育と一線を画すために行われた政策の一つであったと思われますが、逆に原爆犠牲者の遺族達の慰霊に対する心情をゆがめる結果にもなったと思います。
こうした当時の状況を反映して、一例として最初に述べた市女学内に建立された碑は、慰霊碑と呼ばずに「平和塔」と呼びました。この点について市女原爆遺族会長は、「当時わが国は米国占領下にあり、慰霊碑などの建立は許されない諸情勢であったが、市女原爆関係者は率先してこれを建立し、平和塔と呼んでいた」と追憶記の中で書いています。また、この平和塔の浮彫は、「あなたは原子力(E=MC2)の世界最初の犠牲として人類文化発展の尊い人柱となった」と級友が犠牲者を慰めている姿を表しているといわれており、ここでは原子力と原爆が同一視されています。占領政策が解かれた年の昭和26年に持明院境内に建てられた同型の碑では、表面の浮彫は消え、かわりに「市女原爆追悼碑」という碑銘がはいったことなどからみて、いかに原爆がタブー視されていたかの一端がうかがえます。
このように、「原爆」という二文字さえ自由に使えなかった占領下においては、ほとんどの慰霊碑の性格は、慰霊という宗教目的を出ることはありませんでした。しかし、占領が解けると、慰霊碑はさまざまな性格をもつようになってきます。その一つは、「原爆」という二文字が一般的に用いられるようになったことです。つまり、原爆犠牲が「戦死者」「戦災死者」など戦争一般の犠牲者と区別できない表現から、「原爆犠牲者」「原爆死没者」というように、その死因として「原爆」を指摘する表現になったことに大きな意味があると思います。
二つには、原爆という言葉と同時に、「平和の礎」「殉国」「散華」「英魂」「英霊」と言った死者に対する一種の意義づけが行われるようになったことです。「平和の礎」という表現は占領下から使われていましたが、これは、原爆投下が戦争を早く終わらせ平和をもたらしたのだという占領政策の思想からきたのだと思われます。昭和30年ごろまでよく使われていましたが、それ以後の碑にはなくなっています。「殉国」「散華」などは、戦前から使われている普通の表現ですが、占領下では消えており、占領解除後は学校関係の碑を中心に多く用いられています。これは、いたいけない子ども達を失った父母たちが、何らかのかたちでその死を位置づけたいという気もちによるものだと思われますが、今日の靖国神社法案と関連して深刻な問題を示しているともいえます。
「平和の礎」や「殉国」などといういい方は、過去の反省にたった表現となっていますが、昭和30年前後からは、原爆犠牲を過去のこととしてではなく、現在や未来に結びつけたものが建てられるようになりました。つまり、原爆犠牲者への哀悼の念をとおして平和への祈念、原爆への怒り、核兵器廃絶の決意などが語られるようになったわけです。その表現方法も、具体的なことばだけでなく、象徴的な彫刻などによるようになりました。
たとえば、「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから=原爆慰霊碑」「これはぼくらの叫びです これは私たちの祈りです 世界に平和をきずくための=原爆の子の像」「なぜあの日はあった なぜいまもつづく 忘れまい あのにくしみを この誓いを=全損保労組被爆20周年記念碑」「天を撃つな 戦霊を射て 人を撃つな 戦禍を射て 原爆広島に眠る 無名の霊よ 国鉄の魂よ 霊の目はみつめ 魂の手はつかむ 平和と未来を=国労慰霊碑」などがその一例です。
これら慰霊碑の碑文や彫刻などに脈うつ原爆観、平和観はけっして同一ではなく、戦後30年広島・日本・世界中にうずまいた平和運動の影響を多かれ少なかれ受けていると思います。その意味では、今日までの平和観・原爆観の縮図のような気もしますが、一つだけ同じ訴えをしているように思います。それは、広島の悲劇を再び地上にくり返してはいけないということです。
(3)
以上が、碑をめぐる問題について私なりの大まかな史論的な考えです。それと関連して、これら広島の慰霊碑と国などが行っている慰霊祭は、本質的に違うと思うのです。国などの場合は、戦前のことが常に考えられているようだし、靖国神社ともつながって計作されていると思います。これに対し、広島の慰霊碑の性格としては、市民の要求や市民のやむにやまれぬ感情が結集してつくられていると思います。
ところで、体験記の中にも慰霊碑でみてきたのと同じような流れがあります。[中略]
慰霊碑の碑文が簡潔で、どのようにでも解釈できるような場合もたくさんあるわけですが、慰霊碑の建立を機に出されている体験記集とかみあわせることによって、その碑のもつ意味が一つ一つ正確に位置づけられると思います。