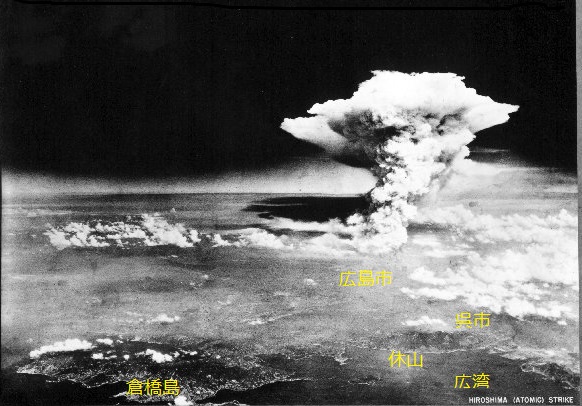『ヒロシマ・ナガサキ原爆写真・絵画集成(全6巻)』(編集委員:家永三郎・小田切秀雄・黒古一夫、発行所:日本図書センター、19930325)
ヒロシマ・ナガサキ原爆写真・絵画集成1-被爆の実相
| 頁 |
タイトル |
著者・作者 |
| 003 |
序 (映像記録の意味するもの) |
家永三郎 |
| 005 |
アサヒグラフ 1952年8月6日号 |
|
|
原爆犠牲都市第1号・広島 |
尾糠政美/松本栄一/宮武甫 |
|
原爆犠牲都市第2号・長崎 |
富重安雄/松本栄一 |
| 020 |
広島 戦争と都市 |
林重男/菊池俊吉 |
| 037 |
被爆直後 惨禍の映像 |
|
|
林重男/川原四儀/松重美人/菊池俊吉/宮武甫/尾糠政美/松本栄一/山端庸介/塩月正雄/富重安雄 |
| 123 |
記録写真 原爆の長崎 |
山端庸介 |
| 186 |
解説「原点」から |
黒古一夫 |
ヒロシマ・ナガサキ原爆写真・絵画集成2-惨禍の傷跡
| 頁 |
タイトル |
著者・作者 |
| 003 |
写真記録 ヒロシマ25年 |
佐々木雄一郎 |
|
8本の線と1個の点/原子砂漠/閃光/爆風/焼け跡/人間をかえせ/惨劇の証人/廃墟のヤドカリ/怒りと祈りと消えぬ爪あと/涙と叫びの夏/不死鳥のごとく |
| 101 |
ヒロシマは生きていた |
佐々木雄一郎 |
| 105 |
原爆と人間の記録 |
福島菊次郎 |
|
病苦と極貧の谷間で/狂気の出漁/7年目の通院/中村蓉子の青春/家を棄てる子供たち/そして、絶望と死と/怨念の水彩画 |
| 161 |
写真集 長崎の証言 |
日本リアリズム写真集団長崎支部 |
|
長崎原爆病院/山口仙二さん |
|
いまだ癒えず 現在を語る被爆者たち |
日本リアリズム写真集団長崎支部 |
|
日々を生きて・富永吉五郎さん、タセさん |
| 198 |
写真記録 被爆者 |
森下一徹 |
| 224 |
解説 「記録」しつづけることの意味 |
黒古一夫 |
ヒロシマ・ナガサキ原爆写真・絵画集成3-継続する悲劇
| 頁 |
タイトル |
著者・作者 |
| 003 |
ヒロシマ |
土門拳 |
|
広島原爆病院/ABCC/精薄児施設六方学園/広島市戦災児育成所/育児施設広島明成園/13年寝たきりの人・平本ツタさん 13年寝たきりの人・中村杉松さん/被爆者同士の結婚・小谷夫妻/倶会一処 |
| 153 |
憎悪と失意の日々 ヒロシマはつづいている |
土門拳 |
|
紫斑の手の娘さん/片足を切断した老婆/病理学標本/柱のガラス・窓のガラス・懐中時計/煮えた瓦/原爆スラム/百合子ちゃん/大野寮の子どもたち/私の目をかえせ |
| 179 |
原爆棄民 韓国・朝鮮人被爆者の証言 |
伊藤孝司 |
|
朴昌煥/朴守龍/尹甲秀/徐正雨/白昌基/辛福守/林玉仙/金南出/安永千/鄭登明/宋年順/金永根/韓鳳愚/李猛姫 |
| 210 |
解説 生きている〈ヒバクシャ〉 |
黒古一夫 |
ヒロシマ・ナガサキ原爆写真・絵画集成4-絶後の意志
| 頁 |
タイトル |
著者・作者 |
| 003 |
広島壊滅のとき 被爆カメラマン写真集 |
広島原爆被災撮影者の会 |
|
尾木正己/川原四儀/川本俊雄/岸田貢宜/岸本吉太/北勲/木村権一/黒石勝/斉藤誠二/空博行/林寿麿/深田俊夫/松重三男/松重美人/森本太一/山田精三 |
| 069 |
母と子で見る 原爆を撮った男たち |
「反核・写真運動」 |
|
松本栄一/菊池俊吉/林重男 |
|
| 110 |
米軍返還資料 |
林重男/菊池俊吉 |
| 125 |
米軍撮影写真 |
|
| 165 |
もの言わぬ証言者たち 原爆遺品 |
土田ヒロミ |
| 189 |
被爆から半世紀 未来への灯として |
SOLENT TESTIMONY:Artifacts form the Bombings |
| 238 |
解説 〈風化〉に抗して |
黒古一夫 |
ヒロシマ・ナガサキ原爆写真・絵画集成5-ヒロシマ
| 頁 |
タイトル |
著者・作者 |
| 003 |
原爆の図 |
丸木位里 ・丸木俊 |
|
第1部 幽霊/第2部 火/第3部 水/第4部 虹/第5部 少年少女/第6部 原子野/第7部 竹やぶ/第8部 救出/第9部 焼津/第10部 署名/第11部 母子像/第12部 とうろう流し/第13部 米兵捕虜の死 |
| 054 |
きり絵画文集 原爆ヒロシマ |
寺尾知文 |
|
閃光/原子雲/炎/川に飛び込む/水を求めて/さまよう/閃光と爆風/子どもを返せ/学徒たち/被爆者の顔/病床/平和の鐘 |
| 069 |
閃光の軌跡 |
山下蘇朴 |
|
炸裂/うずくまる少女/乳飲子を抱いて炎の海から脱出しようとする血だるまの母/炎の街で/目玉の飛出した少年/炎の中で/閃光より子を守る母/閃光に皮を剥がれた娘/炎の中の母子/死んだ子どもを焼く家族/蛆虫の棲処となったヒバクシャの体/ケロイドのある被爆者/子どもの頭蓋骨を持つ女/黒い雨の降る街/髪の抜けることを気にしながら死んだ弟/ヒロシマの鳩 |
| 083 |
〝ヒロシマ〟シリーズ |
増田勉 |
|
自画像/溶解/廃墟/屍/防空壕 |
|
| 88 |
被爆市民が描く原爆の絵 |
|
| 169 |
人間の再生を希求して 原爆に挑む画家たち |
|
|
平山郁夫/上野誠/司修/島崎庸夫/石井壬子夫/森芳雄/奥谷博/絹谷幸二/福島瑞穂/大森運夫/秀島由己男 |
| 200 |
解説 心に刻印された〈地獄〉◎黒古一夫 |
|
|
|
|
ヒロシマ・ナガサキ原爆写真・絵画集成6-ナガサキ
| 頁 |
タイトル |
著者・作者 |
| 003 |
原爆の図◎ |
丸木位里 ・丸木俊 |
|
第14部 からす/第15部 ながさき |
|
| 012 |
被爆市民が描く原爆の絵 |
|
| 055 |
原爆絵巻 崎陽のあらし |
深水経孝 |
| 096 |
原子野スケッチ |
山田英二 |
| 101 |
平和版画集 原爆の長崎 |
上野誠 |
|
長崎の顔/長崎の像/廃墟の丘/生きて残る/傷痕から/丘の上の老女/原子野A・B・C・D/ある被爆物語/火の中の鳩/はばたき/飛翔 |
| 128 |
人類の再生を希求して 原爆に挑む画家たち |
|
|
山崎善次郎/永瀬平八/小川緑/大塚伊次/寺井邦人/松添博/尾崎正義/黒崎美千子/池野巌/小崎侃/平方亮三 |
| 196 |
解説 「証言」と〈祈り〉、〈怒り〉 |
黒古一夫 |